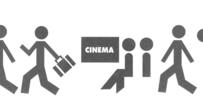しかし、サッチャーに対する評価がこれほど分かれているのは、この強みが行きすぎたためである。エコノミスト紙が「堅苦しいコントロール・フリーク」と呼んだように、サッチャーは頑固で強情で、決して妥協しなかった。閣僚の面々はその激しい闘争心を見せつけられ、首相の意見を否定しても異議を唱えても無駄だ、と何度も思い知らされた。彼女は、忠実なる反対――自身の公正さを保ち、考え方に挑戦し、アイデアを試し、理解を深めるための対抗勢力――を否定した。与党からの建設的な反対にも、野党の反対に対処するのと同じ姿勢を崩さず、強気に振る舞った。
インタビューでは、次のように語っている。「相手が真剣に挑んでくる時、体内にアドレナリンが流れ、私は反撃に転じます。そこに立って、自分に言い聞かせるのです。〈さあマギー、自分だけが頼りよ。誰も助けてはくれないのだから〉。私は戦うことが大好きでした」
サッチャーを政治的に追い詰めたのは、他人の意見を聞こうとしない姿勢や、どちらかといえば小さな国内問題――人頭税と呼ばれる新しい地方税の導入――の撤回拒否だった。主要閣僚がこの政策は裏目に出ると警告したにもかかわらず強行し、信念と頑固さとの境界線を越えてしまった。案の定、すぐに市民暴動が勃発、支持率はイギリス史上最低の20%まで落ち込み、同年末には退陣を余儀なくされた。後任のジョン・メージャーは、就任するやいなや人頭税をカウンシル(区民)税に切り替えた。これは現在も続いている。
さて、マーガレット・サッチャーのような強権的なリーダーに率直に助言するとしたら、2つの選択肢がある。まず、強硬な姿勢を取ってみずからの主張を守り抜くという優れた能力を、時には抑えること――つまり、戦うべき場を選ぶのだ。2つ目は、最悪の事態に陥らないために、得意なこととは正反対の行動を取ること。つまり、信頼できる1人あるいは複数のアドバイザーが自分に影響力を及ぼすことを許すのだ。サッチャーのように自分だけを頼りに成功してきたリーダーにとって、これは本意ではないだろう。それでも、後者の選択肢を選ぶリーダーは存在する。厄介ごとから身を守るには、自分を変えることも必要なのだ。
ただし、ここで読者に質問したい。サッチャー首相が他者の意見をもっと受け入れ、戦いという選択について学んでいたとしたら――それでも、その絶大な影響力を保てただろうか。もっと優雅に退任できただろうか。そして彼女の功績は、違った形で――頑固で融通が利かないのではなく揺るぎないものとして、あるいは賛否を招く極端なものではない形で――私たちの記憶に残っただろうか?
HBR.ORG原文:Thatcher's Greatest Strength Was Her Greatest Weakness April 16, 2013
■こちらの記事もおすすめします
影響力5つのスタイル(後編) 特性を知って使い分ける





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)