経営ははサイエンスでもあり、アートでもある
第1回でビジネススクールには、マーケティング論や生産政策、会計や人事、情報システム論、経営戦略論などさまざまな科目があると述べた。しかし一方で「経営学」という統合科目は存在せず、たくさんの科目単位を取得することでMBA(経営学修士)が取れる構造になっていると説明した。つまり経営教育の具体的な中身は、ビジネススクールの科目構成から眺めると、パーツの学問分野を集めて学生が総合化するという形になっている。
MBAとは、「Business Administration(ビジネスの経営)」のマスター(修士)という意味だが、そもそもビジネスとは何だろうか。ビジネスとは簡単に言ってしまうと、「無から儲け話を創造すること」である。経営トップは経営環境を大局的に眺め、儲けるために設計図(経営戦略)を引くことが必要だが、そのためには大局的視野、状況認知や分析力、論理性といった素養が求められる。これらは「Logical Thinking」と呼ばれる分野の能力である。
そしてもう一つ、「儲け話を創造する」のにクリエイティブなデザイン能力が求められる。英語のLogical Thinkingの反対語は、「Narrative Thinking」または「Story Thinking」である。まだ現実には存在していないフィクション(story)を物語る(narration)力もビジネスには必要なのである。セコムの創業者飯田亮氏は「経営者はビジネス・デザイナー」といっているが、まさにこれである。つまり経営者はロジカルなサイエンティストであり、同時に物語のクリエイターでありアーティストということになる。
したがって経営教育の場は、サイエンス研究の場であると同時に、アート制作のような場でもある。例えていえば、ビジネススクールは芸術大学に近い。芸大は美術評論家のようなロジックの分野で活躍する人も育てているが、もちろん一番の狙いはアーティストの育成であり、「学校教育の場でアーティストは育成できない」という人はいないはずである。ビジネススクールも同じである。アーティストとしての経営者も、座学で育成することができるのである。ではアート教育は具体的にどう構成されているのだろうか。中学や高校教育の中でも「美術」という科目があって、多くの人が経験したことがあるだろう。そこでは色彩学や絵の具の使い方、構図構成法やデッサンの技法といった技術的・論理的な授業もある。一方で、美術館に行って先人たちの傑作を鑑賞したり、また制作実習の時間もある。実際に絵具とキャンバス、あるいは粘土や彫刻刀が配られ、学生それぞれが習作をつくり、皆で論評し合うのである。



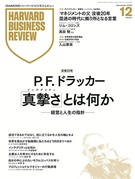
![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









