アート教育をビジネス教育に置き換えてみると、よく似ている。まず経営の手法や考え方を学ぶLogical Thinkingの授業がある。経営環境の読み方、消費者ニーズ分析の方法論、戦略設計やマネコンの基本的な考え方…等々、基本的な枠組みや理論を学ぶ場面である。一方でアーティストの卵たちが先人の傑作を見たり、自ら制作実習を行うように、経営教育の場でも先人の経営の成功や失敗事例を読み、あるいは見聞きし、そのメカニズムを考えると同時に、「自分だったら、こんな場面でどうするだろうか」を考える授業がある。さらに実際に、自らのビジネスプランを白紙に描き出し、それを教師や同僚と喧々諤々議論しながらリファインしていくセッションもある。
ハーバード・ビジネス・スクールはケース・メソッドという教育手法を開発して、学校の評価を劇的に上げた歴史をもっている。今やケース・メソッドは広くビジネススクールに取り入れられているが、これはアート実習に似た手法の一つである。アート教育に方法論があるように、ビジネス教育も方法論があるのだ。
プロ経営者たちは勉強を重ねている
この連載の第2回から第4回に載せた孫正義、藤森義明、新浪剛史といったプロ経営者たちは、私に言わせるとOFFJTのトレーニングを確実にこなしてきた人たちである。孫氏は経営書を読み漁る独学猛勉の人であり、経営者が主催する勉強会にも通い詰め、経営の知識をどん欲に吸収した人である。藤森氏と新浪氏はビジネススクールやそれ以外の場で座学の機会を得て、経営能力を磨いた人たちである。いわばこうした竹刀による鍛錬があった上で、実際に自ら手をあげてOJTにチャレンジし、成功や失敗を重ねることで地歩を築いてきたのである。
彼らにはたくさんのメンターがいて、そのサポートをうまく引き寄せることでチャンスをものにしてきた人たちでもある。こうして彼らは今日、「プロ経営者」と呼ばれるようになった。彼らは学んだ素養をベースに、間違いなく「経営している経営者」である。
繰り返して言いたい。日本企業の弱点は経営トップであり、もしミドルが経営トップ教育の機会を広く得ることができれば、日本企業は勝てる。「有能なCEOを教育現場で量産したい!」。これは日々、経営教育に携わる私たちビジネススクール教員の心からの願いなのである。



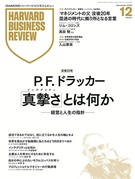
![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









