ジェイコブスの改革を俯瞰して見えてくること
このように見てくると、ジェイコブスの判断力と意思決定力は結果的には非常に優れていたということになる。面白いのは、彼が行ったチームアプローチ、入試施策、教授人事、組織文化といった組織行動論的な施策で、市場における勝利というマーケティング的なメリットを生み出したが、ジェイコブス自身はファイナンスの先生であることである。教員である以上に経営者だったということだろう。
もう一つ特筆すべきは、この変革の根幹には実はアカデミズムに対する篤い信頼があったことだ。実務家はその時代のビジネスについては詳しいが、将来を見通すためにはアカデミックな知見が必要である。これがジェイコブスの基本的な考え方である。それは米国企業の組織構造変化やチームアプローチの論拠がアカデミックな研究だったことに端的に現れている。また、優れた若い教員を雇い入れるという時に彼はすぐれた数学者、経済学者、心理学者等の若手の学者を雇い入れ、彼らに現実の問題に直面させ、深く考えさせるという手法にも現れている。
ジェイコブスが行ってきたことは果敢な意思決定とブレない実行ではあるが、あらためて整理してみると、一石二鳥と好循環を生み出すことを戦略の要諦としていると思われる。これが先述の洞察力の具体的な「姿」である。
アレンセンターでの評価が高い人を残すことで、切れ者の学者の中でも、百戦錬磨の経営者に評価されるような教員が残るようにして、MBA教育の質を上げる一方、エグゼクティブプログラムの新しいプログラムを共同開発することで、教員間のコラボ作業を促し、新しい時代の新しい教育の種をコンスタントに生み出す。
エグゼクティブプログラムを強化することで、シカゴ財界にケロッグのファンを増やし、若いMBAの就職が良くなり、人気が上がる。
入試委員会への学生の参加と候補者全員面接で点数だけの秀才よりもリーダーシップも兼ね備えた学生を選び、さらにチームアプローチで教育することにより、現代の企業のニーズに応えて人気が上がる。
いずれも一石二鳥・一石三鳥の策でありしかも好循環を生み出し、長期政権であったからこそ、その好循環の果実を享受できたのである。まさにディーンの中のディーンである。
【連載バックナンバー】
第1回:変革リーダー、ドン・ジェイコブスの素顔
第2回:ケロッグ校が個人間の競争から脱却した理由
第3回:ケロッグスクールは、卒業生・在校生が入学者を選ぶ?





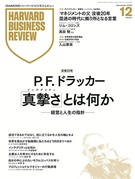
![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









