2日前:リトルロック
それはノエルにとって、財務実績のレビューのための3度目の会議であったが、今回も会議室でただ1人、他の出席者を待っていた。
工場監督者の1人が部屋に顔をひょいとのぞかせたとき、彼女は尋ねた。「会議に出るのですか」
「ええ、たぶん」と、彼は曖昧に答え、机の反対側の遠い椅子に座った。
ノエルは彼のほうに体を傾け、積極的に関わりたいという態度を示そうとした。
すると彼は後ろに身を引き、言った。「自分がここにいるべきなのかもわからないんですよ。案内は来ましたけど、他の人から転送されたものなんで」
ノエルは、このような答えを1日中聞かされていた。人々が、部門間はおろか、自分のチームの同僚とすら、意思疎通ができていないのは明らかであった。最新の財務状況について聞くことに、誰も関心がないようだ。前回の会議に顔を出した数人は、敵意に近い態度を見せた。
その日の会議前、彼女が建物に歩み入ると、そこは静まり返っていた。工場のフロアでもオフィス内でも、人々は自分の殻に閉じこもっていた。彼女が近くを通っても、誰も顔を上げさえしない。喧噪とも、連帯感とも、無縁であった。
「お願いがあるのだけど、マーシャル。あなたはマーシャルですよね?」と、ノエルは尋ねた。
彼はうなずく。
「この会議には他に誰も来そうもないですね」と、時計を見ながら彼女は言った。11時20分だ。「ここで何が起きているのか、教えてもらえませんか」
マーシャルは、しばらく黙って座っていたが、やがて肩をすくめて言った。
「いまの時点で、私にはもう失うものが何もないでしょうね。ここはもはや、働くのによい場所じゃないんです。辞めていく人や、辞めそうな人が常にいます。みんな仕事に来たくないんです。時間だから来て、時間になったら帰ります。
私は18年間ここで働いていますが、いつもこんな風だったわけじゃない。前は仕事が面白かったし、仕事のあとは同僚と一緒に出掛けましたよ。いまじゃ耳にする言葉といえば、『ただ仕事を終わらせて、さっさと帰りたい』です。連帯感なんて、ありませんよ」
「それは、コストカットのせいでしょうか」と、彼女は尋ねたが、その質問を言い終える前から答えはわかっていた。
「ええ、まさに。会社の業績が苦しかったことは、誰もがわかっています。ですが、あらゆる『引き締め』が……」と、彼はジェスチャーを交えて「引き締め」という会社側の文言を引用した。ノエルは、この遠回しな表現の馬鹿馬鹿しさに気づいて、たじろいだ。「……大きな打撃となった。それまでチームをまとめるためにあった、昼と夜の社食とか、ボーナスとかの特典は、たとえささやかでも、みんなに大きな意味があったんです。いまは部下に何もしてやれません。あと、彼らは時給15ドルでは十分じゃないですよ」
「率直に話してくれて感謝します」と、ノエルは言った。「簡単にはいかなそうね」
「さっきも言ったように、もう何も失うものはないんですよ」。マーシャルは悲しげに微笑んだ。「でも、悲しいことです。私はいまでも覚えていますよ。会社が自分に関心を持ってくれて、気に掛けてさえくれている、と感じられた時代を。でもいまでは、誰もが互いを信頼していないという感じです」
「会社があなたの信頼を取り戻せる方法は、何かあるでしょうか」
「正直なところ、私にはわかりません。本社は損益にしか興味がないという感じがします。ここ数年に行われてきたことは、すべて金のためで、人はどうでもいい。そこから伝わるメッセージは、『仕事があってありがたいと思え』です。その状況がすぐに変わる徴候は、まったく見られません」
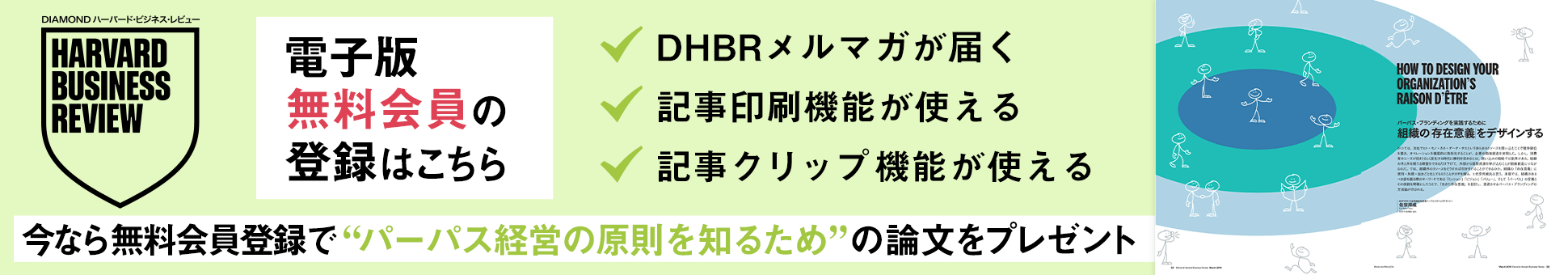





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









