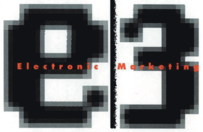米国が直面している最も深刻なテクノロジー上の問題は、安定してインターネットにアクセスできない人が国民の半数に達するということだ。ピュー・リサーチ・センターの調査によれば、米国人の10人中9人は、インターネットへのアクセスを不可欠なものと考えている。その点で、現在のような格差が存在することは由々しき事態と言える。
仕事、教育、医療、社交、さらには生活必需品の購入においても、オンラインへの移行が大幅に進んでいる。その中で、安定してインターネットにアクセスできないことによるダメージはあまりに大きい。
現在、1億6200万人の米国人は、まっとうなインターネット接続(具体的には通信速度が上りで最低25Mbps以上、下りで最低3Mbps以上)を利用できない環境にあったり、ブロードバンド通信料金を支払えなかったりする(米国のブロードバンド通信料金は世界有数の高さだ)。
もし筆者がこのような境遇にあれば、深刻な状態に陥ることになる。筆者の子どもは、学校のオンライン授業に参加するために、ファストフードチェーン大手タコベルの駐車場や、休校中の学校のそばで毛布にくるまって、Wi-Fiにただ乗りするほかなくなるかもしれない(自宅の近くでインターネットにアクセスできるのがこれらの場所だからだ)。
筆者が受診しているオンライン診療も、途中でたびたび回線が切れて中断されるだろう。職も危うくなりかねない。ズームを利用していても、回線が安定しないためだ。多くの人がインターネットに接続するために訪れる最も手近な場所であるコミュニティセンターや学校や図書館には、コロナ禍で立ち入れないケースもあった。
こうしたインターネット接続の格差は、米国社会の不平等が生む結果であると同時に、不平等を生み出す要因にもなっている。黒人と中南米系の人たちの置かれた状況は、ひときわ厳しい。
筆者らが「マスターカード・インクルーシブ・グロース・センター」の支援を受けて立ち上げた「IDEA 2030(すべての人のためのデジタルエコノミー構想)」の調査によれば、人がどこに住んでいるかによって、最も基本的なデジタルプロダクト、すなわち安定したインターネット接続の状況に大きな格差が存在する。その結果、インターネットを介した教育、医療、雇用へのアクセスはインクルーシブなものとは言えなくなっている。
しかも、米国の中でもオンライン授業の体制が特に整っていない地域(たとえば、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ケンタッキー州、アラバマ州、モンタナ州、アーカンソー州など)は、オンライン授業への移行がとりわけ必要とされている地域でもある。州当局の公衆衛生ガイドラインが十分とは言えないからだ。このような州では、オンライン診療、オンラインでの就労、オンラインでの行政手続きの体制も十分に整っていない。
議会と行政機関は、いま千載一遇のチャンスを手にしている。イノベーション能力が高く業績も傑出しているテクノロジー企業に影響力を振るい、インターネット接続の格差を解決するよう促せるのだ。テクノロジーをめぐるほかの問題が議論されて、訴訟が和解に行き着く前だからこそ、それができる。
議会は、批判の主な標的になっている4社の巨大テクノロジー企業(フェイスブック、アルファベット、アマゾン、アップル)に対して、互いに協力し合って、ブロードバンド接続を利用できない「ブロードバンド砂漠」とでも呼ぶべき地域を割り出し、インターネット接続の格差を埋めるための方策を共同で立案するよう圧力をかければよい。
それにより提供される接続サービスはユーザーに過度な利用料を課すものであってはならず、テクノロジー企業がインターネットへの門番役としての立場を利用して恩恵に浴することがあってもならない。
インターネット接続の格差を是正するための取り組みに参加すると表明したテクノロジー企業には、その後の政府との交渉を続けることを認めればよい。そうすることにより、企業が対策に加わり、行動を取るよう促すための適切なインセンティブを生み出せる。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)