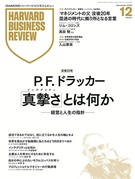異なるデータに目を向ける
コロナ禍のような厳しい環境を乗り切るうえでは、これまでと異なるデータに目を向けるとよい。たとえば、もっとシンプルなデータをいくつか組み合わせてみたり、自明ではない――場合によっては、未整理のいわば「ダークマター」的な――データを掘り下げて検討したりしてもよいだろう。
そのようなデータはしばしば、予測結果に基づいて実地の行動を取る人たちの頭の中にある(担当エリアの出来事やその他の環境について、現場の社員がよく知っているケースもあるだろう)。そのようなデータも整理して、取り込めばよい。
まず、データを集めなくてはならない。多くの予測モデルは、過去の時系列の売上げデータを土台にしている。比較的安定した環境であれば、そのようなデータをもとに、次のシーズンについて正確に予測できるかもしれない。しかし、コロナ禍のような状況では、過去に繰り返されてきたお馴染みのパターンは当てはまらない。それよりも、過去の類似の出来事のほうが予測の参考になるかもしれない。
具体的には、過去の経済的ショック(ドットコム・バブルの崩壊など)や、自然災害(サプライチェーンを長期間混乱させた巨大ハリケーンの襲来など)、そして新型コロナウイルスの感染拡大を乗り越えた地域の経験などを参考にできるだろう。
そのような過去の出来事から抽出したデータ――さまざまな国や都市で需要と供給が回復するまでに要した期間の長さなど――は、コロナ禍とコロナ後の近未来を予測するうえで役に立つかもしれない。
もっとも、過去の類似の出来事に関するデータだけでは十分でない。ほぼリアルタイムのデータも入手して、消費者の現在の姿勢と行動を把握すべきだ。
家庭用品メーカーは往々にして、売り場での正確なデータをただちに入手できない。そこで、小売業者を説得してもっとデータを提供してもらうか、消費者への直販チャネルを確立する必要がある。
そうした方策を講じても、ほかの地域のデータはすぐには手に入らないかもしれない。その場合は、オンライン・ショッピングの売上げデータ、ネット検索のパターン、スマートフォンの位置データ、ソーシャルメディアの感情分析などを駆使することにより、消費動向を把握できるかもしれない。
あるグローバルな食品会社は、新型コロナウイルスの感染拡大が始まって数カ月後に、このアプローチを実践した。レストラン、居酒屋、ホテルなど、これまで数値データに反映されていなかった販売チャネルにおける需要を把握したいと考えたのだ。そのような取り組みは、それ以前はなされていなかった。
この会社は、スマートフォンの位置データを匿名化したものを分析し、7つの製品カテゴリーに関して需要予測に役立つ20点あまりの要素を選んだ。そのうえで、それらの要素に関するデータをあるツールに投入してシミュレーションを行い、それぞれの国ごとに、ワクチンの状況、ロックダウンに関する政策、景気刺激策の内容などの要素に基づいて、いくつかのシナリオを描き出した。
また、同社は、ソーシャルメディアの投稿をもとに消費者心理を把握する試みとして、「パニック指数」も構築した。これまでのところ、このツールによる予測は、現場のセールス担当者が過去の売上げに基づいて導き出す予測よりも、実際の需要を正確に言い当てている。