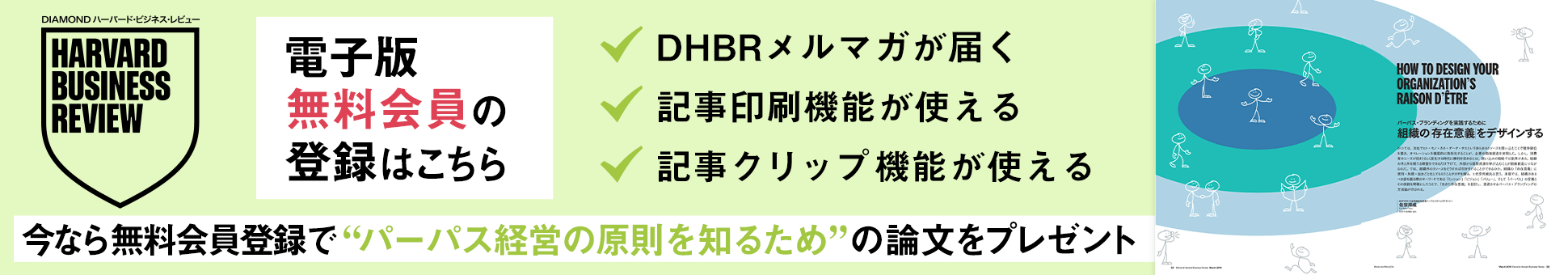(7)ビジネス界も「ブラック・ライブズ・マター」と表明した
2020年は、人種間の不正義に関する意識が大きく高まった1年でもあった。
コロナ禍がさまざまな面でその動きを後押ししたことも事実だ。実際、米国では、黒人、中南米系、先住民系の人たちは、白人に比べて、患者数、入院者数、死亡者数が2~4倍に上っている。しかし、決定的な転換点になったのは、黒人男性のジョージ・フロイドの命が奪われる場面を記録した、おぞましい動画だった。
この事件をきっかけに世界中でデモ行進が行われたことに加えて、ほぼあらゆる組織が「ブラック・ライブズ・マター」運動を支援するために声を上げ、行動を起こすこと、そして人種間の正義を尊重する姿勢を鮮明に打ち出すことを求められていると感じ始めた。多くの企業は、経営層における黒人の割合を増やし、黒人が所有する納入業者からの購入を増やすことを約束した。
たとえば、マイクロソフトは、マイノリティのコミュニティから500メガワットの太陽光発電を買い取り、そのようなコミュニティを支援する意向を表明した。化粧品小売大手のセフォラは、店頭の陳列スペースの15%を黒人所有のブランドに割り当てることを決めた(同社は、さらに包括的な行動のリストも発表している)。
シンボリックな行動が持つ意味も大きかった。食品メーカーは相次いで、時代遅れのブランドイメージを廃止する方針を明らかにした。食品・飲料大手のペプシコ傘下の「アウント・ジャミマ(ジェミマおばさん)」や、マースの「アンクル・ベンズ(ベンおじさん)」などがそうだ。米国の自動車レース、NASCARは、南北戦争時に奴隷制の存続を主張した南部連合の軍旗をレース会場などで掲げることを禁止した。
犠牲者に敬意を表しようとした企業も多い。メディア大手バイアコムCBS傘下のチャンネルは、8分46秒にわたり真っ暗な画面を表示した(8分46秒は、フロイドが警察官に押さえつけられていた時間だ)。
筆者の目にとまった中で最も力強い声明は、思いがけない企業が発したものだった。ベビーネームズ・ドットコムは、生まれてくる子どもの名前を考える際のヒントを提供している愉快なウェブサイトだ。
しかし、同サイトはこの時、シンプルな黒地のボックスを表示し、そこに白い文字で、警察や白人至上主義者によって殺害された黒人たちの名前を記した。そして、次のようなシンプルなメッセージをそこに添えた。「これらの名前の持ち主はみな、誰かの赤ちゃんだったのです」
(8)企業の責任の範囲が拡大した
2020年5月、英豪鉱業大手リオ・ティントは、オーストラリアの西オーストラリア州で鉄鉱石鉱山の規模を拡大させるために、先住民アボリジニの遺跡を破壊した。その後、この件に対する批判が高まり、ジャン=セバスチャン・ジャックCEOは辞任に追い込まれた。
『フィナンシャル・タイムズ』紙の社説が指摘したように、ジャックの辞任は、「社会的責任投資の影響力が強まっていることを裏づけている」。同紙はこの件で、同社の取締役会の責任も指摘している。
この出来事の教訓は、企業が地域コミュニティや社員などの利害関係者をどのように扱うかが、経営幹部の主たる評価基準になったということだ。2020年に起きたもう一つの重要な出来事を紹介しよう。
ウォルト・ディズニーは、実写映画『ムーラン』を公開したあと、厳しい批判にさらされた。この映画の撮影の一部は、中国でイスラム教徒のウイグル人が少なくとも100万人強制収容されている地域で行われたのだ。このウイグル人の扱いは、世界有数の深刻な人権侵害の一つだ。
このように企業は次第に、環境汚染や土地利用といった物理的悪影響だけにとどまらず、自社の企業活動が社会に及ぼすもっと幅広い「インパクト」について責任を問われるようになっている。社会の不正義を助長する要素は、すべて問題にされる時代が訪れつつあるのだ。
(9)企業が社会の重要な柱を守った
2020年には、世界中の国々で民主主義への脅威が強まった。その傾向がとりわけ甚だしかったのが、米国とブラジルだった。しかし、そうした脅威と戦うために、企業がさまざまな形で行動を起こした。
まず、投票へのアクセスの問題。米国では、2000社近くの企業が「タイム・トゥ・ボート(投票の時)」という非営利プロジェクトに参加し、社員が投票を行う時間を確保できるように配慮することを約束した。ターゲット、ワービー・パーカー、コンパス・コーヒー、ギャップ傘下のオールドネイビーは、投票に行く社員に有給休暇を認めた。
また、膨大な量の偽情報が社会に及ぼす脅威も高まっている。そうした情報は、ソーシャルメディアで拡散されることが多い。この問題に対処するために、アディダス、ベストバイ、コカ・コーラから、ユニリーバ、ヴァンズ、ホワイト・キャッスルまで、世界屈指のブランドが続々とフェイスブックへの広告出稿を取りやめた[注]。その広告費は莫大な金額に上った。
偽情報の問題は、科学への攻撃、科学の信頼低下にも密接に関係している。反科学的な動きは、近年で最も危険な傾向と言えるかもしれない。
208年の歴史を持つ『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン』誌と、175年の歴史を持つ『サイエンティフィック・アメリカン』誌は、2020年米大統領選で歴史上はじめて特定候補への支持を表明した。両誌ともに、支持したのはジョー・バイデンだった。『サイエンティフィック・アメリカン』の表現を借りれば、「ドナルド・トランプはエビデンス(科学的根拠)と科学を拒絶することにより、米国と米国民に深刻なダメージを及ぼした」からだ。