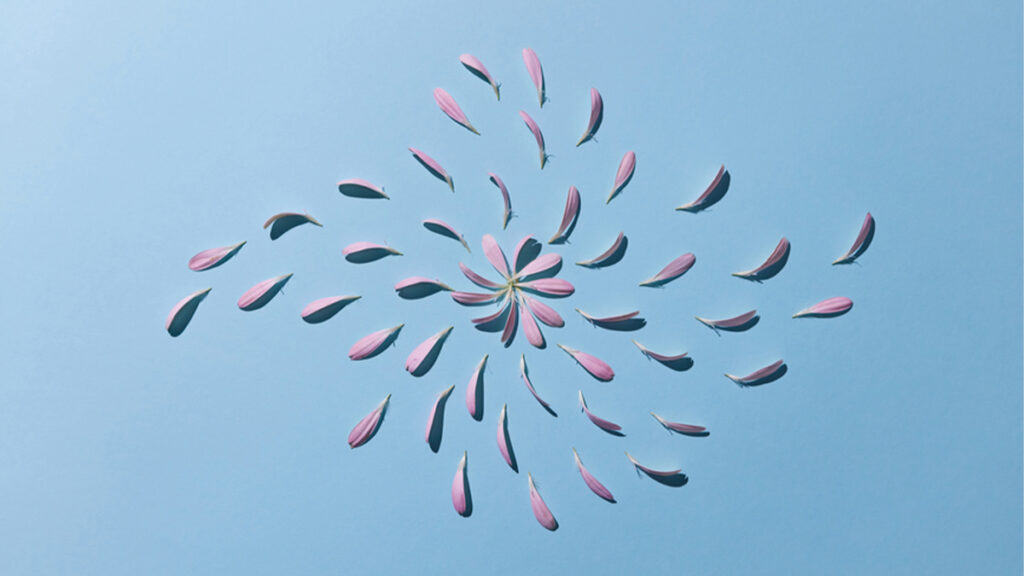
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
「希望を持つ文化」が前向きに働く時、裏目に出る時
感情は日常生活の一部である。それは仕事でも、それ以外でも同様だ。仕事という文脈においては、特に組織が野心的で困難なプロジェクトに取り組んでいる時、感情が生まれやすい。
たとえば、大勢の従業員がプロジェクトのマイルストーン達成を祝い、喜びを分かち合うことがある。あるいは「次なる目玉」として期待された製品のローンチが失敗に終わったことを嘆き、悲しみを共有することもある。
このような感情は、愛情(ロマンチックなものではなく)、おそれ、陽気さなどとともに、組織が機能するうえで重要な役割を果たすことが実証されている。しかし「希望」は、組織が困難な目標に向かって努力する際、頻繁に呼び起こされるにもかかわらず、組織研究において軽んじられてきた感情の一つだ。
実際、組織がメンバーに対して、困難に直面しても「希望を持ち続ける」ように励ましたり、製品やサービスを通じてクライアントや顧客に「より希望に満ちた未来」を約束することは、一般によく見られる。
希望は、表面的には完全にポジティブな感情のように思える。しかし、筆者らの研究では、組織が困難な目標に取り組むうえで、希望はより複雑な役割を果たしていることが明らかになった。組織レベルでは、希望は以下の3つの要素で構成される。
(1)組織のメンバーは、希望に満ちた未来へのビジョンを共有する必要がある。つまり、現在の状況を乗り越えて、より望ましい結果を達成することが可能であると信じなければならない。
(2) 組織のメンバーは、みずからが適切だと考える手段と行為によって、目標に到達することができると信じなければならない。
(3)組織は目標に向かって、モチベーションに関する共有感覚を具現化しなければならない。希望に満ちた組織は、困難な状況に陥った時、それを切り抜けるために必要なものを備えていると信じている。
希望とは、部分的には「よりよい未来が実現可能である」という考えを具現化するものだが、そのためには同時に、現在の状況は理想的ではなく、時には厳しいものであると認識することが必要となる。リーダーは大きなビジョンを描く時、たとえ組織全体に強い希望が満ちていたとしても、失敗する可能性があることを認めなければならない。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









