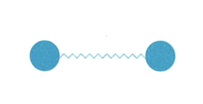よりよい働き方を見つけるために、データを使う
データとテクノロジーは、仕事がどう遂行されているかを理解するための新しく強力な手段を生んできた。監視ツールは個人に焦点を当ててきたが、企業にとっての真の好機は、自社のシステムを理解するための鏡としてこれらのツールを使うことである。
監視は対立を生じさせるが、仕事環境(または人々の仕事体験のあり方)を理解するためのアナリティクスは、従業員と会社の方向性が一致する形で活用できる。より効率的でストレスの少ない仕事環境は、従業員体験と生産性の両方に寄与する。
ほとんどの企業にはすでにその実践例がある。小売企業は、カスタマージャーニーの構築に何百万ドルも投資する。以前はアンケート調査とインタビューを通じて行われていたことだが、大規模に実施するためにはテクノロジーとデータを用いて、顧客体験を理解する必要がある。その結果、体験を効率的かつ直感的で快適なものにすることができる。
顧客と同じようにデジタルワーカーも、毎日仕事をする中で大量のデータを生み出す。雇用主はそのデータを用いて、ワークグラフ──チームが仕事をどのように体験しているかを示すデジタルマップ──を構築し、プロセスが破綻している部分を見つけて改善できるのだ。
責任と共感を持ってこれを実践するために、雇用主はワークグラフの構築に際して以下のルールを遵守しなければならない。
すべてのユーザーを匿名化する
ユーザーの特定や指定ができないようにする。ユーザーの作業のスクリーンショットやビデオは使ってはならない。ユーザーを名前で特定することはプライバシーの侵害となり、システムに対する信頼を低下させる。
ユーザーから寄せられるデータをチームに集約する
集約によって匿名化される。このプロセスの焦点は、チーム内で共通するパターンの特定であり、個人の時間の使い方を監査することではない。目標はチーム全体のための業務改善だ。
オプトインを全ユーザーの標準設定にする
自チームの業務パターンの改善に向けたデータ提供への参加は、完全に自由意志とすべきだ。これにより、ユーザーは取り組みを有益と考える場合にのみ参加できるようになる。
情報の非対称性をなくす
分析とデータと知見を、データ提供者であるエンドユーザーに公開する。そのデータはチームについて何を物語るのか、摩擦部分はどこか、会社はチームをどのように支援するつもりなのかを見てもらい、従業員との対話集会でその取り組みについて話をする。
ワークグラフのデータはチームの仕事体験を改善するためのものであり、個人を特定して害を及ぼす意図はないことを明示しよう。
共同での問題解決に移行する
チームの日々の体験における摩擦を減らすために、どのような対策を取るべきかを決める際、従業員を意思決定に参加させる。たとえば、業務パターンのばらつきが大きいことをデータが示している場合、追加の訓練が必要なのか、あるいは業務を合理化すべきなのかをチームとともに話し合う。各チームに固有の問題を自分たちで解決する動機を与えるために、ワークグラフをみずから構築してアクセスする権限をチームに与えよう。
パターンと対策を、各チームごとに「ローカライズ」する
各チームの個別の課題を理解し、そのチームに合わせて解決策を調整する。たとえば、トップダウンで「すべてのチームは自動化によってコストを10%節約せよ」という画一的な絶対命令を出しても、効果がないかもしれない。それよりも、チームによっては訓練のほうがより適切な選択肢かもしれない。
これらのルールは共感ファーストのアプローチを重視し、データソースが民主的であるという点で従来のツールとは異なる。ユーザーは自主的にデータの提供に参加する。診断と是正措置の対象は、個人の働き方ではなく、チームの仕事体験のあり方である。加えて、従業員と会社の利害を一致させることにもなる。破綻している部分を改善すれば、双方が恩恵を得るからだ。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)