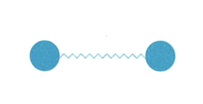経営陣は共感をどのように拡大すべきか
成長の促進、人材の保持、コスト管理、組織変革のマネジメントなど、何であれ、すべての最高幹部の任務において共感が中心となる。経営陣は通常、従業員体験に関する理解を深めるためにインタビューを行うが、大規模な実施は極めて難しい。監視ツールを用いるという方法もあるが、従業員のプライバシーが侵害される。
一方でワークグラフは、組織全体のデジタルマップであり、プライバシーを侵害せずに最高幹部がチームの仕事体験のあり方を広く理解するための役に立つ。したがって、組織で変革のマネジメントとそれを推進するための新たなデータソースとなるのだ。
組織全体における従業員の仕事体験のあり方を理解するために──言い換えれば、共感を拡大するために──このツールを本当に役立てるには、さらにいくつかの手段を講じるとよい。
第1に、ワークグラフを組織全体に導入し、従業員の仕事環境に関する質の高いデータの入手を最優先事項とすべきである。自分たちの個別のワークグラフを構築してアクセスする権限を、チームに与えると効果的だ。それによってチームはこのツールの有用性を確認でき、導き出された知見を活用しやすくなる。
ただし重要なポイントとして、このアプローチから十分な恩恵を得るには──つまり仕事環境の改善に向けて、ワークグラフからの知見に基づいて行動できるようになるには──導入を広範囲かつ適切に行う必要がある。
第2に、経営幹部会議および従業員との対話集会で、ワークグラフのデータを話題に取り上げよう。従業員からフィードバックを求めることで、重要な知見と背景状況が提示されるかもしれず、経営陣の理解が深まる。
ここでのポイントは、ワークグラフのデータはチームの仕事体験を改善するためのものであり、個人を特定して害を及ぼす意図はないと明示することだ。
最後に、チームを巻き込み、共感をもとにした経営判断を行うために、ワークグラフからの知見を活用しよう。たとえば、株主に1株当たり利益(EPS)の増加を約束する際には、ワークグラフのデータを用いて仮説検証をしてみるとよい。(EPSの増加に必要な)生産性は、実現可能だろうか。その約束は、現場のチームが現在直面している問題を踏まえているだろうか。
従業員の仕事を、会社がいかに困難にしているか──その可能性を考慮しないまま、彼らから搾り取ろうとする企業があまりに多い。しかし、破綻したシステムの中で生産性をより高めようとしても限界があり、そのコストも高くつく。
生産性を高めるためにデータを使うべきという直感は、間違っていない。だがその方法がお粗末であれば、信頼と士気は急速に低下しかねない。ワークグラフのデータが実際にもたらしうる潜在的利益を、企業が現実のものとするには、データを使って自社を厳しく見直す意志が必要だ。最終的にはそれが、全員にとって望ましい結果をもたらすのである。
"Monitoring Individual Employees Isn't the Way to Boost Productivity," HBR.org, October 27, 2022.





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)