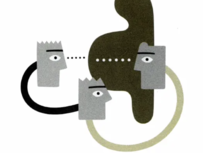共感の重要性
仕事環境における摩擦の原因を見つけて解決することは、チームの生産性向上につながる。共感を用いて仕事を当事者の視点から理解することで、その環境で何が破綻しているのか、その破綻が従業員にどう影響しているのかを明らかにできる。
このアプローチはまた、チームのモチベーション──仕事に対する意欲、満足、エンゲージメント──を高めるためにも使うことができる。
ただし、共感の観点から仕事を理解するには必然的に、問いを投げかける必要がある。
生産性追跡ソフトウェアが、以下の問いに答えられるかを考えてみよう。
・ティムが電話に費やした時間は何分か。
・ティムが席を外していた時間はどれくらいか、および何回か。
・ティムの今日のキーストローク数は、昼食前と昼食後でそれぞれ何回か。
まず、これらの問いへの答えはすべてティムに関してであり、彼のチームについてではない。これらに答えることで、彼のプライバシーは失われる。そして分刻みの監査が突きつけるのは「あなたは常に監視され、
さらに、これらの問いは彼の仕事の環境を無視している。仕事が「どのように」遂行されているのか、そのプロセスで何が破綻しているのか、それをどう改善しうるのかが明らかにならない。
では、仕事の体験に焦点を当てる問いについて考えてみよう。
・非効率なプロセス設計が原因で、チームは同じ仕事を複数の方法で行っていないだろうか。
・顧客へのサービスを向上させるために、チームはどの部分で訓練やメンタリングを必要としているのか。
・お粗末なユーザーインターフェースやユーザーエクスペリエンスがストレスを生み、チームの顧客対応に遅れをもたらしていないか。
・テクノロジーの問題が、どのようにチームに遅れをもたらしているのか。チームは協働と問題解決のための適切なツールを備えているのか。
これらの問いは集計され、匿名化したチームデータによって答えを出せるため、個人のプライバシーは守られる。焦点は従業員の仕事の環境と、チーム全体に共通する仕事の破綻パターンだ。消費時間を分刻みで計算するという狭量な行為も回避される。
ここでの共感とは大まかにいえば、個人ではなくチームに焦点を当てること、そして個人の具体的な行動ではなく人々の仕事の環境に焦点を当てることだ。したがって共感的なアプローチは本来、ボトムアップであり、インクルーシブ(包摂的)であり、各チームの個別の仕事体験に応じて文脈化される。そして個々のユーザーのプライバシーを守り、データによる分析が可能な事項の範囲を制限する。
筆者らの最近の調査では、次のことが明らかになった。組織におけるアプリの急増によって、フォーチュン500に属する企業のユーザーは、仕事を完遂するためにアプリ間での切り換えを1日最大3600回も強いられている。このため仕事中は頻繁に、おのずと注意散漫にならざるをえない。
この状況に対し、2つの見方がある。
「搾り取る」型のアプローチ
「これが我々のやり方だ」と開き直り、破綻したシステムの中で、従業員に生産性を上げるよう圧力をかける。すなわち、従業員の個人用IDを作成したうえで、達成される活動の量と進行スピードを監視し、少しの時間も「無駄」にさせないよう徹底する。切り換え作業を、さらに多く行わせることになるかもしれない。
これによる負担があまりに大きいと判明した場合は、作業を外注し、ほかの誰かの問題にしてしまえばよい。
共感的なアプローチ
「我々は従業員に、このような時間の過ごし方をさせたいのだろうか。自社の環境は従業員にとって、全力を尽くす動機となるだろうか」と自問する。
切り換えの負担の問題を解決するために、業務構造が適切ではない部分、アプリケーション間に統一性がない部分、複数のシステム間にデータが散在している部分を探す。これらの問題の解決に向け、さまざまなソリューションが必要となる。たとえば自動化や、ITシステム改善への投資、さらには今後の企業用ソフトウェアの構成を変えることも含まれる。
必要以上に大変で、非生産的な仕事を強いることには、代償を伴う。一つには、従業員の意欲が低下しやすい。新たなスキルセットを学ぶ機会がない場合はなおさらだ。それに加えて、前述の事例では、お粗末な業務設計によって年間の生産性の9~10%が失われている。
従業員の取引処理の完了スピードを監査すれば、漸進的な改善につながる「可能性」はある。だが、システムの真の問題に対処することにはならない。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)