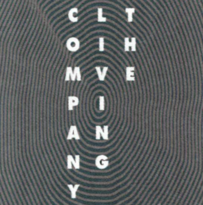なぜインフレが起きるのか
端的に言えば、インフレは、供給に対して需要があまりに多すぎることが原因で起きる。もっと厳密に言うと、元FRB議長のベン・バーナンキがアンドリュー・エーベルと共同で執筆したマクロ経済学の教科書で記しているように、「インフレは、ある特定の価格における需要の総量が、その価格における供給の総量を上回る場合に起きる」。
では、需要が供給を上回る原因は何か。そのような現象が起きる理由はいくつかある。そして、それらの理由を理解するためには、デヴィッド・モスが著書『世界のエリートが学ぶマクロ経済入門』で挙げているマクロ経済の3本の柱について考えることが有益だ。
モスが言う3本の柱とは、産出高(経済における生産量はどの程度か)、貨幣(人々がどれだけの貨幣を保有、もしくは容易に入手できるか)、期待(次に何が起きると、人々が予想しているか)である。この3つの要素はいずれも、インフレに関係している。
供給のショック
しばしば、インフレは、供給のショックが原因で起きる。エネルギーなど重要な経済的投入物に大きな混乱が生じるケースである。たとえば、戦争が原因で多くの産油地帯で原油生産が滞れば、エネルギー価格は上昇する。エネルギーは、ほぼすべての商品やサービスの供給に不可欠な投入物なので、エネルギー価格が上昇すれば、ほかの商品やサービスの価格も上昇する。このようなインフレはしばしば「コストプッシュ・インフレーション」と呼ばれる。
理屈の上では、ある商品やサービスの供給量が減れば価格が上昇し、結果として、その商品やサービスを買いたいと思う人が減り、需要と供給の間に新しい均衡が生まれるはずだ。しかし、現実はそんなに単純ではない。供給のショックは、持続的な物価上昇の引き金を引く場合もあるのだ。
ほかに好ましい代替品が存在しないため、その商品の価格が上昇し続けるケースも多い。あるいは、供給のショックがいつ終わるのか、そもそも終わる時が来るのかがはっきりせず、物価上昇が止まらないケースもある。また、最初の物価上昇により、将来の物価に関する人々の予想が変わる結果、物価が上昇し続けるケースもある。
マネーサプライ
インフレには、需要サイドの要因もある。マネーサプライ(通貨供給量)が増加すれば、インフレが起きる場合が多い。
「銀行口座や財布の中のお金が増えれば、消費者はたいてい、商品やサービスを買う新しい理由を見出すものだ」と、モスは著書で記している。「しかし、供給が増えなければ、消費者の需要が高まり、結果として価格が上昇し、インフレが進行する。『あまりに多くのカネがあまりに少ない商品やサービスを追いかける』時にインフレが起きると、経済学の世界ではよく言われる」。この現象は、「デマンドプル・インフレーション」と呼ばれることがある。
インフレをマネーサプライによって説明する考え方は、経済学者ミルトン・フリードマンの主張によって広く知られるようになった。インフレは「いついかなる場合も貨幣的現象である」というフリードマンの言葉は非常に有名だ。たしかに、マネーサプライがインフレを引き起こす場合があることは事実だが、フリードマンの言っていることは極端すぎる。むしろ、インフレの原因を一つだけ挙げるとすれば、それは人々の期待なのかもしれない。
期待とスパイラル
インフレに関する多くのモデルでは、インフレを生む原因はマネーサプライの増加ではなく、マネーサプライの「想定外」の増加だとされている。直観的に考えても、マネーサプライの増加に伴って需要が増加すると誰もが予想していれば、その需要を満たすために供給も増えるはずだ。インフレの引き金を引くのは、想定外の需要増(もしくは供給減)なのだ。
そして、実際にどのくらいのインフレが起きるかは、人々がどのくらいのインフレを予想しているかに影響される。商品やサービスの値段が高くなれば、働き手が給料で購入できる商品やサービスの量が減ってしまう。そこで、物価が上昇すると予想される場合、人々は生活水準を維持するために、雇用主に対して賃金の引き上げを求める。
一方、企業側は、賃金水準の上昇が予想できれば、さらに自社の商品やサービスの価格を引き上げようとする。こうして「賃金・物価スパイラル」が起こり、ますますインフレが進行する。しかし幸い、このようなスパイラルが起きることは珍しい。
人々の期待が持つ影響力は大きいため、中央銀行は、物価目標の達成に関する中央銀行への信任を維持し、インフレに関する人々の予想を中央銀行の物価目標に近い水準に「固定」しようとする。具体的には、中央銀行が物価目標を達成できると人々に信じさせ、中央銀行が示す見通し通りに物価が変動すると思わせ、毎月のインフレ統計を気にする必要を感じさせないことを目指すのだ。








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)