
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
インド子会社の評価額が高い理由
欧州消費財大手ユニリーバPLCの株価純資産倍率(PBR)は2022年末の時点で6倍、インドの子会社ヒンドゥスタン・ユニリーバは12倍だった。この差は、インド子会社のほうが設立が遅いから、あるいは会社規模が小さいからという理由で生じたわけではない。子会社にはその前身を含めて90年の歴史があり、その時価総額も760億ドルに達している。これはユニリーバに限った話ではない。
スイスを拠点とする世界最大の食品飲料会社ネスレSAの場合、そのPBRが6倍に対して、インド子会社のPBRは実に82倍に上る。米工業・事務用品大手3Mの場合も、そのPBRは4.2倍だが、インド子会社は12.7倍だ。特殊化学品を主力とする世界的な化学メーカーBASFでは、ドイツの親会社のPBRがわずか1倍しかないのに、インド子会社は4倍に上る。重工業の世界的企業シーメンスでは、ドイツの親会社が2倍に対して、インド子会社が10倍である。いずれもかなり大きな差があり、インド子会社の企業評価額が単独で親会社より高いケースさえある。
親会社とインド子会社のPBRにこれほど差があるのはなぜか。それは、親会社が自国の市場で低迷しているのに対して、インド子会社にはより高い成長見通しがあり、より高い収益性、より効率的な資産活用を実現しているからだ。だからこそ、すべての多国籍企業にインド市場戦略が必要なのである。それがなければ世界で最も有望な市場機会を逃すことになる。
そもそもPBRは、企業の資産に関しての市場の評価額を表す。成長見通しが良好で(収益成長率で測定)、事業の収益性が高く(売上高利益率で測定)、資産を効率的に活用しており(総資産回転率:売上高÷総資産で測定)、資本コストが低い企業ほどその値が高くなる。
このうち資本コストの低さは、インド子会社の PBR が高い理由にはならないだろう。企業の資本コストは、その国の信用力を示すソブリン格付けによって制限される。インドの格付けはBBBマイナスで、米国、ドイツ、スイスのAAAよりはるかに劣る。したがって、ほかのすべての条件が同じであれば、インド子会社がG7諸国の親会社より資本コストが低いということは考えにくい。したがって、PBRの高さは、収益性や成長見通しの高さに関連しているはずだ。
過去5年間のユニリーバ・インドの収益の年平均成長率(CAGR)は9.6%で、親会社の2.2%の4倍である。なお、親会社の成長率にはインド子会社の成長率も含まれており、その貢献がなければ親会社の成長率はさらに低くなるだろう。収益性に目を向けると、総資産利益率は親会社の8%に対し、インド子会社は11%である。驚くべきは、親会社の利益率13%に対し、インド子会社の利益率が17%とさらに高いことだ。
インド市場では、ターゲット層の購買力が低いため、ユニリーバーの製品がより安価に販売されている。それにもかかわらず利益率が高いのは、市場の集中度が高く、価格決定力があるためと考えることもできるが、その可能性は低いだろう。なぜなら、インドの消費財市場は、コルゲートなどほかの多国籍企業や、パタンジャリ・アーユルヴェーダのような革新的な地元の競合など複数の競合企業と熾烈な競争が行われており、インフォーマルセクター(露天商や無許可の業者等)を含めて市場に安価な代替品が数多く出回っている。したがって、利益率が高い理由として最も考えられるのは、生産と流通のコストが安く済むことであり、事実、インドはそれらのコストが低い。
ほかの多国籍企業も同様だ。ネスレ・インドの利益率は14.2%で、親会社の9.8%に対して高い。総資産回転率は196%で、親会社の69%を上回っている。シーメンス・インディアの場合、利益率が10.6%で、親会社の4.8%を超えている。総資産回転率も91%と親会社の51%より高い。
これらの数字が示すとおり、市場の成長、資産活用、収益性などほぼすべての面で、インド市場は多国籍企業にとって本国の市場より魅力的な展望がある。
成長するインド市場
インドでは消費財を求める都市部の中間層が急成長している。世界経済フォーラムが的確にまとめているように、「数字を純粋に見れば、21世紀最大の都市変容が(中略)インドで起きている」。
インドの人口に中間層が占める割合は、2005年の14%から2021年には31%に増加し、2047年には63%に達する勢いだ。調査会社フロスト・アンド・サリバンの予測も同様で、貧困層の割合が減り続ける一方で中間層が増えており、その割合は2019年の28.5%から2030年には53.8%へとほぼ倍増する見込みだ。
インドの中間層は、2020年の所得が米ドル換算で6700~4万ドルの世帯と定義される。購買力平価で調整すると、米国の年間所得2万2700~13万6000ドルに相当する。その人口の多さから、中間層の割合が少し変わるだけでも大きな影響がある。現在、インドは14億3000万人と世界で最も人口が多く、米国(3億3400万人)とEU(4億4700万人)の人口を合計した数の約2倍になる。中間層が28.5%から53.8%に約25ポイント増えるということは、現在の人口で計算しても、3億5000万人増加することになる。
インドの都市中間層の増加は、3つの要因が組み合わさっている。すなわち、小さな町の急速な都市化、よりよい雇用機会を求めて人々が農村部から都市部へ移動すること、そして生活の向上だ。自給自足の所得水準の暮らしから、可処分所得が多く野心的なライフスタイルへと進化している。人口100万~250万人の小都市は、年10%という天文学的なスピードで成長している。なかでも若年人口が急増している16の都市は「ブームタウン」と呼ばれている。これらの都市では中間層の割合が拡大し、都市中間層の成長率に拍車がかかっている。

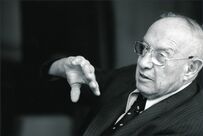







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









