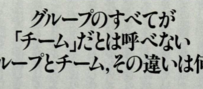2. 混雑した空間ではCDCの基準に満足せず、1時間当たり12回の空気交換を目指す
水槽で魚を飼育する場合は、バクテリアの増殖を抑えるために、濾過システムを使って少なくとも1時間に4回以上(つまり15分に1回以上)、水を浄化している。これは、4ACH、すなわち1時間に4回以上、室内の空気を交換するのと同じ頻度だ。
しかし最近まで、建物内のウイルスの伝播を有効に減らすために、どれくらいの頻度で空気を入れ替えればよいのかという明確な基準は、示されていなかった。そこで、2022年、筆者らは『米医師会雑誌』(JAMA)にCDC宛ての質問状を寄稿し、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために1時間にどれくらいの回数の空気交換を行えばよいのかを明確に示してほしいと訴えた。
CDCの研究員らの回答は、5~6ACHの空気交換が行われている空間で新型コロナウイルス感染症の集団発生が起きた例は把握していないが、一部の状況(飛行中の航空機内や病院の空気感染隔離室など)では、12ACH以上の空気交換が必要かもしれないというものだった。
空間内にいる人の数が増えれば、ウイルスが伝播する確率も高まる。そこで、そのような環境においては、リスクを減らすために空気交換の回数を増やし、対人距離を取ることが必要とされる。たとえば、カリフォルニア州公衆衛生省は、学校では最低でも6ACH、できれば12ACHの空気交換を行うことを推奨している。
3. コスト抑制のために業務時間中だけ空気清浄機を作動させ、フィルターは定期的に交換する
フィルターとファンは、メーカーが推奨しているタイミングで定期的に交換するか、コストを抑えたい場合は、検査を行って性能が容認可能な水準を下回った場合に交換すればよい。検査をすれば、フィルターとファンが予想より長持ちしているか、それとも予想より早く性能が低下しているかを判断できる。たとえば、フィルターに微粒子が詰まっていたり、激しい森林火災により多くの煙が流れてきた後、微粒子を濾過する能力が失われていたりする場合もあるだろう。
病院などでは、1日24時間、週7日ずっと空気清浄機を作動させ続けなくてはならないかもしれない。しかし、多くの企業の場合は、空間に人がいる時間帯、つまり業務時間(一般的には午前9時~午後5時)に空気清浄機を動かすだけで十分な場合も多い。そのように標準的な業務時間だけ用いれば、空気清浄機の耐用期間は4倍長くなり、消費電力も4分の1で済む。機械のオンとオフの切り替えは、その場にいる人物が手動で行ってもよいし、安価なモーションセンサーを使ってもよいだろう。センサーにより人間の活動が確認できなくなった20分後に、機械が自動的にオフになるように設定すればよい。
* * *
企業は、本稿で紹介した3つのステップを実践することにより、費用対効果の高い方法でCDCの新しい基準を遵守し、新型コロナウイルス感染症や、森林火災の煙、アレルギー物質など、空気を介してもたらされる危険から人々を守ることができる。以上のシンプルなステップを通じて空気を浄化すれば、すべての人が恩恵に浴するし、免疫機能が弱まっている人や妊娠している人、高齢者、子ども、慢性の心疾患や呼吸器疾患を患っている人など、高いリスクにさらされている人たちも参加しやすい空間をつくることができる。
"Making the Air in the Office Cleaner," HBR.org, July 05, 2023.









![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)