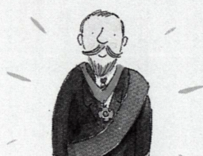-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
世界的大企業が続々と変わり始めた
──前回の記事:サステナビリティを軽んじる古い考え方の問題点に立ち向かう(連載第9回)
──第1回はこちら
2019年8月、「ビジネス・ラウンドテーブル」──世界的大企業のCEO181人(当時)が参加する民間組織で、アップル、ウォルマート、アマゾン・ドット・コム、アメリカン・エキスプレス、BP、エクソンモービル、ゴールドマン・サックスなどのトップを含む──が声明文を発表し、〝利益の追求のみが企業の役割である〟とする見方をはっきりと否定した。声明文では、顧客、社員、そして国に価値を提供するという決意が述べられていた。
「我々はダイバーシティとインクルージョン、威厳と敬意を育てます」と声明は言う。「規模の大小にかかわらず、我々の使命達成に協力してくれる他社に対し、良きパートナーとして役立つよう全力で取り組みます……地域社会の人々に敬意を払い、事業全般を通して持続可能性を重視することで環境を保護します」
当然のことながら、この声明文が突如として巨大な変化を署名各社にもたらしたわけではない。このお墨付きによって、心にパーパスを抱いて行動しようとする人が急に楽になったわけでもない。本書の序章(本連載第1回~第5回)で述べてきた通り、そのような変化を生み出すのはたやすい課題ではない。
ユニリーバのサステナビリティ分野における取り組みによって、ポール・ポールマンが世界中のメディアから熱烈な取材を受けていたのと同じ頃、同じくフォーチュン500企業であるNRGエナジー(主に石炭を使う電力会社で、米国第2位の発電量を誇る)のCEOデイビッド・クレーンは、2030年までに石炭消費量を半減し、2050年までに90%削減すると公約した。彼は、自社が石炭で稼いだ利益を再生可能エネルギーへの投資につぎ込み、世界最大の汚染企業の1社からグリーンの巨人へと変身すると決意したのだ。
2014年にこの方針を始めるとき、クレーンは次のように述べた。ポールマンの口から出たとしても不思議はないセリフだった。「私たちがヨボヨボの老人になったとき、子供たちが我々を椅子に座らせ、反目と失望の入り交じった眼差しでじっと我々の目を見て、こうささやくでしょう。『わかっていたよね……なのに何もしなかった。どうしてなの』と。このままでは、そんな日がやってきます」
この取り組みの結果はどうなったか──。NRGエナジーの株価は下がり、クレーンは取り組みを宣言してから2年もせずに辞めさせられた。同社が再び汚染企業へと舵を切り直すと、株価は急上昇して元に戻った。ユニリーバと同じ道を行こうとしたNRGエナジーの取り組みは、失敗例としてたびたび話題になった。クレーンは米グリーンテック・メディアにこう語っている。
「(気候問題という)大義のために私が際立った貢献をすれば、化石燃料企業がグリーン企業へと変身する方法を示せると思っていました。これこそが、私が必死でやろうとしたことでした。しかし、私がクビになり、それを実現できなかったことで、正反対のメッセージを示すことになりました。自分の会社を改革して報酬をもらえると思っているなら、それは不可能ですよ、と」
NRGエナジーのエピソードは、まだ世界が企業の役割によって資本主義者の楽園に変わってはいないことの証左だ。とはいえ、ビジネス・ラウンドテーブルの声明文のような声が出てくることは、変化が進みつつあることを暗示している。今日、業績のいい企業で、世間に対して堂々と「当社はそんな問題はいっさい気にしません」と言える企業を見つけるのは極めて難しい(率直に言えば、業績の悪い企業でも同じことだ)。NRGエナジーでさえ、自社のウェブサイトでサステナビリティの取り組みが成功していると喧伝しているほどだ。
たんに世評を気にしているからに過ぎない、と見る人もいるだろうが、それだけでは説明できない。こうした問題に取り組むべきだという圧力は極めて強く、〝うちは気にしない〟と公言できる企業は1社もないほどだ。最低限のことをするだけでなく、こうした問題に積極的に取り組む企業、ただ大事だと認識するにとどまらず、行動に踏み出そうとする企業は、実はこれらの問題に取り組むことが企業としての成功をもたらすことに気づきつつある。
ビジネス・ラウンドテーブルの声明文は、要するに生き残りのためなのだ。少なくとも社会善の価値を認めない限り、企業は今後生き残っていけない、ということだ。実際、こうしたテーマを大切にし、全力で取り組む企業が成功するようになりつつある。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)