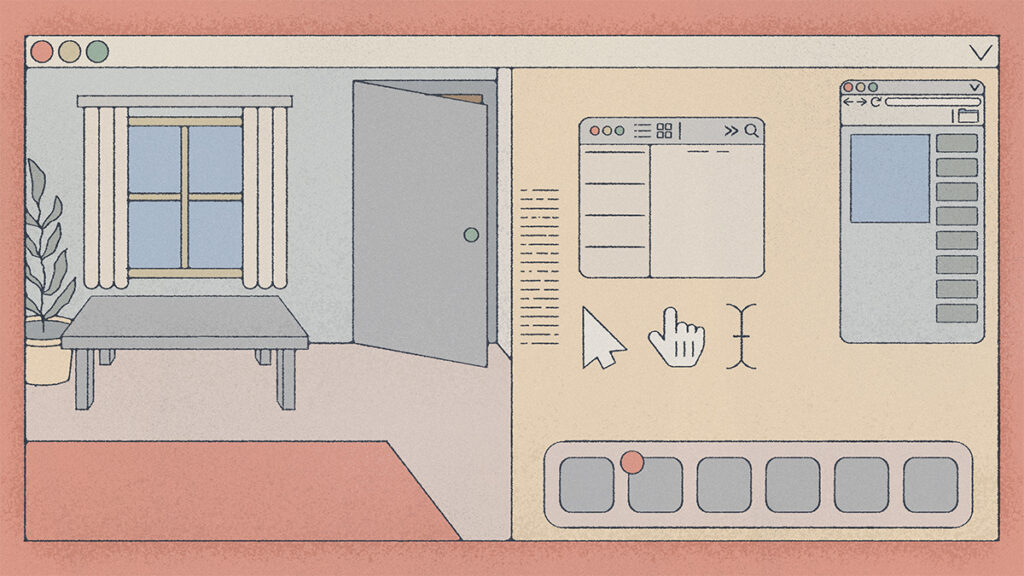
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
働き方に関する議論は二極化が進む
リモートワークの利点や危険性をめぐる熱い議論が、至るところで交わされている。リーダーの生産性に関する懸念には根拠がないという主張もあれば、イーロン・マスクのような著名な経営者が、在宅勤務をしている人は「真剣さに欠ける」と示唆するものもある。
この問題は、RTO(リターン・トゥ・オフィス)やハイブリッドワーク、フレキシブルワークなど、さまざまな枠組みでとらえられており、各者の主張が極端であることは間違いない。そして、賛否両論あるそれぞれの意見に共通しているのは、その主張が強硬で凝り固まっていることだ。
リモートワークに対する相反した視点は目新しいものではないが、その緊張はますます高まっている。たとえば、アマゾン・ドットコムでは従業員グループが、出社日数に関するオフィスポリシーに反発してウォークアウト(抗議のための一時的な職場放棄)を行った。ファーマーズ・インシュアランスの従業員は、CEOがリモートワークに関するポリシーを撤回したことに対し、組合を結成するか退職すると迫っている。グーグルは最近、従業員のオフィスへの出勤状況を追跡するようになった。ほかにもRTOのポリシーを守らなかったために解雇されたという話が後を絶たない。どちらの側も主導権を握っているわけではないので、議論が二極化するほど、双方にとって有益な解決に達することは難しくなる。
産業革命以来、最も大きな働き方に関する変化に対し、リーダーは従業員と積極的に協力して、バランスの取れたアプローチを見つけなければならない。
ここではまず、リーダーと従業員がリモートワークについて合意することが難しい理由を説明し、その知識をもとに、リーダーが従業員と率直でオープンな話し合いを進めるためのいくつかのステップを紹介する。双方のニーズと懸念を理解して正当性を認め合うような議論をしていこう。
雇用主と従業員のずれ
20年以上にわたってリモートワークについて研究し、コンサルティングを行ってきた筆者は、リーダーと従業員の双方から多くの見解を聞いてきた。進むべき道について合意を形成することが難しい主な理由は、はっきりしている。古典的な5つのW(誰が、何を、どこで、いつ、なぜ)について合意がないまま、費用対効果のトレードオフを評価しようとするからだ。
5つのWは、問題のあらゆる側面を考慮していることを確認するための認知ツールである。より総合的な視点を整理したうえで、リーダーが率先して、その視点を基盤に従業員との対話を進めることが重要だ。そうした対話は、バランスの取れたもの(双方のニーズを理解する)、敬意に満ちたもの(それらのニーズの正当性を認める)、そして継続的なもの(ニーズの変化に合わせ、時間をかけて調整する)でなければならない。
何よりも、双方が相手に勝つことではなく、相互に最適な解決策を見出すことを目指して対話に臨む必要がある。そこで、5つのWに関する考え方を説明しよう。
Why(なぜ) あらゆる議論の出発点は、なぜフレキシブルワークについて議論するのか(あるいは、議論しないのか)、その理由をすり合わせることだ。生産性の向上や維持のために、または人材の獲得や維持のために議論したい人もいれば、人間関係や社会的基盤に関心がある人もいるだろう。最初に議論するのは、議論の動機についてだ。
What(何を) 続いて、それらの動機をどのように定義するかを明確にする。パフォーマンスはリモートワークの利点としてもコストとしても強調されるが、そのようなことが起きる理由は、パフォーマンスの定義について、そもそも意見が一致することがほとんどないからだ。たとえば、生産性とは生成されたコードの行数なのか。修正の量が多いか少ないかという意味での品質なのか。それとも費やした労力当たりのアウトプットで算出できる効率性だろうか。
これについてわかりやすい例は、通勤時間をめぐる議論だ。通勤を無駄な時間と考えるなら、その短縮は明らかなメリットである。一方で、職場と家庭の緩衝材や、旧友と再会するための強制的な仕組みとして見る場合、通勤時間の削減はコストになる。
Where(どこで) どの組織も均一ではなく、さまざまな仕事を達成するための道筋がある。カスタマーサービスの電話対応はどこでもできるが、製品の梱包は製品がある場所に制約される。どのような仕事が行われているかを考慮することで、リモートワークのポリシーをめぐる議論の境界線が定まる。
When(いつ) 組織のリーダーと従業員にとって、時間を超えて効率的に考えることは難しいものだ。従業員は、短期的には勤務時間に関する政策の恩恵を受けるが、長期的にはそのコストを実感する。たとえば、フレキシブルに働ける日を増やすと、通勤時間がなくなるという短期的な利益があるかもしれないが、周囲とのスケジュールが合わなくてメンターシップが弱くなるなど、長期的には不利益が生じるかもしれない。
Who(誰が) この項目を最後に説明するのは、筆者の経験上、これが意見の相違が生まれる根底にある問題だからだ。ワークポリシーは、関係する人全員に同じ影響を与えるわけではない。たとえば、影響を個人のレベルで考えるのか、あるいは集団のレベルで考えるのか。従業員が在宅勤務を自由に選べるようにするポリシーは、個人のワークライフのスケジュール調整には有益だが、集団が共有する組織文化の感覚を犠牲にするかもしれない。
リーダーは、誰の利益や成果を優先するかを考えなければならない(これは、リスクが高い時代における心理的安全性に関する筆者の最近の研究でも、重要な問題だった)。5つのWが明確になれば、そのように考えやすくなる。
5つのWは、実りある話し合いのために、すべての情報を確実にテーブルに並べるためのツールであって、完全に独立した要素ではない。たとえば、どの業務がフレキシブルワークに向いているかを決めることは、場所に関する議論(何を重要な成果として定義するかにも左右される)である一方で、誰がその恩恵を受けるかということに大きな影響を及ぼし、従業員の公平感や公正さにも影響する。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









