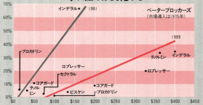-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
テクノロジーの急速な進展で「近接性」戦略が重要に
今日、事業戦略責任者のグループと話をすると、自社の意思決定がマヒ状態に陥っていると言う人が少なからずいるだろう。AI、IoT(モノのインターネット)、デジタル化、3Dプリンティングなど、急速に展開しているトレンドがもたらすと予想される影響に圧倒されているのだ。
筆者らは、急成長中でしばしば重なり合うこうしたトレンドを理解するうえで、エグゼクティブに役立つ戦略的概念を明らかにした。それは「近接性」である。中核となる前提は、デジタルテクノロジーの進展によって、価値の創出と需要の生じる瞬間がますます接近しているということだ。時間的に近いだけではなく、物理的にも近くなっている。近接性を理解することによって、あらゆる部門の戦略担当やリーダーシップチームが新しいツールやテクノロジー、トレンドの相互の関連性を理解し、それらがもたらす可能性のあるインパクトを見極め、どうすれば自社の繁栄のために管理し活用できるかを思い描くことができるだろう。
本稿では、近接性の意味を追求し、現在の活用例を共有して、リーダーシップチームが自社の近接性戦略を構築するのに役立つ4つのステップを提示したい。
戦略責任者を立ち往生させるトレンド
筆者らの研究と、さまざまな業界の戦略責任者100人との対話から明らかなのは、組織の遠い将来まで見通すべきエグゼクティブが、トレンドを追うことに忙殺されているということだ。誇大な宣伝と現実を切り分け、各トレンドの影響を見抜き、最新ツールやテクノロジー、プラットフォームのうち、いったいどれが自社に真の価値をもたらすのかを理解することに苦戦しているのである。
過去10年間だけで、どれほどテクノロジーが進展したかを考えてほしい。トラクターから冷蔵庫に至るまで、あらゆるものがコネクテッドデバイスとして家庭や農場、職場へとどんどん進出し、顧客とのやり取りの性質を変化させている。人間が介在しない完全自動化工場から人間と機械のコミュニケーションまで、生成AIによって自動化が幅広く進み、製造業でも医療業界でもこれまでの慣行の再考を余儀なくされている。空間コンピューティング(バーチャルリアリティやメタバースなど)は試練の時期を経て、広く受け入れられるようになり、近い将来に現実世界でも活用されることが有望視されている。3Dプリンティングは製造業での採用がますます増えて成果を上げつつあり、アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の進歩は、顧客データへのアクセスと共有を容易にしている。
より広い文脈で考えることも重要である。地政学的な不確実性は、世界各地でリスクと予測不可能性をもたらしている。顧客はスピードとパーソナライゼーションの向上を求めるようになった。その一方で、気候変動に関する(投資家や利害団体からの)プレッシャーとコスト(規制、保険、インフラ、人材)が増していることで、困難な状況が生まれている。
近接性の概念は何を明確にするのか
急速に発展する重大なトレンドがこれだけ多くあれば、戦略責任者もビジネスリーダーも圧倒されてしまうだろう。モザイク画の前に立っていると想像してみるとよい。個々のピースや込み入った模様につい目を奪われ、各要素がどのようにつながって一体性のある全体を構成しているのかにはなかなか思いが至らない。
ここは、元米国空軍戦闘機パイロットでストラテジストのジョン・ボイド大佐のアドバイスに耳を傾けるとよいだろう。ボイドの理論によると、環境を正しく読み取りたいならば、常に状況を観察し、要素を分解し(分析)、新たな組み合わせで再構成して(合成)、現状を理解する必要がある。端的に言うと、状況の構成要素を新しい絵として合成できなければ、新しい現実への適応が遅れ、戦略的に不利になるリスクがあるのだ。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)