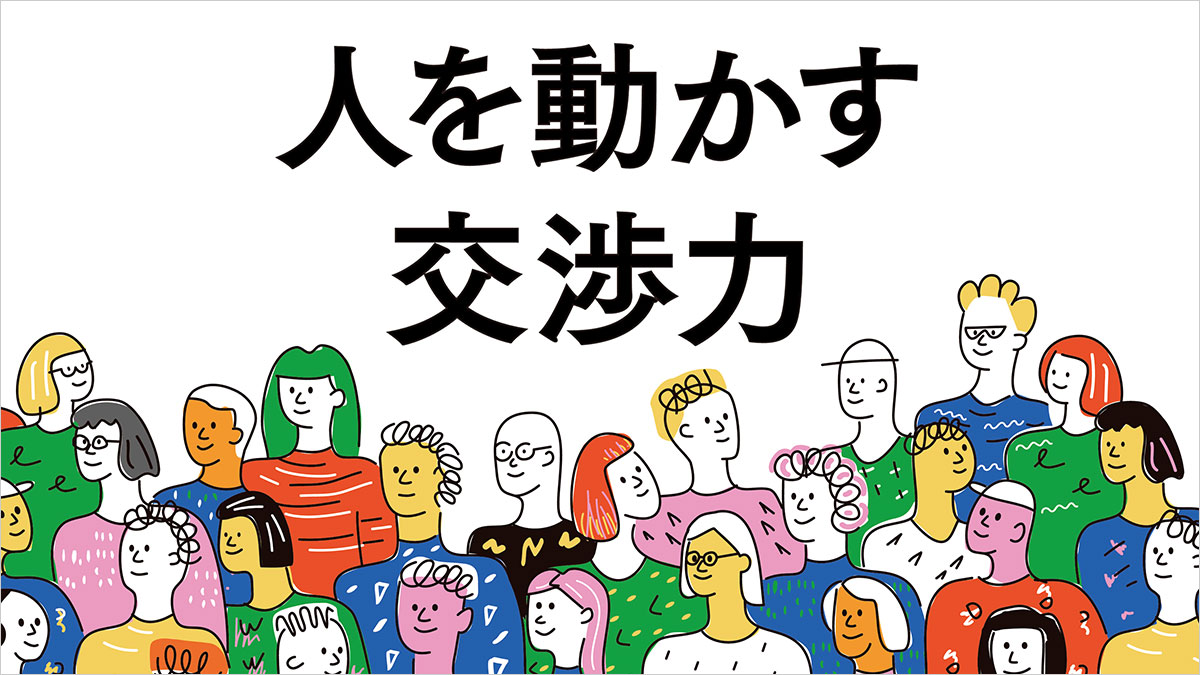
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
価値創造につながる交渉のあり方とは
「交渉」と聞いて、どのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。主導権をめぐる駆け引き、利益を最大化する条件の提示、相手を出し抜く知恵比べ……。そんな連想を働かせる方も多いかもしれません。
たしかに交渉には、そういった一面もあるでしょう。しかし変化が激しいいまの時代には、事を成すに当たってみずからだけで完結することは少なく、むしろ異なる強みを持った他者と手を結び、信頼関係を築きながらより高次の価値を生み出していく姿勢が求められます。今号の特集「人を動かす交渉力」では、相手も納得して動きたくなる、そんな交渉のあり方を探ります。
特集1本目「交渉は相手を深く知ることから始まる」では、困難なディールを成功に導いてきたサントリーホールディングスの新浪剛史氏に、交渉に臨む際に心がけてきた点を伺いました。
特集2本目は、交渉に関する世界的権威であるマックス H. ベイザーマンによる論考「交渉を価値創造のプロセスに転換する」です。この論考の中でベイザーマンは、交渉とは決まった大きさのパイを奪い合うものだと誤解されているが、本来はそうではなく、パイのサイズを大きくする方法を考えることこそが交渉の要諦であると喝破しています。
近年ではますます、異文化間で交渉に臨むケースが増えてきています。特集3本目「異文化間の交渉で生じがちな誤解を防ぐ4つのルール」は、交渉相手の文化的な違いに過度に引きずられることなく、個々の人物に注目することの重要性を説いています。
特集4本目としてご紹介するのは、「組織内の『対立』をマネジメントする方法」。初出は1960年というクラシックながら、組織内でもしばしば起こるコンフリクトにどう対処し、円滑に仕事を進められる体制をつくるのかを考えるうえでいまもなお示唆に富む内容です。
交渉に関わるすべてのプレーヤーが、「ウィン・ルーズ」の関係ではなく「ウィン・ウィン」の関係を築いて価値を享受できる合意形成に至るために、本特集をぜひお役立てください。
さて、今号から新連載「視点のデザイン 思考の殻を破る」を隔月でお届けします。人は誰しも、知らずしらずのうちに固定観念を抱いているものです。過去の成功体験や長年の経験に引きずられ、新しい発想や物の見方が妨げられてしまうことも少なくないでしょう。そこで、自分とは異なるレンズで世界を見ている人の視点を借りることで、新たな気づきが得られるのではないか。そんな仮説から生まれたのがこの連載です。
連載第1回にご登場いただいたのは、現代美術家の塩田千春さん。息を飲むような彼女の作品に込められた意図を知れば、空間を満たすその赤い糸の先が、まるで自分に伸びてくるかのような気配を覚えます。見開き2ページの小品ではありますが、次回以降も多様な異才の視点をご紹介する予定です。
最後に予告を一つ。DHBRは次号から、新しいブランドロゴに切り替わります。新ロゴは、『ハーバード・ビジネス・レビュー』(HBR)の伝統的な盾のモチーフを活かしながらも、時代とともに進化するブランドを表現しています。こちらもどうぞお楽しみに。
(編集長 常盤亜由子)






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









