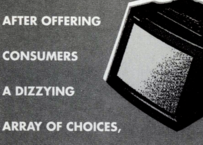-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
近視眼的ではない、戦略的な引き算とは
いま世界中の企業は、地政学的環境の不安定化とAIの台頭により、経済とビジネスを取り巻く不確実性が増大している時代に身を置いている。そのような厳しい状況の下では、ビジネスリーダーは、コストの削減、オペレーションの簡素化、無駄の削減など、いわば戦術レベルの「引き算」を実践しようという誘惑に屈しがちだ。
たしかに、現在のようにリソースが十分とはいえない状況に対処するうえで、引き算の行動は、時に強力な手立てになりうる。しかし、レジリエンスや認知度の向上など、他の目標を犠牲にして、効率の改善だけを目指すのであれば、近視眼的な姿勢と言わざるをえない。その点、戦略的に引き算を行えば、戦術レベルの引き算で片端からコストを削減するのとは異なり、イノベーションの推進を通じて、企業が混乱を乗り切り、さらには再浮上するための道を開ける。
本稿ではまず、企業が引き算の行動を取ろうと考えた場合に、その行動の有効性をチェックするための「3つのテスト」を紹介する。狙いは、その引き算の行動の結果として、企業が目指すべき3つの重要な目標──効率性、レジリエンス、存在感──にどのような影響が及ぶかを確認することだ。記事の後半では、この3つの目標のバランスを取りつつ、すべての目標を満たすための引き算型の変革の方法を6種類論じたい。
引き算の有効性をチェックするための「3つのテスト」
引き算を成功させるためには、効率性だけでなく、企業のパフォーマンスに関して重要なその他の複数の要素も考慮に入れて、総合的なアプローチを採用する必要がある。まず、次の問いから始めよう──「引き算により、効率性を改善し、レジリエンスを強化し、存在感を向上させることを通じて、激動の時代にイノベーションを成し遂げるには、どうすればよいのか」。2025年の複雑な環境においてイノベーションを成功させたければ、引き算を実践するに当たり、3つの互いに関連のあるビジネス上の目標を追求しなくてはならない。
・効率性:投入するリソース、時間、労力を最小化する。
・レジリエンス:大激変に対処して、中核的な機能を維持する。
・存在感:認知度を高めて、ステークホルダーにとっての魅力を高める。
効率性だけを追求して合理化を徹底的に推進すれば、システムが脆弱になり、不透明性も増しかねない。そうなれば、価値が生み出されるどころか、長い目で見れば価値が損なわれてしまう。
これは、究極のコスト削減策として「ジャスト・イン・タイム」の在庫管理法を推し進めた企業の多くが経験したことだ。そのような企業においては、コロナ禍の時期に脆弱なネットワークが破綻した結果、厳しい在庫管理によって成し遂げたささやかなコスト削減の成果は、工場の閉鎖や店頭での商品不足、顧客の不満によってたちまち消し飛んでしまった。この出来事は、レジリエンスの下支えを欠いた効率性がオペレーションのマヒと売上げの喪失をもたらすことを浮き彫りにしたといえる。
もっと痛烈な実例としては、航空宇宙大手ボーイングの経験を挙げることができる。同社は、ジェット旅客機「ボーイング737マックス」の開発で長年にわたり徹底したコスト削減を続けたことにより、設計のための時間とテストの予算を減らすことができた。しかし、市場投入後に相次いだ墜落事故により、200億ドルを超す直接的な出費が発生し、さらには、それまで何十年もかけて築いてきたブランドとしての強みが壊滅的なダメージを受けた。この一件からはっきり見えてくるように、信頼、評判、ステークホルダーの安心感をないがしろにすれば、短期的にはコストを削減できたとしても、長い目で見れば会社の存続が脅かされかねない。
つまり、効率性、レジリエンス、存在感という3つのテストのすべてに合格できないにもかかわらず、引き算を実践すれば、目先はリーンな体制を築いて成果を上げられても、将来的な破滅をもたらす重荷を背負う可能性があるのだ。
6種類の引き算型の変革
では、ビジネスリーダーはどうすれば、引き算により、効率性の改善だけでなく、イノベーションを成し遂げられるのか。筆者らは、これまで100以上の企業や組織が激変の時代にイノベーションの機会を見出すための支援をしてきた。その経験からいうと、効率性とレジリエンスと存在感という3要素のバランスを取りつつ、引き算思考を実践するための方法が6種類ある。これらの方法論は、プロセス、システム、プロダクト、サービスのいずれにも適用できる。
削除する:要素や手順、選択肢を完全に取り除く
重要な機能を果たさなくなった要素をすべて取り除いたり、一部を選別して取り除いたりする。ある要素を丸ごと廃止してもよいし、特定の手順や、価値の小さい選択肢、不要なルール、重複している業務引き継ぎをなくしてもよい。
たとえば、家具大手のIKEAは2021年、世界中でよく知られていた紙の商品カタログをついに廃止した。これに伴い、同社は、莫大なコストを生む印刷プロセスを全廃できた。その結果として削減できた紙の使用量は、年間3万3000トンに上ると推定されている。
この措置により、生産と流通に関する支出が減り、効率性が改善した(=効率性)。また、すべての商品のストーリーをデジタルプラットフォームで即座にアップデートできるようになり、レジリエンスも強化された(=レジリエンス)。加えて、紙の使用量を減らすことを通じて、サステナビリティを徹底して重んじる姿勢──それは若い世代の消費者に共感されるものだ──を発信し、ブランドの存在感を向上させることもできた(=存在感)。
代替する:複雑な要素をシンプルなものと交換する
複雑な要素やプロセス、システムをよりシンプルなものに取り換える。同じ役割をよりエレガントに果たせるものと交換するのだ。ルワンダの国民健康サービスはそれを実践した。2016年、不便な土地への輸血用血液の輸送に伴う問題を解決するために、山道を運搬するという信頼性の乏しい方法に代えて、米国のドローン関連スタートアップ企業ジップラインのバッテリー駆動型ドローンを導入したのである。
2022年に『ランセット・グローバル・ヘルス』誌に掲載された研究によると、その結果として、ルワンダでは使用期限切れになる輸血用血液の量を67%減らすことができた。すべて電力で動く軽量のドローンに輸送手段を切り替えたことで、人間の労力と燃料の使用量が減り(=効率性)、冠水した危険な道を通る必要がなくなり(=レジリエンス)、ヘルスケア分野のイノベーションに関してルワンダの国際的名声が高まった(=存在感)。
統合する:複数の機能を一つのソリューションに束ねる
この方法論には、プロセスを圧縮するアプローチと、複数の機能や部品やタッチポイント(顧客との接触点)を統一的なシステムに束ねて、構成要素を減らしつつ、以前と同じ価値を生み出すアプローチの両方が含まれる。
たとえば、エストニアの「eレジデンシー」(電子居住権)制度は、複数の行政上の機能を単一のデジタルIDに統合したものである。エストニアでこのシステムが導入されたことにより、起業家は世界のどこにいても、一つのIDカードでシステムにログインするだけで、全面的にオンライン上で、EUに拠点を置く企業を設立して経営することが可能になった。
この「eレジデンシー」制度の下では、申請のペーパーレス化により行政機関の負担が減り(=効率性)、暗号技術で保護されたシステムにより行政サービスの継続性が実現し(=レジリエンス)、しかもエストニアはデジタル行政に関して国の規模をはるかに上回る知名度を得られた(=存在感)。
見えなくする:アクセスしやすさを維持しつつ、複雑性を表面から隠す
日々の業務フロー、プロセス、プロダクトが持っている複雑性の一部を隠すことにより、機能面を犠牲にすることなく、人々の認知的負荷を軽減できる。主要なインターフェース上で、必須ではない複雑性を見えなくする一方、必要になった場合にはそれらの要素にもアクセスできるようにしておけばよい。たとえば、企業の新規採用者向けの社内ポータルサイトでは、次に取るべきステップだけを示すようにしつつ、クリック一つですべての説明書類にアクセスできるようにしておく、といった具合だ。
AIを活用した音声文字起こしサービス「Otter.ai」も、この手法を実践した例といえるだろう。このツールのハイライト機能を用いた場合、ユーザーが求めない限り、書き起こしの全文が表示されることはない。簡潔なサマリーが自動生成により表示されて、逐語的な書き起こしの全文は1回のクリックで表示可能な場所に隠されている。
このツールを導入したチームは、長い文書をコンピュータ画面で延々とスクロールする時間が減り(=効率性)、しかも後で詳しく調べられるように記録を残すことができる(=レジリエンス)。そのうえ、Otterはユーザー中心主義の生産性重視の企業という評判を確立できた(=存在感)。
一時停止する:システムの一部の構成要素を暫定的に停止する
戦略的な判断により、一部の機能、プロセス、サービスを一時停止する。その要素を完全になくしてしまうのではなく、後で状況が変わった場合には再び有効にできるようにしておくのだ。
たとえば、動画配信大手のネットフリックスは、ワンクリックにより、メンバーシップを「一時停止」できるようにしている。これにより、会員は退会するのではなく、最大3カ月間、料金の請求を停止することが可能になった。こうした利用中断の制度を導入した結果、顧客の退会率が下がってコスト削減が実現しただけでなく(=効率性)、顧客データを手放すことなく、利用再開時にシームレスに活用することが可能になった(=レジリエンス)。しかも、同社は顧客の身になって物を考える姿勢を打ち出すことにより、ライバルと差別化することができた(=存在感)。
抽象化する:ユーザーが複雑性に触れずに済むようなインターフェースを設ける
シンプルなインターフェースをつくることにより、ユーザーが背後の複雑な処理について理解していなくても、ユーザーのインプットがバックエンドの複雑なオペレーションに変換されるようにする。
アマゾン・ドットコムの「アマゾン ウェブ サービス」(AWS)は、複雑なインフラマネジメントを抽象化し、デベロッパーがサーバーと物理的に関わることなく開発に専念できるようにし(=効率性)、イノベーションを加速させている(=レジリエンス)。そのうえ、インターフェースをシンプルにしたことにより、ユーザーはバックエンドの途方もなく複雑な操作に触れる必要がなく、そのおかげでAWSは、企業が拡張性の高いシステムを構築しようとする際に真っ先に選ばれるソリューションの地位を確立した(=存在感)。
引き算をデフォルトの戦略にするためには
引き算を組織の中核的な能力にしたいリーダーは、いくつかの実践的な戦略を採用すればよい。ただし、そうした試みを他の取り組みから切り離して実践するのではなく、「より少ない行動でより大きな成果を上げる」ことを目指す動きの一貫と位置づけるべきだ。
引き算を中核的なプロセスに織り込む
引き算を1回だけの意思決定と位置づけるのではなく、チームが計画を立てて優先事項を決めるプロセスに織り込むべきだ。リーダーは、旧来の目標設定のエクササイズに加えて、「やめるべきこと」を検討するエクササイズもチームに導入すればよい。そのような検討の場では、業務フローやツール、要求事項を検討し、もはや価値を生み出さなくなっているものをあぶり出していくのだ。
6種類の方法論の中で「削除」は、アウトカムにほとんど寄与しないよけいなステップを取り除ける。「統合」は、不要な引き継ぎや承認のプロセスをなくすことができる。「見えなくする」アプローチは、大きな価値を生まないプロダクトやサービスをなくすことにより、顧客の混乱を減らしたり、戦略上の集中がぼやけることを防いだりする効果が期待できる。以上の3種類の方法論を年間計画もしくは四半期計画の立案に織り込むことにより、複雑性を高めることなく、効率性を改善し、戦略の一貫性を維持できる。
引き算することをデザイン上の課題と位置づける
引き算することをデザイン上の課題と位置づけることにより、問題解決のプロセスを足し算的な発想から脱却させ、本質的な価値を重視するものに転換させることができる。チームに対して、新しい要素をつけ加えることによりプロセスを改善する方法を問うのではなく、より少ない手順や機能、より少ない制約の下で同じ結果を達成するにはどうすればよいかを問うのだ。
この点では、「統合」を実践すれば、クオリティを下げることなしに、手順を減らし、業務フローを圧縮できる。「代替」の方法論は、より規模が小さく、よりエレガントなソリューションに道を開ける。そのようなソリューションには、活用しやすく、維持しやすいという利点がある。「抽象化」は、インターフェースをよりシンプルなものに変更できる。
以上の3つのアプローチはいずれも、オペレーションの足を引っ張る要素を減らして、効率性を改善するはたらきがある。また、レジリエンスを強化する効果も期待できる。シンプルなシステムのほうが破綻しづらく、問題が発生した場合にも対処しやすいからだ。そして、デザイン上の課題と位置づけることにより、創造性に枠をはめるのではなく、創造性が発揮されるきっかけとなる制約をつくり出せる。
引き算に成功した場合に祝福する
引き算の行動は見落とされることが多く、恩恵が無視されやすい。リーダーは引き算の成果に目が向くようにするために、チームのメンバーに対して、何をやめたかを記録するだけでなく、引き算を行なったことを成果として祝福するよう促すべきだ。こうしたシンプルな行動を取り入れることにより、引き算が価値の源泉として認識されるようになり、称賛の対象になる。
「削除」や「一時停止」などのテクニックを実践することにより、このような引き算を計画的に達成できるようになる。重複している課題を削除すれば、無駄になる時間を減らして効率性を改善できる。その点で、この引き算は、有意義な貢献として評価に値する。また、インパクトの小さいプロジェクトを一時停止すれば、未来の選択肢を残しつつ、目の前の活動に集中することが可能になる。これも、称賛すべき戦略的決定といえる。引き算の行動を評価することは、戦略的な意図を持って引き算を行うことを、怠慢ではなく、進歩と見なす考え方を強化できる。
生成AIを活用して、引き算型の変革を後押しする
生成AIツールは、引き算の機会を見出す手立てになりうる。AIは、人間が見落としかねない機会を指摘してくれるからだ。
たとえば、筆者らは一つの実例として、「ジェミニ2.5」と「クロード4」という2種類の生成AIツールに指示して、インドの大手病院経営企業向けに、本稿で論じた6つのアプローチを用いて引き算のアイデアを提案するよう求めてみた。
具体的には、次のように指示した。「[XYZ社のために]引き算によりイノベーションを実現するためのアイデアを提案してください。そのアイデアは行動につながるものでなくてはならず、手順を減らすか、コストを引き下げるか、複雑性を和らげるかして、それまでと同等、もしくはそれ以上の価値を生み出す一方で、レジリエンスを維持もしくは向上させ、さらには存在感と認知度を維持もしくは向上させるものである必要があります。[6つのアプローチのそれぞれについて]少なくとも一つの具体的なアイデアを挙げてください」。
以下にAIの応答を紹介する(ただし、文章の明晰性を確保するために若干の編集を加えている)。
・削除する:症状が安定している慢性期の患者に関しては、対面での再診を廃止する。遠隔診療を導入することで、患者の利便性を向上させ(=効率性)、診療の継続性を確保し(=レジリエンス)、[XYZ社を]テクノロジー重視の病院経営企業として位置づけることができる(=存在感)。
・統合する:患者との接触点(診察、診断・検査結果の説明、支払い、事前問診)を一つのモバイルアプリに一本化することにより、患者と病院の関わりを合理化し(=効率性)、コミュニケーションを一元化でき(=レジリエンス)、サービスへのアクセスを容易にできる(=存在感)。
・代替する:旧来の紙ベースのカルテを、音声入力によるデジタル形式のものに切り替える。これにより、データ入力のエラーを減らし(=効率性)、記録の正確性を向上させ(=レジリエンス)、病院としてイノベーションの先頭を走る存在としてアピールすることが可能になる(=存在感)。
・見えなくする:賢明なトリアージのシステムを導入することにより、患者が適切な水準のケアを受けられるようにしつつ、患者が複雑性に触れずに済むようにする。その結果として、患者の待ち時間を減らし(=効率性)、診療の質を維持し(=レジリエンス)、患者の満足度を高めることができる(=存在感)。
・一時停止する:柔軟性のある予約システムを採用し、患者がペナルティを受けることなく、予約を変更できるようにする。それにより、診察の無断キャンセルを減らし(=効率性)、患者と医師の関係を維持し(=レジリエンス)、患者中心の診療をおこなっていることを実証できる(=存在感)。
・抽象化する:すべてのやり取りを一つのインターフェースで完了できるようにし、患者が複雑性に触れずに済むようにする。それにより、アクセスをシンプルにし(=効率性)、サービス全体を通した継続性を確保し(=レジリエンス)、[XYZ社を]デジタルの面で先進的な病院経営企業と位置づけることができる(=存在感)。
企業はAIモデルに指示して、さまざまな種類の引き算の選択肢を検討させることにより、要素を増やそうとしがちな人間の習性を克服し、よりエレガントなソリューションを見出すことができる。効率性だけでなく、複数のパフォーマンス上の目標のバランスを取ることが可能になるのだ。
* * *
あらゆる競争相手が機能やチャネル、データ、支出を増やそうと躍起になっている時代に、真の差別化要因になるのは、取り除く勇気だ。引き算は、倹約主義でもなければ、ミニマリズムでもない。それは戦略上の選択だ。
ビジネスリーダーは、必須とは言えない要素を取り除いて、画期的な成果が生まれる空白地帯をつくることにより、景気が回復し始めた時に、自社がその上昇気流の先頭に立てるようにできるのである。
"In Turbulent Times, Consider 'Strategic Subtraction'," HBR.org, June 17, 2025.









![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)