同社執行役員でホテル事業の責任者である岡田光氏は、東京・目黒の「CLASKA」の支配人、大阪の「堂島ホテル」のプロデュ-サーとして、ACE HOTELの影響を受けたロビー・ソーシャライジングを積極的に試みてきました。なかでもCLASKAは「ロビーを遊び場にする」というコンセプトを開業時に掲げ、クラブイベントや音楽ライブ、ファッションショーなどを開催してきました。つまり大人の夜の社交場として、ホテルを開放したのです。

20TRANSIT GENERAL OFFICEが手がけた東京・目黒の「CLASKA」。ロビーにパーティスペースとしての機能をもたせた画期的なホテルとして2003年9月に開業した。
そんな岡田氏は日本流のロビー・ソーシャライジングの可能性について、どのように考えているのでしょうか?
「歴史を紐解くと、もともと日本の高級ホテルはエクスクルーシブなものではなく、地域の社交場として存在していました。特に平屋文化だった東京がそうですが、海外と違ってたくさんの個室やパーティールームがあるわけではないので、自宅に大勢を呼んでもてなすことが難しい。だからホテルに迎賓館のような機能を持たせて、そこで親族や友人たちとの交流を行っていた。まさに帝国ホテルやホテルオークラがそうで、ただの宿泊所ではなく、地域の人々が交わるソーシャライジングされた場所でした」
それが外資系ホテルの参入により、豪華でエクスクルーシブな空間演出こそが高級ホテルという価値観に文脈が変わってしまいました。

岡田光氏:トランジットジェネラルオフィス執行役員。ヒルトン、ハイアット、ペニンシュラなどの外資系ホテル勤務を経て、2003年にトランジットジェネラルオフィスに入社。「CLASKA」や「堂島ホテル」などのホテル事業のほか、愛媛県宇和島の旅館「木屋旅館」も手がける。
しかし、こうした外資系のホテルブランドが必ずしも日本を訪れる外国人のニーズと合致しているわけではありません。岡田氏はアメリカのホテル情報サイト「Tablet Hotels」の代表に指摘されたことが印象的だったといいます。
「日本は食やファッションにおいては非常に素晴らしい国だけど、アジアのほかの国に比べてナイトライフが充実していないと言われたんです。これはクラブのような遊び場だけではなく、ホテルにおいても同じ。外資系チェーンの高級ホテルはたくさんあるけど、それなら海外にだってある。日本に来てまで泊まりたくなるような個性的なホテルブランドがないという指摘でした。CLASKAはその受け皿として歓迎されましたが、客室は20しかない。これからどんどん外国の観光客が増えていくなかで、もっと大規模でオリジナリティ溢れる高級ホテルが必要とされているのです」
そんな日本ならではの高級ホテルのあり様について考えるとき、帝国ホテルやホテルオークラが行っていた地域の人が足を運ぶようなホテルづくりがヒントになります。




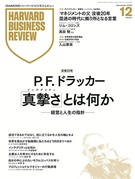
![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









