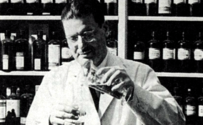1.構成を決める
即興で話すことへのプレッシャーは、不確実性から生じている。何を言うべきか、何を言わないほうがよいのか――。ビジネスの場で聞き手にストレスを与える最悪のスピーチは、目的が曖昧なままダラダラと続く話だ。弁論術ではこの問題に対処するため、メモ用紙にさっと構成を書いて話の要点を明らかにしていた。導入部分、主張の根拠となるものを2~3点、そして結論というパターンが多かった。こうした骨組みをメモしておけば、さまざまなストーリーや事例、データなどで細部を埋めることが容易になる。夕食会や役員会で突然のコメントを求められた時、私は紙ナプキンやノート、パワーポイント資料の裏などに、話の要点とその主な根拠をいくつか走り書きする。次に、主張を示すために必要な事例やデータを、20語以内で付け加える。これだけで曖昧さが消え、とりとめのない話をすることもなくなる。
2.要点(パンチライン)を最初に言う
私がコンサルタントをしていた頃、コミュニケーションで鉄則とされていたルールの1つは、「要点を先に」ということだった。どんなプレゼンでも必ず、最初に論旨を明らかにしておく。そうすれば聞き手は、後に続く話の内容を理解しやすくなる。ビジネスパーソンのプレゼンが要点を欠いたまま続き、聴衆は最後に結論を聞くまで要点がわからない、という場面を私は数えきれないほど見てきた。ビジネスの場でうまくスピーチをするのは、うまいジョークを言うのとは違う。オチを最後まで取っておいてはいけないのだ。
3.聞き手の存在を意識する
ほんの数行の言葉で、聞き手に敬意を表し、スピーチを新鮮に感じさせることができる。導入の部分で、いま話している場所や土地のことに触れるとよい。相手方の組織を、自分が話すストーリーの一部と関連づけるのもよい。だれかの名前を具体的に挙げて、自分の話に関連づけるという方法もある。いずれも些細な工夫だが、その場や聴衆にふさわしいスピーチへとカスタマイズするのに役立つ。
4.話し方ではなく、話す内容を覚える
話し方を細部までしっかり練習したのに、本番で頭が真っ白になり話の内容が飛んでしまった、という経験はだれでも一度ならずあるだろう。弁論術を用いたスピーチでは、引用文を5~10ほど、人名や地名を3~4つ、根拠となるデータを3~4つほど盛り込むのが一般的だった。これを30分以内に準備するのだから、調べて覚えるだけでも大変だ。そこで、重要なストーリーとデータを記憶することだけにエネルギーを注ぎ、話し方については練習しない。一字一句を完璧に話す練習に時間を費やすと、本番で言い間違えてしまった時に、話を生き生きと伝えるのに必要なディテールを忘れてしまう。さらによくないのは、聞き手に重要な点だけを強調しながらよどみなく進めるのではなく、パワーポイントや書類をそのまま読み上げることだ。内容を把握していれば、言葉は自然に出てくるものである。
5.短くする
思想家で数学者のブレーズ・パスカルによる、有名な言葉がある――「長い手紙になってしまいました。短くする時間がなかったものですから」。限られた準備で話すことの難しさは、「話すことを十分に思いつけるか」だと考えられがちだ。しかし実際にはその逆の場合が多い。私たちは言うべきことを用意していない時、必要な時間を短く見積もってしまう。ストーリーや論点をたくさん詰め込みすぎて、時間が足りなくなるうえにメッセージが散漫になってしまうのだ。簡潔な話をだれよりも強く求めているのは、聞き手だ。だから、言うべきことに迷った時は言葉を少なめにしよう。
即興のスピーチに強くなるためには、練習に勝る方法はない。話を効果的にしようと思えば、考慮すべきことはたくさんある。しかし上記のような基本的なポイントをいくつかマスターするだけで、準備の際のストレスを減らし、聞きやすいスピーチにできるのだ。
HBR.ORG原文:5 Tips for Off-the-Cuff Speaking August 29, 2014
■こちらの記事もおすすめします
米国の名門大学の卒業講演に学ぶ、ビジネスの知恵
心を揺さぶり、信頼を感じさせる、ストーリーの語り方

ジョン・コールマン(John Coleman)
著述家。Passion & Purpose: Stories from the Best and Brightest Young Business Leadersの共著者。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)