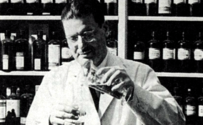②インセンティブが重要
協働は人々を引き合わせるだけでは起こらない。誘発する何かが必要だ。そこで、関与と協働の度合いを成績に連動させたところ、生徒たちはこれに応えた。講座のいずれかの時点で、全参加者の半数以上が他者に質問を投げかけ、約75%が他者の質問に答えを返した。一方、他の多くのオンライン講座における掲示板では、参加者の1割が9割の貢献を担い、残りの人々はほとんど関与しないというのが典型例だ(これはハーバード教育大学院のアンドリュー・ホー教授のデータによる)。
協働のインセンティブは、大掛かりである必要はない。我々の場合は「関与の最低基準」を義務づけることで、協働が自然に勢いを増していった。
有意義な協働は、質問と答えの両方が交わされることで生まれる。我々はどちらも同じように評価した。さらに、質問の種類を考慮することも奨励した。初歩的、難解、抽象的、等々に分けることで、学習テーマに関するさまざまな質問を効果的に発することができるようになる。
③参加者の能力、決意、継続性が協働のカギとなる
効果的な協働を実現するためには、参加者がこれら3つを有していなければならない。職場でチームを編成する時は通常、無作為に人を寄せ集めるということはしない。選ばれるメンバーには理由があり、オンラインでもそうあってしかるべきである。
受講希望者の能力と決意を判断するために、最初に開講したHBX COReは出願による承認制とした。(注:HBXには現在、CORe、Courses、Liveの3コースがある。COReはMBAへの準備的な位置づけで、本記事が報告しているのはこのコースについて。Coursesは現在はクレイトン・クリステンセンの「破壊的戦略論」講座のみで、今後はマイケル・ポーター等の講座が開講予定。Liveは現在は招待制のみ。)COReは「ビジネス・アナリティクス」、「マネジャーのための経済学」、「財務会計」の3科目で構成されている。出願には過去の学業成績に加え、小論文の提出も求められる。受講料もまた、受講者の決意を問う大きな要素となる。全10週間、各週10~15時間のコースで1500ドルだ。
また、継続的な協働を促進するために2つの原則が必須となった。まず、学習体験、プラットフォーム、カリキュラムを魅力的なものにすること。そして、COReで“大まかな同期”を義務づけることだ。具体的には、教材を公開する際に個々の単元(細分化された学習テーマ)ごとに締め切り日を設定することで、生徒たちにある程度同じ期間内に授業に参加してもらう。科目を修了する日は一定の期限内から柔軟に選べるが、各単元の締め切り日は全員が守る必要がある。これによって参加者は、他のメンバーより2~3日以上先行または遅延することなく進捗を合わせることになる。
他のオンライン講座では、受講の柔軟性を増やす傾向がますます顕著となっている。柔軟性は良いことだが、学習体験の共有は生徒間の対話と協働を喚起できるのだ。
受講者の選抜、学習意欲の重視、そして上述のような仕組みは、生徒たちの毎週の定着率に寄与し、結果として継続的な協働にもつながった。もし多くの参加者が意欲を示さなかったり受講に値する能力に欠けていたりすれば、生徒間の対話と学び合いにマイナスとなる。HBX COReの参加者たちは、生徒間で学び合うことの興奮について報告している。なかには自分の必修課題よりも、仲間を助けるための任意のディスカッションにより多くの時間を費やした生徒もいた。
これらの要素は、修了率にも関わってくる。上述のような指標を過度に重視すべきでない正当な理由もあるだろう。しかしオンライン講座の離脱率は平均で90%以上という状況(英語記事)では、生徒間の対話と協働はどうしても損なわれてしまう。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)