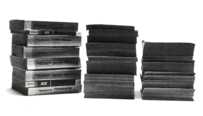④オンラインでの協働の規範(マナー)は、能動的に形成できる
オンライン上の交流は、たいてい次の3つのいずれかになる。結局は盛り上がらずに終わるか、時とともに交流の質が高まっていくか、低俗な大衆嗜好へと収束してしまうかだ。低俗化は多くのウェブサイトで見られ、不作法あるいは冒涜的なコメントが良質なコメントを駆逐する。また、時にはその反対が起こる場合もある。しかしオンラインでのマナーは、成り行き任せではなく運営者が方向づけることもできるのだ。
HBXでは講座の開始時に、強く奨励される振る舞いと望ましくない振る舞いを示し、オンラインでの交流の規範を明らかにするよう努めた。他者への反論は、敬意をもって行われる限り奨励される。無礼、下品、傲慢な態度は歓迎されない。こうした方針に反する生徒には警告が与えられ、場合により除籍の可能性もある。
最初に規範を明らかにしておくことの最大のメリットは、ひとたび条件と期待を包括的に示せば生徒たちが互いにチェックし合うようになることだ。HBXではその様子が実際に数回見られた。ゲーム理論家トーマス・シェリングの言葉を借りれば、フォーカル・ポイント(コミュニケーション手段がない場合に、人々が採用するであろう自然、特別、または適切な解決策)、つまり人々の期待値の焦点を定めれば、それを中心に協調が生まれるということだ。成り行きに任せてしまえば、予想外に悪い結果が待っているかもしれない。
⑤交流型の学習は専門家の知識に匹敵する
オンラインを含むほとんどの教育は、「学習を牽引するのは専門家(教授者)である」という考えに根差している。これは教育コンテンツの作成においては正しいであろう(実際にHBXの各講座は、HBSの教授陣と協力者のチームによって数カ月かけて入念につくり込まれた)。しかし生徒側における、教材への理解、定着率、発見型学習については当てはまらない。専門家の介入が早すぎると発見を阻害してしまうのだ。
交流型学習は我々がHBXをめぐり決断した大きな賭けだったが、最も重要な教訓をもたらしてくれた。生徒から質問が挙がった時、我々教授陣は応答に加わりたいという衝動をこらえて、生徒同士でのやり取りに任せた。生徒がコンセプトの理解に苦しんでいた時、我々は手を貸したいというさらに強い衝動を抑え、他の生徒たちに軌道修正を任せた。
結果は目を見張るものだった(そして専門家にとっては頭が下がる思いであった)。挙げられた質問の9割以上が、他の生徒たちによって正確かつ具体的に解答されたのだ。COReのある生徒は以前、最も人気のあるムーク(MOOC:大規模オンライン公開講座)の1つでティーチング・アシスタント(TA)のリーダーを務めていた。彼によれば、オンライン講座において教える側が直接関与する方法の典型は、TAを大勢揃えておき、生徒から寄せられるどんな質問にもこれらの“専門家”がすぐに対応できるようにしておくというものだ。しかしこのやり方は、予期せぬ結果を招いたという。間もなく誰もが、質問にはTAが答えてくれるものと期待するようになり、生徒たち自身での助け合いをやめてしまったのだ。
「生徒たちを信頼しよう」というのが我々の合言葉だ。これは守るのが非常に難しい。専門家や教師は、生徒側に混乱の兆しが見られたらすぐさま助けの手を差しのべたくなる。しかしその衝動をこらえれば、学習者による発見を促せる。生徒たちを信頼することで、彼らはみずから問題を解決するよう迫られ、それが協働の原動力になる。専門家による介入は協働を阻害しかねないのだ。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)