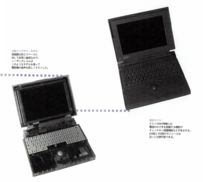トップダウン型の限界と
ファシリテーションへの注目
「ファシリテーション型リーダーシップ講座」に参加した、ある大手メーカー人事部で働くBさんのエピソードを紹介したい。Bさんは、講座で学んだことはこれからの管理職全員にとって必須のスキルだと考え、人事として社内向けに「ファシリテーション型リーダーシップ研修」を新設する企画書を上司である人事部長に提出した。ところが、上司は「ファシリテーション型リーダーシップ」の必要性が納得できていない様子だった。そこでBさんはある実験を行なった。
この企業では年に一回全社で職場の整理整頓を行う「5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)週間」という恒例行事があった。工場では当たり前の「5S」運動だが、人事を含む本社部門では積極的に参加する社員は少なく、「5S週間」が終わればすぐに元の汚い状態に戻ってしまうのが恒例だった。
そこでBさんは、人事部門にある5つのチームのうち、1つのチームは従来通りのトップダウン型の指示で整理整頓を行い、残りの4つのチームでは若手を「5Sプロジェクト」のファシリテーターとして任命して、ファシリテーションの基礎知識をレクチャーした上で、チームでプロジェクトの進め方を考えさせることにした。すると、若手ファシリテーターはチーム内に点在していた工場出身者を講師として5Sの重要さを学ぶ時間を設けるなど、従来のトップダウン型とはまったく異なる進め方を行なった。結果、ファシリテーション型で進めたチームの方が圧倒的に職場が綺麗な期間が長かったそうだ。そして、それを目の当たりにした上司は、トップダウン型の限界とファシリテーション型の効果を実感したという。
このように通常の組織で行われる業務でさえも、プロジェクトだと捉えることで成果を高めることができる。また、通常の組織の多様化も進んでいる。同じチームに外国人や時短勤務の社員、飲み会に参加しない若者など、通常の組織であっても多様なメンバーが増え、従来のような「阿吽の呼吸」が通じる組織は減った。そのような組織でイノベーティブな成果を求められている中、リーダーに必要なスキルとして注目を集めているのが「ファシリテーション能力」である。
では、プロジェクト推進に必要なファシリテーション能力とは何か。従来のリーダーシップとファシリテーション型リーダーシップとは何が違うのか。そのような点について、次回は考えてみたいと思う。
※第2回につづく。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)