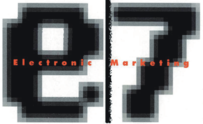働き方、価値の出し方を
グローバルに統一する段階
伊賀:ちょっと話は戻るんですが、先ほどネスレはずっと新興国で稼いできたと言われましたよね。実は私、若い頃に南米やらアフリカやら、世界中を旅してたんです。
高岡:へえ、すごいですね。
伊賀:そういう時、何時間もバスで走って到着した森の中の国境オフィスの売店で売られている商品が、どこでもだいたい同じなんです。
たとえばネスレのコーヒー、ナビスコのビスケット、ニベアのクリーム、プロクター・アンド・ギャンブルの洗剤、あとはコカ・コーラ。どうやってこんな僻地にまで商品を届けているのか、本当に驚くような僻地にまで商品が届いている。あれには驚かされました。
私が社会人になった頃、日本はバブル経済が始まって「ジャパン・アズ・ナンバーワン」とか言って浮かれていました。たしかに空港から伸びる幹線道路には、どの国でも日本の自動車メーカーや家電メーカーの看板がデカデカと掲げられていました。でもちょっと地方の小売店に行くと、日本商品なんてまったく見ない。さっき言ったような、欧米のグローバル企業の商品ばっかりなんです。
今から考えると、日本がまだ戦後の焼野原だった時代から、そういうグローバル企業はすでに南米の奥地の小さな売店にまで流通ルートを開拓していたんですよね。その彼我の差には驚くしかありません。
でも高岡さんがおっしゃったように、今は地理的な販路拡大だけでは売上げは伸ばせない、だから質的な転換、つまりイノベーションが必要になったというわけですね。
高岡:ネスレグループの中で、日本は人口減少・少子高齢化が進む最も厳しい市場であるのに、売り上げも利益もすごい勢いで伸び、グループをリードする存在になっている。その要因がビジネスモデルとか、マーケティングやイノベーションにあることは、本社の役員たちもわかっていました。
それはわかっているけれども、では、日本で起こったイノベーションをノウハウ化して、グローバルに展開するにはどうすればいいのか。日本はヨーロッパからはあまりにも遠いし、いろいろ特殊な市場だから、あそこで成功したからといってそのノウハウはほかのマーケットでは使えない、ややもするとそういう議論になってしまいがちなんです。
伊賀:それにしてもすごいことですね。グローバル企業の中でも、日本のやり方を他国の支社が真似て導入していく必要があるっていう状況にできている企業、あまり聞きません。さすがの経営手腕だと思います。
それと、「うちの国は特殊だ」っていう話。これはグローバル化にはつきものの壁ですよね。マッキンゼーの発祥はアメリカのシカゴで、最初の海外進出先はイギリスだったんですけど、グローバルトレーニングの際に年配のダイレクターから聞いたところによると、当時はイギリス人でさえ「アメリカのやり方はイギリスでは通じない」とか言って反発してたらしいんです。
その後、フランスやドイツに支社を開いたのですが、今度は「いや、英米流のアングロサクソンなやり方はわが国では通用しない」という声があがる。もちろん日本支社でも長らく「日本は特殊な市場だから」と言われてました。今は「中国は違う」とか「中東は違うんだ」とか、延々と続いてます(笑)。
こうした地域特殊論というのは、グローバル企業の発展段階では必ず起こります。でもその一方で、結局さいごはどこも同じだったという話になる。しかも今は企業より先に消費者がグローバル化しているケースも多いので、最初から世界全体で同じやり方をとってくる企業の躍進スピードがすごく早い。「特殊だから。他とは違うから」と言っていると、失ってしまう時間価値が大きくなってしまう時代だと思います。
【著作紹介】
生産性―マッキンゼーが組織と人材に求め続けるもの
(伊賀泰代:著)
「成長するとは、生産性が上がること」元マッキンゼーの人材育成マネジャーが明かす生産性の上げ方。『採用基準』から4年。いま「働き方改革」で最も重視すべきものを問う。
ご購入はこちらから!
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]










![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)