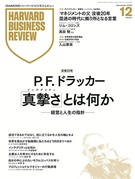服装規定を再考する
性別に基づく既存の制度(服装規定など)や施設(トイレやロッカールームなど)を土台にトランスジェンダーのインクルージョンを目指す仕組みは、意図せずして、ノンバイナリー、ジェンダーフルイド、ジェンダー・ノンコンフォーミングの人たちを排除する結果を招く。
その種の仕組みは、トランスジェンダーの社員が「男性」「女性」に関する社会の固定観念に適応しなければ、職場で受け入れられない時代につくられたものだった。
しかし、ジェンダーに関する男女二者択一的な思考そのものに異論を唱える人が増えるにつれて、こうした制度は意義を失い始めた。トランスジェンダーの人だけでなく、自分の性別に対して典型的に期待されるような制服を着たくないシスジェンダーの人にとっても、有益な制度とは言えなくなったのだ。
服装規定をいっそうインクルージョン志向なものにするためには、ジェンダー化された言葉遣いでルールを定めるのではなく、どのような服装が許容されて、どのような服装が許容されないかをより具体的に定めればよい。
「20キロの荷物を運ぶ妨げにならない服装をすべし」といった具合に機能性を基準に定めたり、安全性、個人識別のしやすさ、ブランディングなど、正当なビジネス上の目的を理由に定めたりすればよいだろう。もし意見対立が持ち上がることがあったとしても、このような基準があれば、それを土台に話し合い、どのような服装が妥当かについて具体的に議論できる。
私たちの調査によれば、正式な服装規定という形を取るか否かに関係なく、性別に関する固定観念に基づいた服装を要求される状況は、固定観念によって規定されたくない人たちに、きわめて大きなストレスをもたらす。その結果、そうした人たちが服装に関する期待に異議申し立てすることも多い。
ローワンは、ノンバイナリー。人称代名詞は「he/him」でも「she/her」でもなく、「they/them」を望む。
職場での性別表現を変え始めた時、服装に関する期待と衝突した。日によって、一般的に男性的とされる服装で出勤したり、女性的とされる服装で出勤したりしていた。
すると、人事部門の人物がすぐに取り締まりを始めた。そのような服装をすることで会社の評判にダメージが及ぶと言い、採用イベントでワンピースを着たり、メークをしたりすれば、代償を払うことになると警告した。
パーカーは、トランス男性。人称代名詞は「he/him」を用いる。長い間、男性的な(ブッチ)レズビアンと自認していたが、その後、トランスジェンダーであると再カミングアウトした。
ブッチレズビアンを自認していた頃は、男性的な服装のせいで、職場の男性たちからも女性たちからも嘲笑を浴びた。業務関連のカンファレンスに出席するための出張を申請した時は、スカートとワンピースを着ていくことが条件だと言われた。パーカーは、この求めに従うことを拒んだ。