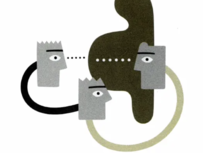思い込み(1) 成功は個人の努力の結果である
個人の努力やハードワークが、成功につながると思われがちだ。その考え方だと、成功「しない」人は、強い労働倫理を持っていないからということにもなる。
しかし、カナダの心理学者ロジャー・バーンズリーが、1980年代半ばに実施した調査を考えてほしい(マルコム・グラッドウェルが著書『天才!』で紹介した)。アイスホッケーのエリート選手の中には、年初に近い時期に生まれた選手が不釣合いに多いという。それはなぜか。
カナダのアイスホッケーチームは、1月1日を境に年齢別になっている。1月2日に10歳になった子どもが、10歳になるまであと1年かかる子どもと一緒にプレーすることになるのだ。わずか12カ月でも、この年代では身体的な差は大きい。
その結果、2人とも同じような努力をしても、先に生まれた子どものほうがオールスターチームに選ばれる可能性が高く、より多くのプレー時間とよりよい指導を受けられる。これはトップリーグへの道を開く、経年的な「累積的優位」だ。
従業員は誰もが、自分では直接コントロールできないものも含め、能力や経験をユニークに組み合わせた状態で組織に参画するため、パフォーマンスや生産性のレベルがそれぞれ異なる。パフォーマンスの高い人は、時間の経過とともに優位性を蓄積していく。その結果、リーダーシップ開発プログラムを受けたり、HiPosだと見なされたり、地位が高く人前に出ることの多い役割に昇進したりする可能性が高まるのだ。
それ以外の従業員にもたらされるのは「累積的不利」だ。パフォーマンスが低い、あるいは中程度の人は、自分のスキルや能力を向上させるための開発プログラムから除外されるので、パフォーマンスが現状に留まるか、低下する可能性が高くなり、キャリアアップの機会が少なくなる。
この問題に対処する方法の一つは、すべての従業員を対象としたトレーニングサポートを提供し、対象者のパフォーマンス基準を柔軟に設定することだ。
世界的なソフトウェア企業のアドビが導入する「ラーニングファンド」は、継続的な教育と専門能力の開発を支援するために、「パフォーマンスのよいすべての従業員」に対して、学位やその他の資格取得のために年間1万米ドル、短期的な学習機会のために年間1000米ドルを上限として補助を与えている。
ラーニングファンドに関しても、従業員のパフォーマンスが対象者を決める際の論点であることに変わりはないが、ハイパフォーマーだけに偏った選出がされるわけではない。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)