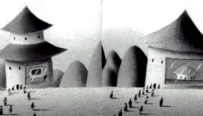米国経済における強さの源
労働市場の活況は、賃金と支出の増加につながり、実体経済の強さを判断するうえでよい材料になる。消費支出は、財消費の冷え込みと、拡大するサービス消費の間で綱引き状態にある。ロックダウンと景気刺激策により、耐久消費財の消費がオーバーシュートしたことを受けて、実質消費支出は減少しており、新型コロナ以前の水準を上回っているとしても、反動を受けた状態にあるのは明らかだ。
一方で、サービス消費は2倍の規模があり、高いインフレ率にもかかわらず、消費者には休日のレジャーやレストランでの食事などの活動を取り戻そうとする動きがある。全体的に、消費はレジリエンスを発揮して、いまのところ成長を続けている。
労働市場の活況に加えて、家計のバランスシートが非常に堅調であることも、好調な消費を支えている。家計の純資産は、全世帯を5等分した所得五分位階級別に見ると、すべての階級で新型コロナ以前よりもはるかに多く、インフレと消費者心理の悪化という逆風をある程度、和らげている。
なかでも際立っているのは、現金残高だ。所得が最も少ない第1階級を除いて、ほとんどの米国人は、新型コロナ前を大きく上回る現金を保有している。中間層(40~60パーセンタイル)が2019年末に保有していた現金は推定1000億ドルで、現在は5300億ドルを超えている。インフレはそれだけ購買力を抑え込んでしまっており、明らかに支出を妨げている。
企業業績も依然として好調で、収益性は記録的な高さが続いている。しかし、逆風にさらされているのも事実だ。S&P500企業の利益率は、異例の高水準から下がりつつある。その大きな要因は、売り手優位の労働市場で、労働者を集めてつなぎ留めるために、賃金が急上昇していることである。
しかし、名目上であっても売上高は力強く成長し続けており、いまのところ利益率の低下を十分に補って、過去最高益に近い水準に達している。このような利益水準と強い労働需要を背景に、企業はすぐに解雇に踏み切れないため、労働市場と消費は堅調に推移し、それが企業の売上と利益をさらに強化している。
米国経済の強さがもたらす呪い
こうした状況は、インフレに勢いをつけなければ、いい兆候だろう。しかし、インフレはあまりに強力で広範囲にわたっており、とても動きが速い。消費者物価指数は2022年8月と9月に予測通り押し下げられたが、その下落幅は失望するほど小さく、インフレが多くのカテゴリーに広がっていることがわかる。
たとえば、エネルギー価格の高騰に対して、米連邦準備理事会(FRB)ができることはほとんどない。物価の上昇を許容範囲に引き戻すためには、影響を与えられる範囲でいっそうの努力が求められる。
その主なターゲットは、賃金インフレを引き起こしている、売り手優位の労働市場だ。FRBとしては、インフレ目標の2%に見合う水準まで賃金上昇率が落ち着くように、労働市場の需給が鈍化することを期待している。もっとも、賃金上昇率が6%を超えて活気に沸くサービス業を見る限り、まだそれには時間がかかりそうだ。
こうしたことから、FRBは「金利パス」、すなわち一連の利上げを高い水準に設定し、少なくとも2025年末までは金融政策の「引き締め」を維持する見込みだ。今夏、市場はこのFRBの発表に疑念を抱いていたが、最近は現状をほぼ受け入れて、今後数年はFRBによる積極的な金利政策を織り込むようになった。
これは現代において特異な状況であり、FRBや市場は通常、経済の強さを問題視しない。問題となるほど高いインフレをもたらしているのは、供給サイドの能力を上回る需要の周期的なオーバーシュートである。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)