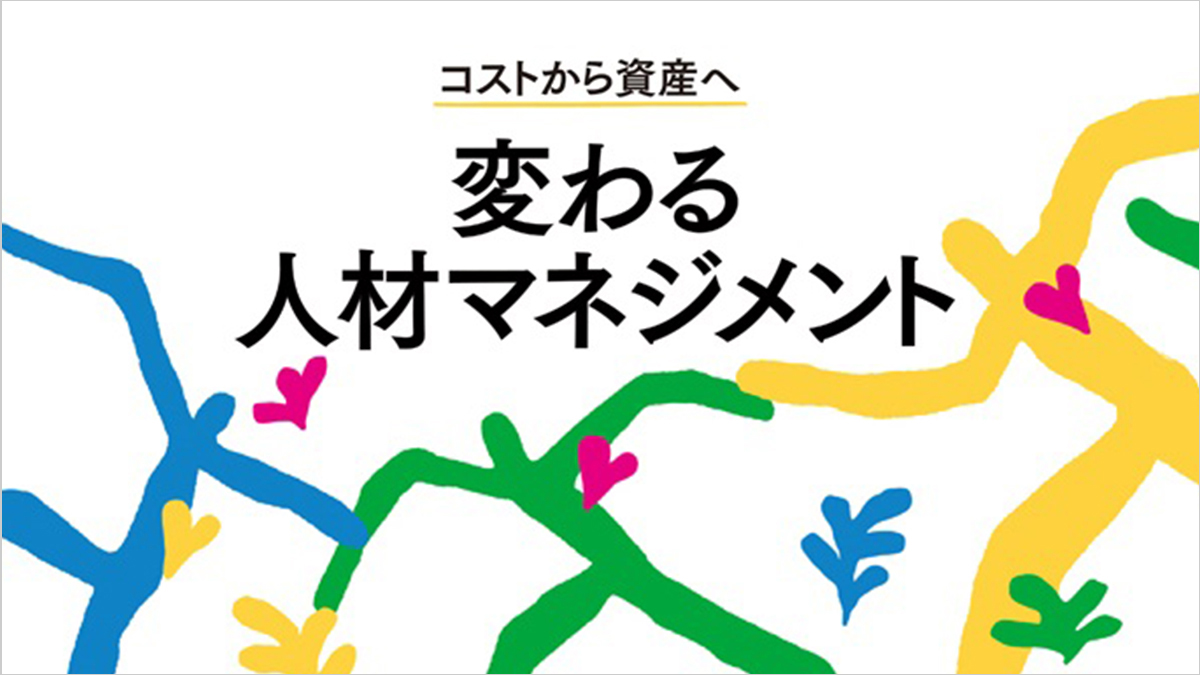
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
コロナ禍を経て変わる人材マネジメント
新型コロナウイルス感染症によるパンデミック前まで、先端的な企業では、遊び心のあるオフィス設計や無料の飲食物の提供が流行していました。米HBR編集部にも卓球台が置かれていましたが、それも無用の長物となったようです。
いま従業員のニーズは、給与や職場環境から勤務の柔軟性や仕事の目的意識へと大きく変わっています。そこで今号の特集「変わる人材マネジメント」では、「人的資本」と呼ばれる従業員のニーズに企業が応え、その人材の可能性を組織として引き出す方法について考察します。
国内では、2023年度から人的資本の情報開示が一部義務化されたことを受け、大手企業を中心に、人材マネジメントのあり方が大きく変化しています。そもそも人的資本とは何でしょうか。ピーター・キャペリの論文「従業員は企業のコストではなく『資産』である」では、人的資本をめぐる米国財務会計上の課題を明らかにすることで、人材投資の効果について論じます。
新たな働き方の研究を続けるマーク・モーテンセンとエイミー・エドモンドソンは、論文「従業員価値提案を見直すべき時」において、従業員ニーズに真っ先に応えることはやめよと述べます。リーダーは、目先の課題に対処するのではなく、「能力開発・成長の機会」や「つながり・連帯」などの4要因から、人材マネジメントを包括的に検証する必要があります。
部下に任せた仕事が期待とは異なる成果物として提出されたことはないでしょうか。あるいは、上司の指示が曖昧であったり難易度が高すぎたりしてその仕事を都合よく解釈したことはないでしょうか。論文「部下と上司の職務を正しく設計する方法」では、上司と部下のミスコミュニケーションを防ぐための方策を述べます。
そのほか、インタビュー記事も充実しています。外資系企業の人事経験が長い、アステラス製薬の杉田勝好専務は「人事ほど経営戦略の実現に貢献できる仕事はない」と述べます。人材の価値を軽視してきた日本企業に対し「能力開発の機会や労働環境の整備を怠っていないか」と投げかけます。
キリンホールディングスの磯崎功典社長は、「キリンは 『挑戦』と『対話』で従業員の無限の可能性を引き出す」と話します。自身のホテル経営の経験を踏まえ、従業員の意識を変えて成長を促すために必要なのは新規事業に挑戦することだと説きます。また、リーダーの役割として、部下との対話のアプローチが有効であることを強調します。
さて、新年度を迎えました。今特集を機に、人材という会社の「資産」の可能性にあらためて目を向けてはいかがでしょうか。
(編集長 小島健志)





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









