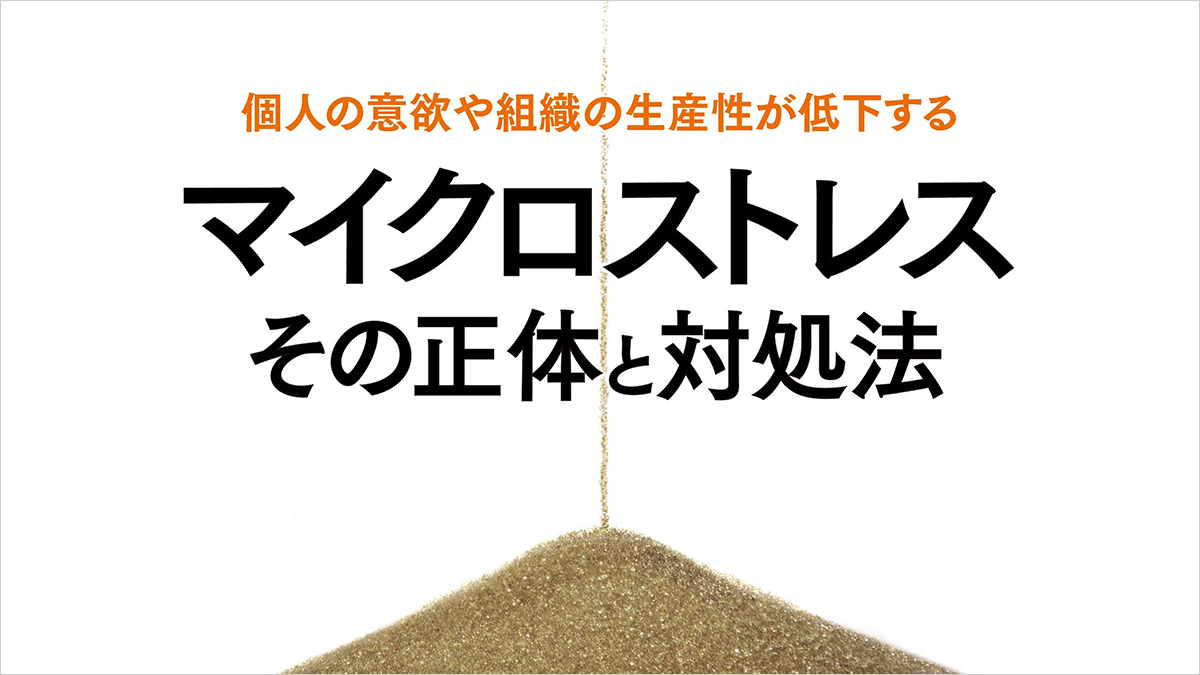
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
マイクロストレスの正体
締め切りに遅れそうな同僚を手伝ったり、身近な人からのメールやチャットの対応に追われたり、終業間際に新たな仕事を頼まれたりする──。今号の特集「マイクロストレス その正体と対処法」では、このような些細なストレスが積み重なることで、徐々に私たちの意欲が奪われ、チームや組織の生産性が低下するメカニズムを明らかにします。
特集1本目の論文では、マイクロストレスは自覚できないものだと述べられます。脳ではその重大性を認識できないにもかかわらず、通常のストレス同様に、体には血圧や心拍の上昇、ホルモンや代謝の変化が起きます。また、放っておいて消えるものでもないため、いつのまにか精神的な余裕が奪われ、消耗するというのです。
特集2本目「マネジャーはマイクロストレスをどう管理するか」では、マネジャーがマイクロストレスに脅かされる実態を3事例から描きます。その影響はチームや組織にも及びます。筆者らは総じて、幅広い人間関係を築くことの重要性を指摘します。
特集3本目「思考の罠から抜け出し、不安を手なずける方法」は、成功している人ほど不安に陥りやすい状況を解説します。物事を正確に見て、適切な判断を下すためには、「思考の罠」を回避することが欠かせません。
特集4本目は、マッキンゼー・アンド・カンパニーの酒井由紀子氏による「エンプロイーヘルス・マネジメント:従業員の心身の健康を保ち、組織の生産性を高める」です。日本企業としてメンタルヘルス問題やウェルビーイングの向上にどう向き合うべきか、グローバル調査をもとに解説します。中でも「誰を対象に」と「何を目的とするか」の組み合わせによって異なる介入プログラムの設計法を明らかにします。
特集5本目は、禅僧の藤田一照氏へのインタビュー「人生はストレスに満ちているが、苦しみに向かう必要はない」です。ストレスは個々のとらえ方次第で大きくも小さくもなり、そのコントロールのカギは「いま、ここ、私」にあるといいます。自己を自覚し、自分自身の心のあり方を認めることが大切です。
さて、休日まで頭に霧がかかった状態のリーダーは要注意です。今号の診断表を活用して、いまの状態を確認してみてください。自分の心のあり方を見つめ、人間関係を広げていくことで、マイクロストレスから身を守ることができ、さらに自身や組織を高めていけるのです。
(編集長 小島健志)





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









