ソーシャルメディアの「壁に囲まれた庭」の問題
ツイッターやフェイスブック、リンクトインといった最大手のソーシャルメディアアプリケーションは、ウォールドガーデン(壁に囲まれた庭)──ユーザーの情報をプラットフォーム内に閉じ込め、アクセスを厳格に管理する自己完結型のエコシステム──として設計されている。ユーザーが自身の投稿や写真などのコンテンツをエクスポートすることも可能ではあるが、他の場所に簡単に移行できる仕組みにはなっていない。手動で一つずつアップロードし直すしかない。
さらに、「いいね」など評価に関する情報や、フォローグラフ(フォロー先やフォロワーの情報)などのネットワーク情報も抽出できないため、ユーザーは新たなプラットフォームに参加するたびに、フォローグラフや評価を再構築せざるをえない。その結果、コンテンツの拡散力が極めて大きかったり、膨大な数のオーディエンスを持つパワーユーザーは特に、他のプラットフォームへの乗り換えに消極的になる。
こうした状況は、ソーシャルメディアプラットフォームが市場での優位性を確立するための後押しとなってきた。競合他社に乗り換えるのは面倒だから、ユーザー体験が低下しても、ユーザーはそのプラットフォームを使い続ける。プラットフォーム側は必ずしもユーザーの最善の利益のためにコンテンツのキュレーションを決定するわけではないし、仮にそうしようとしても、うまくいくとは限らない。最近、批判を受けたツイッターのフィードアルゴリズム変更が、そのよい例だ。
この状況は、プラットフォーム関連の仕事で生計を立てている人にとって、とりわけ大きな頭痛の種となる。コンテンツクリエイターが何年もかけてオーディエンスを築き上げても、プラットフォーム側の都合によるさまざまな理由で、一瞬にしてそれが失われることもありえる。ソーシャルメディアプラットフォームのAPIを利用してきた開発者も、プラットフォーム側の気まぐれに振り回される。ツイッターやレディットが最近行ったように、「壁に囲まれた」プラットフォームは自由にAPIの価格設定を変更したり、APIへのアクセスを完全に遮断したりできるのだ。
一般ユーザーへの影響もある。「壁に囲まれた庭」において、ユーザーのデジタルアイデンティティやソーシャルネットワークは、プラットフォームごとに切り離されてサイロ化している。たいていの場合、人は一つ、あるいはごく少数のソーシャルメディア環境に注力せざるをえず、その結果、コンテンツを最大限に広範囲のオーディエンスに届けられないおそれがある。
たとえば、筆者らの同僚の多くは、ツイッターで業務やテクノロジーに関する投稿を積極的に行っている。彼らの投稿はリンクトインでも支持を集めるだろうが、彼らにはリンクトインでエンゲージメントを確立する時間的余裕はない。複数のプラットフォームでオーディエンスを獲得するためには、コンテンツを分散させるか、多かれ少なかれ同じような内容をあちらこちらに投稿する、という非効率なプロセスを踏むしかないのだ。
プラットフォームからオープンプロトコルへ
一方、オープンプロトコルに基づくソーシャルメディアであれば、こうした問題のいくつかを解消できる。異なるプラットフォーム間でデータを共有できるようにすることで、プラットフォームの垣根を超えたコンテンツ消費と評価の形成が可能になる。また、開発者がさまざまなフィードアルゴリズムやコンテンツ配信モードをリミックスして実験する道も開けるだろう。
プロトコルとは、プラットフォームの内部システムを構成するソフトウェアであり、機能面(各ユーザーアカウントがどのような情報を有しているか、ユーザーがどのようなタイプのコンテンツを作成できるか、など)、および状態(ユーザーのデータやインタラクションの履歴)を決定する。
ユーザーは、「クライアント」と呼ばれるフロントエンドのアプリケーションのレイヤーを通して、この内部システムとやり取りしている。たとえばツイッターでは、ユーザーはツイッターウェブやモバイルクライアント、さらにツイートデックやフートスイートといったクライアントなど、多様なアプリケーションを通じてバックエンドのプロトコルとやり取りしている。ただし、ツイッターの場合、プラットフォーム自体がプロトコルへのアクセスを管理しており、実際、同社は自社の主要アプリと競合する多くのクライアントを最近、締め出したばかりだ。
これに対して、オープンプロトコルのアプローチでは、中核となるソフトウェアプロトコルを一般のコンピューティングインフラ上(ブロックチェーン上のケースも多い)に公開しており、他のアプリにもプラグイン可能な標準フォーマットにデータを記録している。おかげでユーザーは、一つのソーシャルアカウントを同時に多くの異なるプラットフォームにリンクさせることができ、フォロワーやコネクションの情報、さらには、特定のコンテンツやそれに対するリアクションまで、おそらくリンク可能になる。これは「グーグルでログイン」にやや似ているが、仲介役は存在しない。
つまり、オープンプロトコルに基づくソーシャルメディアでは、IDが統一され、持ち運び可能なのである。コンテンツの作成者は単一のプロトコルを使って、短いコンテンツはスレッズやツイッター、写真はインスタグラム、長編動画はユーチューブやツイッチへ、という具合に各プラットフォームに振り分けられる。しかも、閲覧数や「いいね」の数は、すべてのプラットフォームで共有される。さらに、コンテンツの消費者は、プロトコルレベルで統一されたフォローグラフのおかげで、利用中のすべてのソーシャルメディアプラットフォーム上で、お気に入りのクリエイターとつながることが可能になる。
ソーシャルメディアがクローズドなプラットフォームでなく、オープンなソフトウェアプロトコルを利用する流れは、「ウェブ3」と呼ばれるインターネット技術の大きな潮流の一部だ。ユーザーが自分のデータなどのデジタル資産を直接管理し、そうしたデジタル資産を異なるプラットフォーム間で柔軟に使えることが、その潮流の中核である。
筆者らの一人(コミナーズ)がクードス・ラボの共同創業者ジャド・エスバーと共同で執筆した記事や、ウェブ3とマーケティングの専門家であるスティーブ・カチンスキとの共著(2024年1月発刊予定)で詳しく説明しているように、このモデルはユーザーに、より完全な、そしてより統一されたデジタルアイデンティティの構築に投資する機会とインセンティブをもたらしてくれる。ユーザーは、現実世界で慣れ親しんでいるのと同じ要領で、みずからのIDと評価を携えて、複数のデジタル環境を行き来できる。
オープンプロトコルシステムには、ユーザーと開発者、企業にとって理論的に明らかなメリットがある。まず、ソーシャルメディアにおけるユーザーとプラットフォームの関係を変えることで、競争を加速させられる。あるプラットフォームの質が低下したり、他に優れたプラットフォームが登場した場合、ユーザーは自身のデータとオーディエンスを携えて、簡単に競合他社に乗り換えられるのだ。
コミナーズがライトスパークの共同創業者で、マサチューセッツ工科大学(MIT)クリプトエコノミクス・ラボ創設者のクリスチャン・カタリーニと共同で書いたように、これによって市場の競争が加速し、品質でしのぎを削ることが期待される。
ただし、このプロセスが機能するのは、プロトコルの作成者が、システムが継続的にオープンでアクセス可能であると保証できる場合のみだ。そのためには一般的に、どこか一つの事業体や個人によって完全に制御されることのない、ブロックチェーンなどの分散型インフラ上にプロトコルを構築することが求められる。
たとえば、ブロックチェーンベースのソーシャルメディアプロトコル「ファーキャスター」は、同プロトコルを利用するすべてのクライアントで使用可能なIDとユーザー名を各ユーザーに付与する「ネームレジストリ制」を採用している。そうした情報はイーサリアムのブロックチェーン上に保存され、各ユーザーのイーサリアムアカウントにひもづけられる。このアカウントはユーザーの管理下にあり、ユーザーはファーキャスタープロトコルのIDを、エコシステム内のどのクライアントにも持ち運べる。サードパーティの開発者は、異なるコンテンツフォーマットや異なるユーザー層向けに多様なクライアントを構築する権限を付与され、また、そうするよう奨励される。
実際、ファーキャスターのプロトコルをベースに構築されたサードパーティアプリケーションのエコシステムがすでに登場している。また、ブルースカイやマストドンのような非ブロックチェーンベースの分散型ソーシャルメディアプロジェクトも、技術面の仕組みは異なるが、同様にオープンなエコシステムとユーザーの利益を目指している。

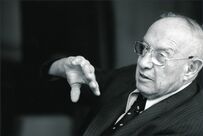






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









