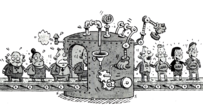地域に適したハイブリッドワークを設計する
筆者らは地域による違いを発見したが、そこから言える重要な点は、どのような違いがあるにしろ、リーダーは方針を設定する場所の背景を理解するために時間を割かなければならないということだ。
従業員にとって、ある方針が約5000キロメートル離れた本社の一般的な通念と一致しているかどうか、あるいは人気のある評論家のツイートと合致するかどうかなどは、どうでもよい。その方針が従業員の経験や置かれている現場のニーズと調和するかどうかが、大切なのである。同様に、もし従業員が柔軟な働き方を望んでいない、あるいは望んでいるとしても勝手に制限してしまうなら、柔軟な働き方を提供するグローバルな方針は、リーダーにとって何の益にもならない。
あなたの組織の多様な地理的、文化的背景に適したハイブリッドワークに関する方針を設計するためには、次の5つのステップを踏むとよいだろう。
ステップ1:なぜハイブリッドワークを提供するのか決める
柔軟な働き方を提供する理由は、組織によって違うだけではなく、組織内ですら往々にして意見の相違がある。したがって最初の重要なステップは、柔軟な働き方やハイブリッドワークを提供する理由について話し合い、それがどの拠点でも適用できるかどうかを検討することである。
たとえば、あなたの活動拠点では、最上位の目標は生産性の最大化かもしれないが、ほかの拠点では激しい人材獲得競争に直面しているかもしれない。また別の拠点では、任務に不可欠なサポート機能が結束の強い文化に依存しているかもしれない。
もちろん、理想的な答えは、生産性、人材の保持、社会構造という3つのモチベーションの組み合わせである。最も必要なのは、それぞれの拠点や市場での各要素の相対的な重要性について、リーダーレベルで率直に話し合い、どのように優先順位をつければよいかを理解することだ。
ステップ2:従業員がその拠点で何を求めているかを探り当てる
言わずもがなのことではあるが、やはり言っておく必要がある。リーダーは従業員の好みを承知していると思いたいだろうが、往々にして取り違えているか、全体のごく一部しか見ていない。
たとえば、地域の交通事情が従業員の通勤にどのように影響するかを考えてほしい。メキシコシティで交通渋滞の中、片道2時間かけて通勤する従業員と、アムステルダムやコペンハーゲンで街を縦横に走る自転車専用レーンでペダルを漕ぐ従業員の体験を比べれば、ニーズの違いがわかるだろう。
つまり、組織がそれぞれの拠点で何を優先するかが明確になったら、次は各拠点の従業員のニーズがその場所と具体的な仕事によってどう違うかを知るために、時間を割く必要がある。主な拠点でデータを収集して比較しよう。
データを分析する際、従業員のニーズがあなたのニーズと一致しないように見える部分に、特に注目してほしい。そこが盲点になる可能性があるからである。それを話し合いの出発点にして、拠点による好みの違いを理解し、あなたの理解が正しいかどうかを必ず確かめてほしい。「あなたたちが最も優先するのはXだと理解しています。それは正しいですか」という単純な質問をすれば済むのだ。あなたがどこで間違った結論に至ったかが、すぐに明らかになるだろう。
ステップ3:差別化されたハイブリッドワークの提案をする
ハイブリッドワークとなると、一つのやり方がどこでも通用するわけではない。唯一のグローバルな方針を設定しようとするのではなく、ステップ2で収集したデータを活用して、多様な背景に適した提案をしよう。
たとえば、ある拠点の従業員にとって柔軟な働き方が優先事項ならば、在宅勤務日は毎週、好きな曜日を2日選べるようにすればよい。一方、結束を重んじる文化が優先される拠点では、在宅勤務を特定の曜日に限定して、チームの対面での交流を最大化するとよい。
もちろん、提案を差別化するほど複雑さは増し、管理コストも増える。だが、一からつくり直す必要はない。給与も同じように複雑だが、組織は長年、差別化された給与体系を提供し続けてきた。
コストと複雑さのバランスを取る一つの方法は、各拠点のグループに似たようなニーズのパターンがあるか探すことである。欧州のオフィスの従業員には似たようなニーズがあり、それはアジア太平洋の従業員のニーズとは異なるかもしれない。筆者らの研究では広範な地理的カテゴリーで報告したが、あなたは自分のデータを活用して、どの粒度が自分の組織を理解するのに最も役立つかを判断すべきである。地域や国、あるいは地方の違いが最も優れた知見を提供するかもしれない。それに従って方針を設定しよう。
ステップ4:透明性を保ち、公平性に留意する
従業員は次第に、ハイブリッドワークを特権あるいは権利と見なすようになってくる。したがって給与やボーナスと同様、公平と公正の意識を保つことが極めて重要だ。地域による方針の違いやその理由について透明性を保とう。幸い、これまでのステップを踏んでいれば、あなたの主張とそれに伴う決定を支えるデータがある。
ハイブリッドワークはすべてのグループに平等に影響を及ぼすわけではなく、不公平のもとになりうることも認識しよう。筆者の一人であるモーテンセンは、米国にいくつかの子会社を持つ日本の製薬会社との話し合いで、この問題に出くわした。グローバルな労働についてのワークショップの際、在宅でのビデオ会議は、従業員の拠点によって非常に異なる意味合いがあることがわかったのである。
チームの米国人メンバーは快適なホームオフィスからビデオ会議に出席できるが、多くの日本人メンバーは狭いアパートで暮らしているので、家族のじゃまにならない(またはじゃまされない)ためにオフィスにいることを選んだ。同じ方針でも、地域の背景によってもたらされる結果は異なる。
従業員が地域による方針の違いに気づかないことを期待したくなるかもしれないが、真実はたいてい明らかになる。先手を打つほうが賢明だ。
ステップ5:地図を更新し続ける
パンデミック以降の在宅勤務の需要は、オフィスが提供すべきものについての認識が高まることで和らいできた。しかし、経済状況の変化と労働市場の変動のただなかで、ハイブリッドワークの風景は変化し続けている。さらに、こうした要因はすべて多様な地域の背景によって形成されるという事実がある。
したがってリーダーは、方針を設定するだけではなく、それが適切なものであり続けるように定期的に再評価することが不可欠だ。このプロセスのほかのステップと同じように、再評価する時期は地域の背景に合わせなければならない。労働市場と経済状況は地域によって変化の速度が異なるからである。
* * *
以上のステップを念頭に置けば、リーダーは活動する背景の違いに適合したハイブリッドワークの方針を設計することができる。そして、ある地域のニーズには応えても、別の地域では新しい頭痛の種を生むような方針を設けずに済むだろう。
"How Opinions About Hybrid Work Differ Around the Globe," HBR.org, August 21, 2023.







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)