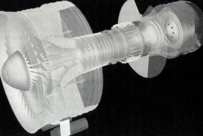開発セクターおよび日本政府の変化
第3に、開発セクター(国際機関やNPO)と日本政府の変化である。開発の世界においては、1970年代には「南北問題」が提起され、先進国経済と途上国経済の格差が問題視されて、例えば先進国の多国籍企業(MNCs)が途上国へ進出することは、貧困国からの搾取になりかねないといった批判が見られた。
その後海外直接投資は途上国の経済発展に資するものという認識が広まり、80年代以降は多くの途上国が海外直接投資を受け入れる姿勢へ転じた。その間、低所得層が抱えていた様々な社会問題の克服は、主として国際連合の各種機関(UNESCO、UNDP等)や世界銀行、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行といった公的機関、および各種の非営利組織(NPO、NGO)の手によって担われていた。2000年には国際連合によって八つの「ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals, MDGs)」(文末・参考資料1)が整理され、2015年までに到達すべき数値目標が設定された。
しかし、現時点でこれらの目標の期限内の達成度は極めて限定的(初等教育に普及が一部の国で達成された)であり、補助金や寄付に依存する支援の構造自体に限界が感じられるようになった。こうした事態を迎えて高まってきたのがビジネスの力を社会問題の解決に役立てようという動きである。1990年代後半から高まったCSR(企業の社会責任)への関心は1999年の国連によるグローバルコンパクトの提唱に結実した。130か国の7700社が署名し、社会・環境・倫理的側面での責任ある企業行動を求める憲章である。
2008年には、企業の側から社会問題解決への参画を他企業に呼び掛ける運動Business Call to Actionが、国連開発計画(UNDP)の働きかけによって始まった。現時点で世界の主要企業47社(うち日本は住友化学、伊藤忠、ユニチャームの3社のみ)が署名している。アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、世界銀行も、資金面から包括的ビジネスの支援を行っている。2010年に発表されたISO26000 (企業・組織の社会的責任に関する努力目標を提示。コミュニティの重要性等を含む)も、国際社会から企業に対する社会性追求への要請として解釈できるだろう。
日本政府(経済産業省および外務省が中心)も国家の産業競争力強化や、政府開発援助(ODA)が削減される中での国家的プレゼンスの強化という観点から、日本企業による包括的ビジネスの振興政策を2009年度から本格化させている。経産省によるBOPビジネス支援センターの設置や、JICAによるフィージビリティスタディー支援事業、JETROによる参入支援制度などが主なものである。それらのイニシアチブとも呼応し、実業界における関心度も徐々に高まりつつある 。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)