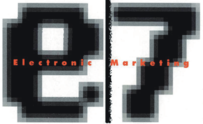第1に、多様なステークホルダーが同時に参加した共創となっている。前回紹介したMI型は、主に企業と消費者との共創であり、その課題として、誰に何を聞けばいいのかわからないという問題があった。
今回紹介したAJICONには、大学を拠点に、タンパク質エキスを作る原材料サプライヤー、将来のB2Bユーザーである病院や介護施設、広告代理店、業界コンサルタント、管理栄養士、公認会計士等、さまざまなステークホルダーが参加している。そのため、より長期的かつ幅広い社会のニーズを取り入れた商品やサービスが開発できる可能性が高い。これは、誰に何を聞くべきか、という問題の新たな選択肢といえる。
第2に、画期的な技術シーズから出発している点である。前回掲げた2番目の課題は、革新的な製品ができないというものだった。AJICONでは、科学技術の最先端にある大学の基礎研究・応用研究段階から、マーケティング志向を徹底させる。マーケティング理論に基づいて、STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)や4P(製品・価格・プロモーション・流通)を考慮したビジネスプランを立てるのである。
そもそもシーズ自体が画期的であることと、それを基に将来の社会的ニーズに応えるプランを立案することから、既存品の改良・改善ではなく、革新的な製品やサービスが生まれる可能性が高い。加えて、将来のニーズを探る際に、発見済みのシーズを応用するという制約を与えることで、実現可能性が担保されている。こうして、最先端のシーズと将来のニーズを結びつけることが可能となる。
第3に、画期的なシーズを用いた商品の開発にも関わらず、開発期間が大幅に短縮できる点も特徴である。その理由は、多様なステークホルダーとの対話をうながすために、プロトタイプ(試作)を早期に行うためである。ワークショップで試食しながら対話し、それを基に商品化の技術課題を抽出するため、早期の問題解決につながりやすい。
文部科学省の狙いどおり、大学がさまざまなニーズとシーズを新たに結ぶハブとなり得る可能性はありそうだ。ただし前回、第3の課題として指摘した、事業としての継続と拡大については、依然、課題として残っている。
イノベーション対話推進プログラムやフューチャーセンターの取り組みは、まだ端緒に着いたばかりである。こうした取り組みをどう育てていくかは社会全体の共通の課題だ。筆者も実践者の一人として、引き続きかかわっていきたい。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)