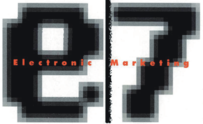オープン・イノベーションの可能性
本連載では、技術だけではないオープン・イノベーションの可能性について考察を重ねてきた。第1回で紹介したように、インバウンド・アウトバウンド、テクノロジー・マーケティングという2軸で考えれば、オープン・イノベーションは4つの類型に分類される。
しかし、繰り返しになるが、イノベーションの本質は、ニーズとシーズの結びつきにある。今回、紹介したイノベーション対話促進プログラムは、最初に紹介した4つの類型のいずれにも属さない、全く新しいタイプのオープン・イノベーションである。
あるべき社会の将来像を描き、そこで満たされるべきニーズと、その実現に必要なシーズとを柔軟に結び付けることこそ、オープン・イノベーションの本質なのである。
――――――
(注1) 文部科学省科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 大学技術移転推進室「イノベーション対話促進プログラムの実施状況報告書について」平成26年6月。
(注2) 文部科学省科学技術・学術審議会 産業連携・地域支援部会 イノベーション対話促進作業部会「大学発イノベーションのための対話の促進について」平成25年5月20日。
(注3) 紺野 登(2008)「未来をつくるワークプレイス、欧州発祥の『フューチャーセンター』」2008年3月27日 。日経ビジネスオンライン。
(注4) 野村恭彦(2012)『フューチャーセンターをつくろう:対話をイノベーションにつなげる仕組み』プレジデント社。
(注5) 川上智子(2005)『顧客志向の新製品開発:マーケティングと技術のインタフェイス』有斐閣。
(注6) 文部科学省「平成27年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者等の決定について」
(注7) 関西大学イノベーション対話プログラム AJICON






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)