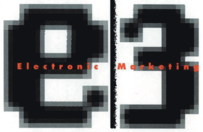同僚や上司、常連客の目にさらされないおかげで、明るい未来を妄想し続けられているドライバーもいる(「運転や配達で、毎日たくさんの人に出会う。その中の誰かが自分の人生を変えてくれるかもしれない!」)。また、仕事でよく起こりうる嫌な出来事に納得している人もいる(あるドライバーは「
また、自分の経験を歪曲しないまでも、一人であれこれ解釈するだけでなく、フェイスブックなどのドライバーのプライベートグループで、仕事の良し悪しや不条理さ、滑稽さを語り合っているドライバーも多い。ほかのドライバーとつながり、比べることによって、互いの物語をすり合わせようとしているのだ。このようなアイデンティティ・マネジメントで、ドライバーたちはかろうじて安堵を覚え、仕事を続けることができている。
筆者がドライバー・コミュニティへの潜入を切り上げた時には、「アプリワーカーの非人格化は、グローバル経済全体で進行している変化によって生まれ、強化された経済モデルのバグではなく特徴である」という思いを拭い去ることができなかった。その変化とは、労使関係の薄れ(独立請負人契約)、テクノロジーへの強い依存(アルゴリズムによる管理、プラットフォームを介したコミュニケーション)、社会的孤立(同僚の不在、顧客との限定的な交流)を特徴とする労働形態が広まっていることである。
重要なことに、こうした変化の影響は、調査した低賃金のギグワーカーをはるかに超えておよび、フリーランス全体が同様の実存的な問いや問題に直面している。アジャイル・ワークフォースや顧客第一主義の導入がほぼ完了したいま、心理的契約(労働者と組織の間にある不文律の期待や義務)が、我々の目の前で書き換えられる危険性がある。実際、強力な心理的契約を支える3つのC、すなわち、成長や出世が可能なキャリア(career)、社会的なつながりや帰属意識を育むコミュニティ(community)、そして仕事に意味とパーパスを与える社会的意義(cause)は、独立しているワーカーにとっても皆無に等しい。
この問題の核心は、企業が目標を達成するために人材を「買う」のではなく「借りる」ことを志向し、実践しているという変化にある。たとえば、経営幹部や上級管理職を対象としたある調査では、回答者の90%以上がデジタル・フリーランス・マーケットプレイスの活用を「非常に重要」または「ある程度重要」と考えており、50%以上が今後デジタル人材プラットフォームの利用を「大幅に増加する」と答えている。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)