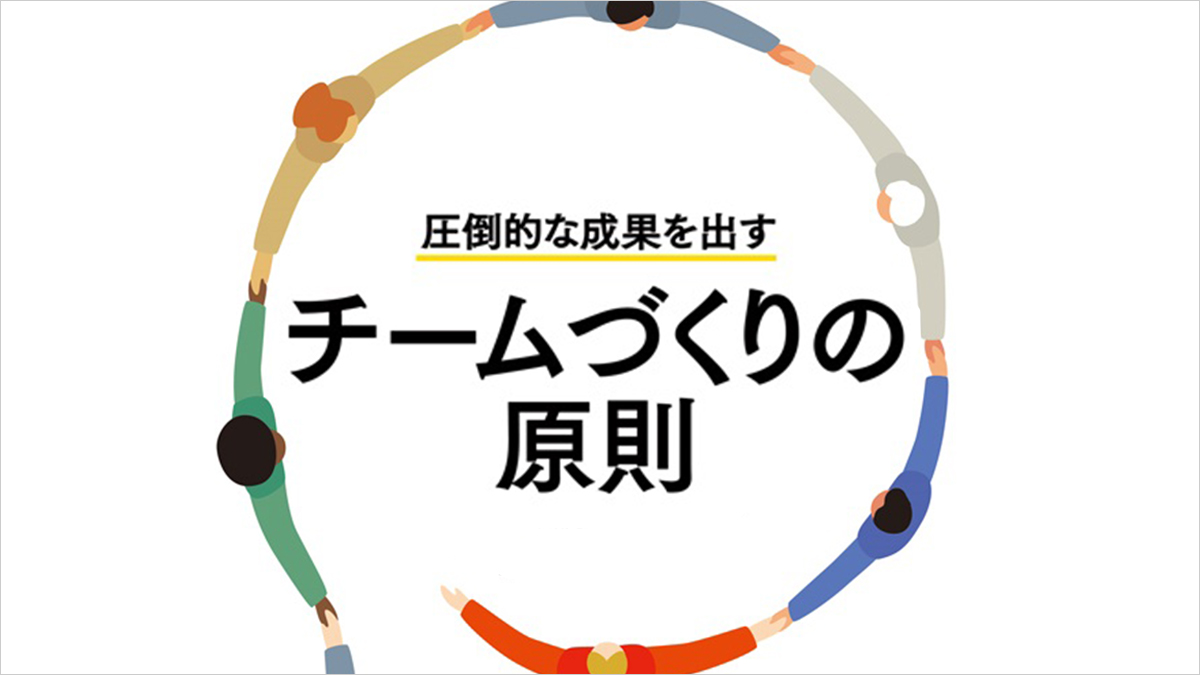
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
機能不全に陥ったチーム
以前、ある革新的なスタートアップの方から、ちょっとした悩みを聞きました。
「とても優秀なメンバーが集まっているのですが、雑用をすすんで引き受ける人がいなくて……。何かをやるにしても毎回、私がその役回りを担っているのです」
決められた業務ではなかったこともあり、食事の手配や会場設営、ごみの片付けなどを「自分の仕事だ」と考える人はいませんでした。チームづくりを促すようなミートアップや食事会などが盛んに行われていたにもかかわらず、その裏側を担うのはいつも決まった人でした。
どうも、メンバーは経営者のことしか見ていなかったようです。そのリーダーの言うことに従えばよいと考え、指示された仕事や定められた業務しかやる必要がないと考えていました。
そのため、引き受け手はいつまでたっても現れず、彼女を苦しめていったのです。
メンバー間の隙間を埋めるような些細なことであっても、チーム内の誰かの助けが必要です。その役割がなければ、感情的なつながりは失われ、連携する機運もなくなり、チームは機能しなくなります。
いつしか彼女もチームから離れ、スタートアップ自体も事実上、解散に追い込まれました。
いま振り返れば、優秀なメンバーが揃っていたにもかかわらず、チームがチームとして機能していなかったのではないか、と感じる出来事です。
圧倒的な成果を出す
チームづくりの原則
「自分たちのチームがその潜在能力を十分に発揮している」と感じているメンバーは2割に満たない──。
時代の大きな変化に組織が適応するためには、強力なリーダーシップが必要だと考えられています。たしかにその考え方は有効です。
ですが、かつてないスピードで世の中が変化し、事業予測が困難になったいま、リーダー個人の力に頼っていてはすぐに成長の限界が訪れます。
意思決定の質とスピードを上げて、組織の変革やイノベーションの実現につなげるためには、組織を構成するチームの潜在能力を発揮する仕組みが必要です。そこで今号の特集「チームづくりの原則」では、チームの持つ力に着目しました。
特集1本目の論文「チームの力を解き放つ新しい協働のあり方」の調査によると、81%のメンバーが「チームの力が発揮できていない」と感じ、71%が「互いを高め合う行動を取れていない」と回答しています。筆者はチームの現状を診断するツールとともに、優れたチームに生まれ変わるための方法を提案します。
また、特集2本目の「チームをチームとして機能させるためにリーダーがすべきこと」では、早稲田大学の村瀬俊朗准教授がチームづくりの原則を述べます。なぜ有能なメンバーを集めたはずのチームが平凡なチームに負けてしまうのか。そこにはチームの目的とメンバーが連携する構造が欠かせません。チームづくりの基本となる考え方と実践するうえでのポイントを提示します。
特集3本目は「業績管理システムの刷新が部門間のコラボレーションを促す」です。チーム間のコラボレーションが大事だと叫ばれているにもかかわらず、業績や目標管理の仕組みが伴っていない企業が目立ちます。個人と組織の目標をリンクさせる4つの視点を提示します。
特集4本目は「職場にはびこるシニシズムを一掃する法」です。マイクロソフトが停滞していた時代、内部競争を過度に促す仕組みによって社員同士の争いが絶えなかったといいます。職場に広がったシニシズム(冷笑主義)を一掃するための具体的な方法論を明かします。
特集5本目の「1on1ミーティングの効果を最大化する方法」では、部下との個別面談にマネジャーの時間を割くことが有益な投資になると述べます。仮に上司が毎週30分費やしても、その時間は年間25時間を超えることはありません。それ以上にはるかに大きな効果が出て、チームの成長につながるのです。
最後は、数々の人気テレビ番組を手掛けてきた、プロデューサーの佐久間宣行さんに、専門性の異なるスタッフや個性あふれるタレントを束ねるための秘訣を伺いました。
インタビュー記事「チームの成長が番組の成功につながり、自分自身にも成果をもたらす」によると、佐久間さんは3つの点を重視して番組づくりを行っています。それが目的の明確化、文化の構築、「やらないこと」の共有です。長寿番組へと導くためのこの考え方は、チームマネジメントのヒントになります。
これらの内容は、チームの見直しに役に立つはずです。チームの変革があってこそ組織の変革につながります。ぜひご一読ください。
(編集長 小島健志)




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









