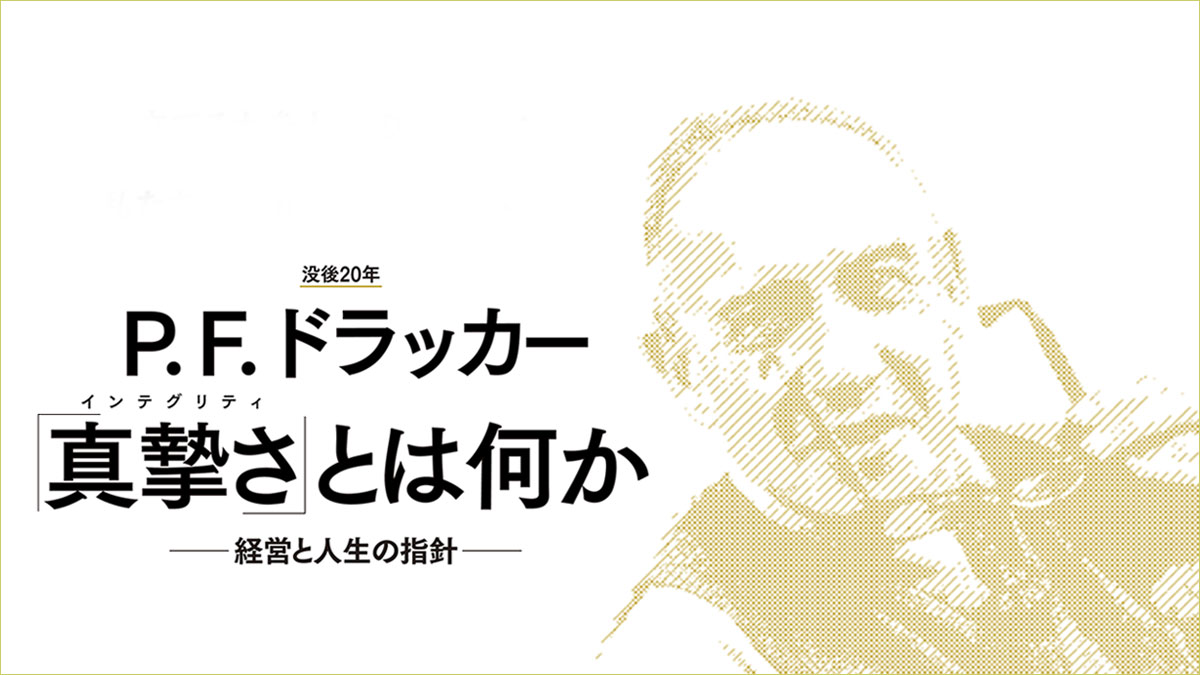
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
ドラッカーが希求した社会の姿とは
ピーター F. ドラッカーが逝去してから、2025年11月で20年が経ちます。「マネジメントの父」と称されることの多いドラッカーですが、それは氏の広大無辺の思想を形成する一面にすぎず、ご本人は「社会生態学者」を自認していました。
2度の世界大戦を経験し、欧州がナチスドイツの全体主義に染まりゆく様を目の当たりにしたドラッカーは、その後英国へ、さらには米国へと渡りますが、その間も一貫して関心を寄せていたのは「社会的存在としての人間の自由と平等」であり、そのために社会、組織、個人はどうあるべきか、何を為すべきかを、数々の著作を通じて世に問い続けました。
今号の特集は、氏の著作にたびたび登場する「インテグリティ」という言葉を手掛かりに、社会生態学者ドラッカーが遺した思想に再び光を当てようという試みです。世界が安定を失い、対話よりも対立が、理解よりも分断が優勢になりがちな時代だからこそ、いまなお輝く巨星の思想の中に私たちがあらためて参照すべき重要な何かがあると、編集部は考えます。
特集1本目「成功できるかではなく、役に立てるかを人生の軸とせよ」は、『ビジョナリー・カンパニー』の著者として知られるジム・コリンズ氏へのインタビューです。いまから約30年前、気鋭の研究者だった頃にドラッカーと出会ったコリンズ氏は、その後の人生を決定づけるような問いをドラッカーから投げかけられたといいます。それは果たしてどのような問いだったのでしょうか。
2本目「世界を揺るがす転換期に私たちはどう向き合うべきか」は、生前のドラッカーと数々の交流を重ねてきた前会計検査院長の田中弥生氏に、ドラッカーの広大な思想がどのようにして成り立ってきたのかを解説いただきました。「マネジメントの父」としてのドラッカーとはまた違った側面が、読み応えのある筆致とともに描き出されます。
3本目「インテグリティとは何か」は、日本語に置き換えることが難しいと言われる「インテグリティ」という概念の本質的な意味を、東京大学教授の中島隆博氏に伺いました。強いて日本語で表現するならば「公共的なものに開かれた立派さ」だという中島教授の解説から、ドラッカーが著作で幾度となく言及したインテグリティという概念の輪郭が浮かび上がります。
4本目「企業は人を幸せにするために存在する」は、インテグリティを体現するような経営スタイルを実践してきた経営者の一人として、ジャパネットたかた創業者の髙田明氏にお話を伺いました。常に目の前のお客様のことを考えてビジネスをしてきたという髙田氏の経営哲学に迫ったインタビューです。
5本目「自分の中にぶれないモラルコンパスを持つ」は、混沌の度を増す今日の国際社会の中にあって、主張や立場の違いを乗り越えて共通の善を追求するために何を重視すべきなのかを、数々の紛争の現場や国際交渉の会議を経験されてきた国連事務次長・軍縮担当上級代表の中満泉氏に聞きました。
特集後半では、ドラッカーが『ハーバード・ビジネス・レビュー』(HBR)に寄稿した34本の論文のうち、編集部が実施したアンケートで読者の皆さんからの得票が多かった「プロフェッショナルマネジャーの行動原理」と、抄訳3本をまとめた「すでに起こった未来へのまなざし」をご紹介します。ご回答いただいた皆さん、心のこもった推薦の言葉とともにご投票いただきありがとうございました。
また特集の締めくくりとして、ドラッカーの95年の軌跡をその全著作とともにたどる年表「ドラッカーの軌跡」をお届けします。折々にドラッカーの歩みを振り返る際の資料として、ぜひ保存版としてご活用ください。
最後に、ドラッカーがその著書『産業人の未来』に寄せた「1995年版へのまえがき」の中から、こんな一文で締めくくりたいと思います。「今日われわれが直面している問題は、50年前のものとは異なる。だが、その解決のための原理は同じである」
(編集長 常盤亜由子)






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









