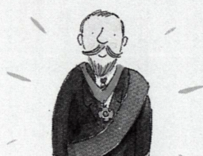職場の安全性を高める体系的アプローチ
W. エドワーズ・デミングの有名な言葉がある。職場における問題の94%はシステムに起因し、個人レベルの特異な要因に起因するものはわずか6%にすぎない、というものだ。いじめのあらゆるタイプと、あらゆる表れ方に対処するためには、いじめの防止に焦点を当てた体系的なアプローチが求められる。
いじめを行う人の特性も関係するとはいえ、いじめは、その発生と継続を許容する組織環境によって機会が生じた結果の行動である。人間の本質であるエゴイズムを消し去る力は組織にはないが、利己的な行動を強化する代わりに、抑制するようなシステムを構築することは可能だ。
いじめを防止する効果的な組織体系を、ゼロから設計する必要はない。非同期作業による生産性を支え、インクルーシブで心理的に健全な組織であり続けることを促進する仕組みは、いじめ防止においても重要な役割を果たす。効果的ないじめ防止の仕組みは、組織的な正義や透明性、結果重視、意思決定における有効な手段の使用に根差している。また、インクルーシブで柔軟な働き方、発言、参加を促すようなツールにも支えられている。
敵対的ないじめへの対処:スクリーマーを阻止する
敵対的、感情的いじめの防止は、選考と訓練によって、個人レベルである程度は実現できる。組織は、業績不振との関係が明らかな否定的特性(リーダーシップにおける傲慢さなど)に基づいて人材を合法的に選別することが可能であり、またそうしなければならない。
非暴力的なコミュニケーションについて従業員を訓練することも、重要な手段の一つだ。たとえば、基準に満たない仕事に対するコミュニケーションは、暴力的でいじめにつながりやすい。
「これを報告書だと言うのですか。こんな報告書を用意するとは侮辱的です。報告書の書き方を知らないのですか」
同じ内容でも、以下のように非暴力的に言い換えることが可能だ。
「この報告書のドラフトを転送、使用できないのが残念です。明瞭な報告書が必要なのです。数値データを表にして、4~5つの箇条書きにしてください」
システムの視点で見ると、敵意は通常、リソース不足と全体的なストレスによって喚起される。現実的でない納期、職場の「ハンガーゲーム」につながる慢性的なリソース不足、恐怖を用いたマネジメント、道徳的妥協などのストレスを軽減すれば、敵対的いじめの減少に役立つ。
手段を用いたいじめへの対処法:スキーマーを阻止する
間接的に、隠れて行われるいじめを防止するためには、組織は報酬の獲得方法について透明、公正、公平、かつ正当な基準を用意する必要がある。昇進やリソースの配分、その他の重要な決定は、透明かつ正確に測定された業績に基づいて行われるべきだ。「目分量」で業績を判断すると、 自慢話や横取りした手柄、中身に関係なく外見上存在するだけの特権に報酬を与えることになってしまう。
さらに、組織の意思決定において公正さを担保するには、必要な場面(先述したノアの事例のように、判断の根拠となった情報が不完全だったり虚偽だったりした場合)で重要な決定を訂正できる仕組みが必要だ。たとえば、独立した第三者組織(オンブズマン委員会など)が降格や段階的懲罰を裏付ける根拠を検証できるとよい。
具体的な仕組みは組織のタイプ(国営、民間、組合など)や雇用形態によって異なり、特定のタイプの従業員(職種別従業員か否か、給与制か時間制かなど)を対象とする苦情処理委員会の形を取ることも多い。いずれにしても、苦情処理およびチェック・アンド・バランスの仕組みがあれば、出世のためにいじめを行うというインセンティブを抑制できる。
また、タスクボードや共有ドキュメントといった非同期型の業務ツールも、手柄の横取りや不当な評価といったいじめの防止に役立つかもしれない。そのようなツールは、生産性向上という役割に加えて、業績や貢献度を記録する役割も担う。
実証されたスキルや結果、他者をサポートする力(自分をアピールするのではなく)に焦点を当てた、有効かつ適切に設計された採用、選考、人材マネジメントの仕組みも、ポジティブな組織風土を構築するうえで重要な役割を果たす。
このような仕組みがあれば、いじめにつながる行動を早期に発見し、手柄を横取りする人や自信過剰で能力が不足している人の採用・昇進を阻止できる。たとえば、採用候補者に失敗の経験や他者を成功に導いた経験を語ってもらうことで、その人の謙虚さや自己認識、他者への姿勢を推し量ることができる。








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)