
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
多くの企業がレイオフを発表
最近はニュースを読めば、嫌でもレイオフに関する記事が目に入る。2022年12月には、モルガン・スタンレーが2%、バズフィードが12%、ペプシコが数百人の人員削減計画を発表した。同じように、不動産仲介のレッドフィン(Redfin)(13%の人員削減、以下同)、ライドシェアのリフト(13%)、オンライン決済のストライプ(14%)、写真共有アプリスナップチャットのスナップ(20%)、オンライン不動産売買のオープンドア(Opendoor)(18%)、メタ(13%)、ツイッター(50%)も人員削減を行っている。
あまりに多くの企業がレイオフを実施したため、IT系や人事系企業の起業家がTrueUp TechやLayoffs.fyiといった、ITセクターにおける人員削減の推移をトラッキングするサイトを立ち上げたほどだ。
不況になると、企業はレイオフを経費節減の手立てにする。人員削減が財務改善の最も手っ取り早い、最良の方法だという考えに、いまだにしがみついているのだ。
筆者らは、2009年からレイオフに関する研究を行っている。2018年にHBRへ寄稿した記事では、レイオフによる短期的なコスト削減よりも、それによる企業イメージの低下、知識の喪失、エンゲージメントの低下、自主退職者の増加、イノベーションの停滞のほうがいかに重大な問題であるかを述べた。これらはすべて、企業の長期的な利益を損ねている。
今回のレイオフに見られる特徴
このような悪影響は、4年経っても変わっていない。しかし、レイオフを取り巻く社会情勢は、この間に大きく変化している。今日における経済的混乱の中で、知的かつ人道的な人事決定を行うには、まず、最近の3つの傾向を理解する必要がある。
噂の広まるスピードが増した
コロナ以前の従来のオフィス環境では、上司との予期せぬミーティングから戻った同僚の動揺した顔を見て、人員削減の噂が広まったことだろう。
いま、同僚とは離れた場所で仕事をしているかもしれないが、スラックやチームズのメッセージ一つで、世界中の何万人もの従業員が同時かつ瞬時にレイオフの噂を聞き知る。企業が望むと望まざるとにかかわらず、コミュニケーションは社内外を問わず、従業員からSNS、ジャーナリスト、特定の業界やそこで働く人々を対象とした業界メディアへと広がっていく。
企業の意思決定は詳細に調べ上げられる
企業はこれまでも、みずからの行動の正当性を示す必要があったが、今日、企業の説明は、従来のメディアとSNSの両方で広範な精査にさらされる。製品やサービスが人々の日常生活に深く浸透し、そのリーダーが有名人となっているIT企業は特にそうだ。どのSNSを見ても、顧客が企業の取る戦略に素早く反応し、強い意見を表明していることがわかる。
レイオフにまつわる恐ろしいエピソードは、いつの時代も驚くほど簡単に見つかる。かつて、従業員を2つのグループに分けた会社の話を聞いたことがある。片方の部屋には、クビを告げられた人たちが集まっていた。そのすぐ隣の部屋では、首のつながった人たちに、誰かが隣に聞こえるほど大きな声でこう言っていたという。「君たちは勝者だ。君たちのおかげで、会社はもっと繁盛できる」
いまや従業員を不適切に扱うことは、近視眼的であり、企業の利益に反している。かつては、会社が人員削減を決めても、労働者の権利を擁護する少数の人々が抗議しただけだった。いまは、SNSのおかげで、誰もが人員削減の決定に異議を唱え、こう問うことができる。「そんなことをする会社では、誰も働きたがらないということがわからないのだろうか」

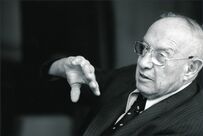





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









