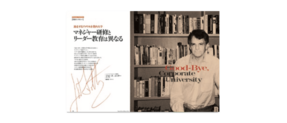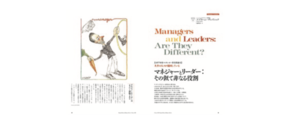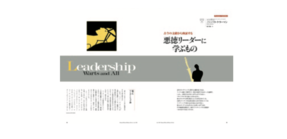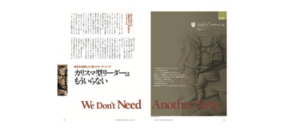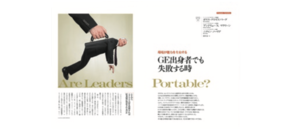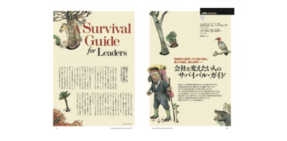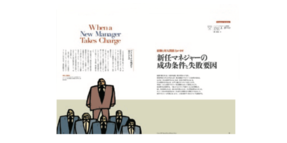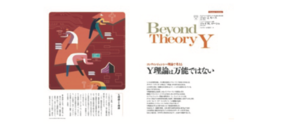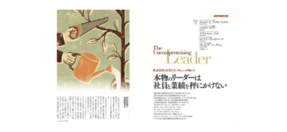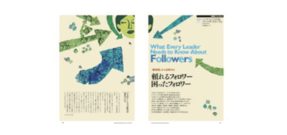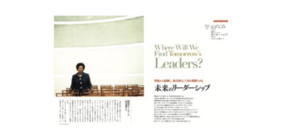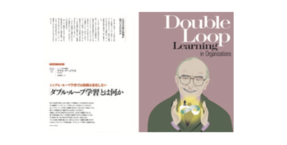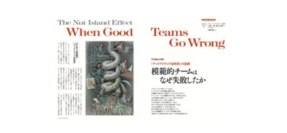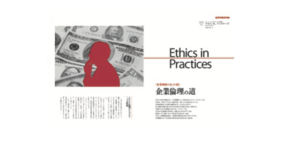-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
組織における対話の重要性
会議では伏せられた問題が後で浮上したり、実行に移されなかったりする「誤った意思決定」には共通点がある。それは社内の対話が不毛であることだ。
人間同士の対話は何らかの結果を生み出すはずなのに、不毛な対話のために十分な意思疎通が図れず、断固とした行動を取れないケースが多い。
断固たる行動が取れない原因は、組織風土にある。そうした風土をつくり出したのはリーダーだが、またそれを変革できるのもリーダーである。
変革の主要な武器となるのは、人間同士の相互作用、すなわち対話である。固定観念に挑むのかどうか、情報を分かち合うのかどうか、不協和音を表面化させるかどうか。いずれも対話を通じて行動に移される。
組織では、対話は仕事の基本要素である。人を集めてどのように情報を加工するのか、意思決定をいかに下すか、そしてお互いについてどのように感じ、決定内容についてどう思うのか。これらは対話の質によって決まる。対話をきっかけに新しいアイデアが生まれ、それにはずみがつき、市場における競争優位につながる。
対話は、知識労働者の生産性と育成の礎となる最も重要な要素である。まさに、対話の中身とスタイルが社員の行動や信念、すなわち組織風土を形成する。その影響は、私のこれまでの研究において給与体系の変更や組織改革、将来構想などよりも、いち早く表れ、かつ永続する。
優柔不断な組織風土を改めるには、社員に率直な態度を学ばせ、信頼関係を育むリーダーが必要である。社員と接触するたびに、その機会を利用して、オープンで正直、かつ意思決定を導く対話とはいかなるものかを示すことにより、リーダーは組織全体の対話スタイルを確立できる。ただし、対話スタイルの確立は、優柔不断な風土を変革するための第一歩にすぎない。
次のステップは、「組織運営メカニズム」で率直な対話が交されるようにすることである。ここでいう組織運営メカニズムとは、経営委員会、予算および戦略レビュー会議など、企業にとって重要事項を決定する場のことである。このようなメカニズムが対話の場となる。