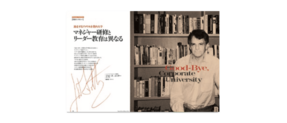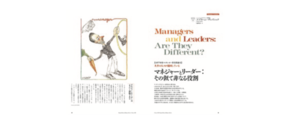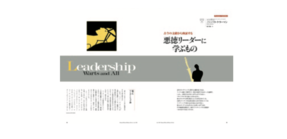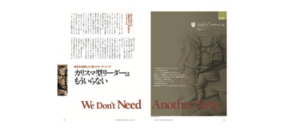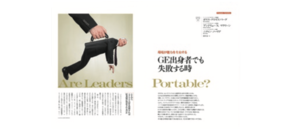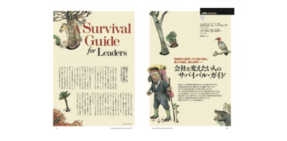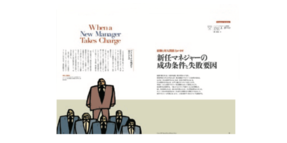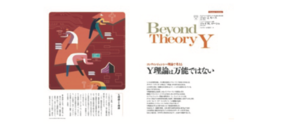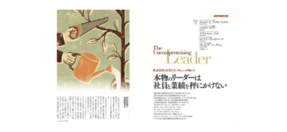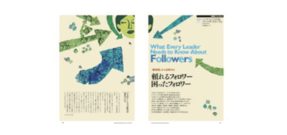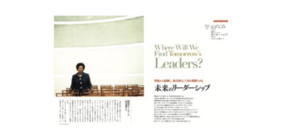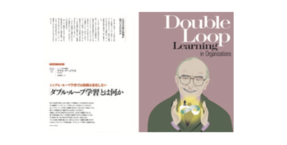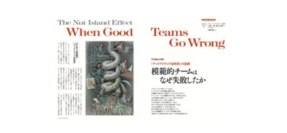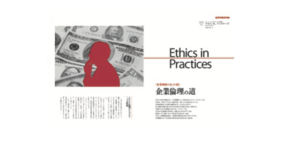-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
企業組織では倫理観が失われやすい
情報が具体的で、選択肢が白黒はっきりしているならば、道徳的な判断を下すのも簡単である。しかし、あいまいな情報、不完全な情報、さまざまな立場、矛盾する責務などが絡んでくると話はまるで違ってくる。そのような場合──現実はいつもそうだが──道徳上の判断を左右するのは、意思決定プロセスそのものと、意思決定者の経験、知性、良心である。
しかるべき道徳的判断力は、一朝一夕に身につくものではない。企業のなかでこの能力を育んでいくのは、ある面、次の要素からなる一連のプロセスである。
すなわち、ある意思決定を社会道徳に照らしてその意味を知ること、討論によって違った視点の存在に気づくこと、暫定的な決定が適正かどうか、「自己の利益と周囲への配慮のバランス」「将来的な施策の重要性」「企業の価値観との調和」という3つの面から確認することである。
しかし、このような努力を払っても、はっきりとしたコンセンサスが得られないならば、最終的な責任を負う者がみずからの直感と信念に基づいて、決断を下さなければならない。したがって、意思決定者の度量がきわめて重要になる。
道徳的に意思決定するには、意識して育成すべき資質が、少なくとも3種類必要になる。
第1は、道徳上の問題を認識し、さまざまな解決方法が及ぼす影響を見通す能力である。第2は、異なる視点を求め、あるタイミング、ある場面で、また特定の関係や状況のなかで、何が正しいかを判断する自信である。
そして第3は、ウィリアム・ジェームズの言うところの「強靭な精神力」(tough-mindedness)である。企業経営の文脈に照らせば、知っておくべき情報が不十分な場合、目の前の問題について、満場一致で決まった解決法がない場合、敢然と決断を下せる資質である。
残念ながら、現代企業において道徳的な人間は孤立していることがあまりに多い。いかにこのような資質に恵まれた道徳的な人物でも、組織からしかるべき支援がなければ、いつも自律的に行動することは難しい。