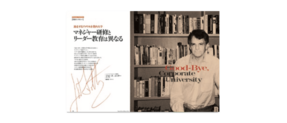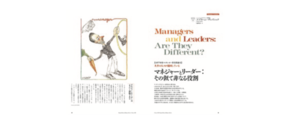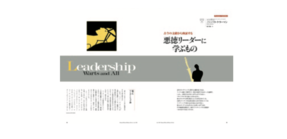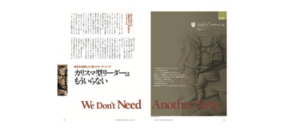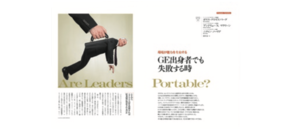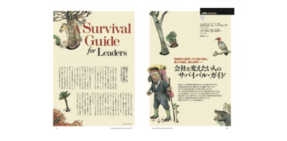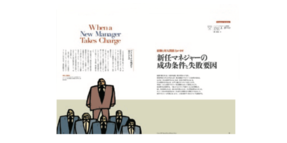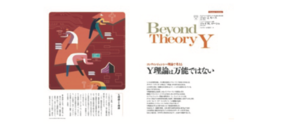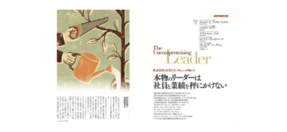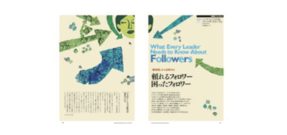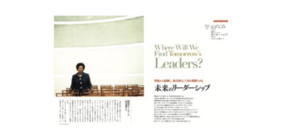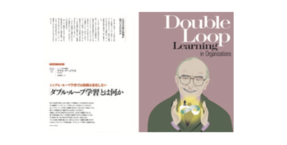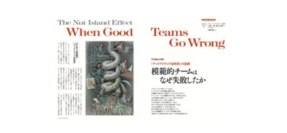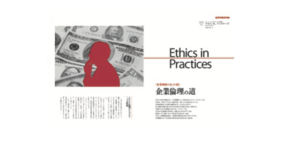-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
学習する組織の3つのM
『最強組織の法則』[注1]を著し、学習する組織という言葉を世に広めた、マサチューセッツ工科大学のピーター M. センゲは、その著作のなかで、学習する組織を「人々が継続的にその能力を広げ、望むものを創造したり、新しい考え方やより普遍的な考え方を育てたり、集団のやる気を引き出したり、人々が互いに学び合うような場」と定義している。
学習する組織については、野中郁次郎も「知識創造企業」というコンセプトを提唱し、「新しい知識を創り出すのが何も特別なことではなく、その組織のなかではだれもが知を生み出す成員として振る舞い、存在するような組織」と定義している[注2]。
とはいえ、これらの定義は抽象的もしくは理想的であり、具体的なところがわかりにくく、なかなか実際的な行動指針とはなりにくい。たとえば、どのような状態が学習する組織と呼べるのか、具体的にどのような行動の変化が必要なのか、どのような方針や転換プログラムが必要なのかといった問いには答えてくれない。
学習する組織の具体的な姿を考えるには、次の3つの重要な点をクリアしなくてはならない。
第1が「定義」(meaning)である。我々には、学習する組織について納得できる、十分検討された定義が必要である。それは行動指針となり、適用も容易でなければならない。
第2が「マネジメント」(management)である。我々には、抽象的な理念よりも実務家のために具体的な行動基準を提示する必要がある。
そして第3に、学習する組織の完成度を高めるための「業績評価指標」(measurement)を明らかにする必要がある。
[第1のM]
定義
驚くことに、学習に関する定義はいまでも判然としない。組織論の研究者の間でもいろいろな見解が錯綜しているのが実情である(図表「組織学習に関する定義」を参照)。組織学習が知識の習得と業績向上に関する長期的なプロセスであるという点では、おおむね合意しているようだが、そこから先は見解が分かれる。