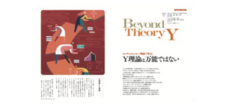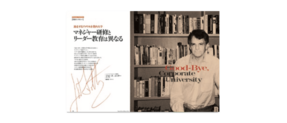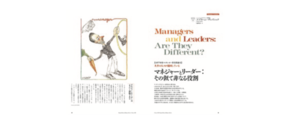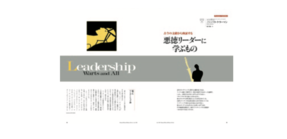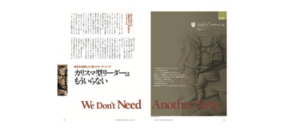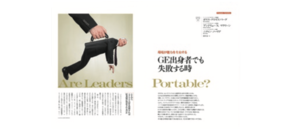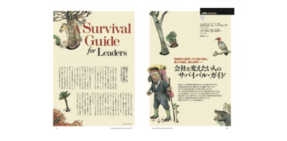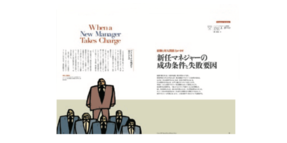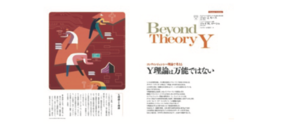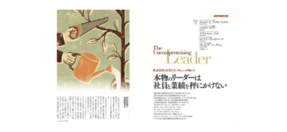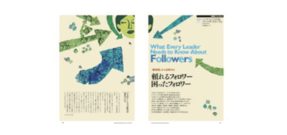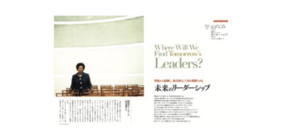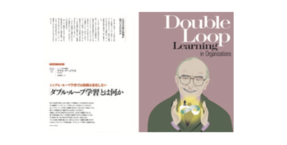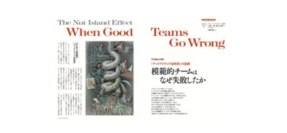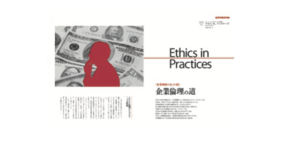-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
MBOの欠点
「目標管理」(MBO:management by objectives)というコンセプトは、もはやマネジメント・プロセスに欠かせなくなっている。
にもかかわらず、MBOに抱いている思惑とは裏腹に、あまりうまく機能していない。その根本的な理由は「相手は人間である」という視点がまったく抜け落ちているからである。
この視点がいかに抜け落ちているかを見るために、典型的なMBOプロセスをたどってみよう。通常、トップ・マネジメントは来たる1年間に向けて全社目標を掲げる。ROI、売上高、生産高、成長率そのほか、測定可能な目標となるだろう。
これらの参考指標それぞれにおいて、各事業部のマネジャーは、全社目標の達成のために、自部門がどれだけ貢献するかが問われる。あるいは、全社目標とはあまり関係のない、独自の目標が求められるかもしれない。後者の場合でも、とにかく前年より高い目標が期待される。
またその範囲にしても、全社活動の一翼を担うこと、あるいは具体的な統計数値を改善することに限定されるのが普通である。場合によっては、何らかの研修を受講したり、特定のスキルを獲得したりすることも含まれるかもしれない。
各事業部の管理職が自部門の目標を設定し、上からの承認が下りれば、これが彼ら彼女らの目標となる。おそらく、これら管理職は自分が達成したい目標に絞るだろう。そして、その目標を公にすることで、この責任を引き受ける。以後管理職は、自分の言葉によって縛られた状態になる。
では、このプロセスを詳細にわたって再検討してみよう。この一連のプロセスは、全体的に短期志向であり、しかも自己中心的な視点に基づいており、なおかつその根底には「報酬か懲罰を与える」という心理がある。
典型的なMBOプロセスでは、各事業部の管理職たちを、言わば迷路のなかのネズミとほぼ同じ立場に置く。彼ら彼女らは、2つの選択肢のどちらかしか選べない。ネズミを迷路に置いた実験者は、ネズミがエサという報酬を選択するものと想定している。そう想定できない場合は、ネズミがエサをほしがるように飢えさせる。MBOがこれと異なる唯一の点は、管理職たちが自分のエサを選べるところにあるが、その範囲は限られている。