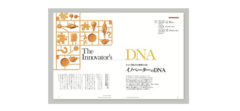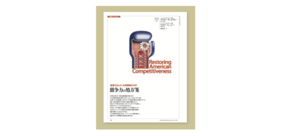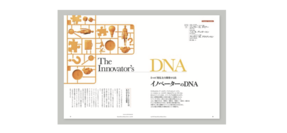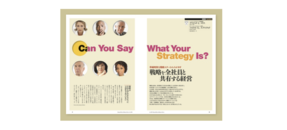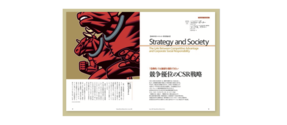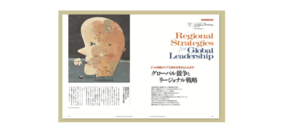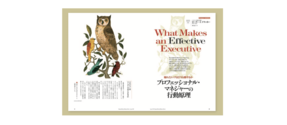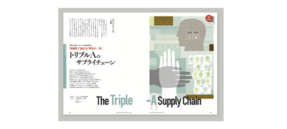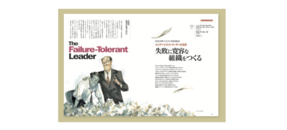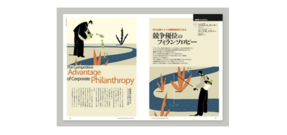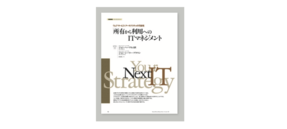-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
新興国市場に「企業帝国主義」は通用しない
多国籍企業が成長源を探し求めるならば、中国やインド、インドネシア、ブラジルで台頭しつつある巨大市場で競争しなければならなくなる。ここでのキーワードは「新興」(emerging)である。
何億人という巨大な顧客基盤が急速に発展しつつある。他国企業にすれば、これらの市場はいまだ不透明であり、事業を展開するには不確実性や難問を覚悟しなければならないが、それでも欧米の多国籍企業は参入せざるをえないだろう(図表1「新興国市場とアメリカ市場の比較」を参照)。
市場参入の第1波が起こったのは1980年代で、その間、多国籍企業はいわゆる「帝国主義」の態度で事業を運営していた。すなわち、これら巨大新興国市場を、既存製品向けの新市場と見なしていたのである。既存製品の売上げが右肩上がりで増えていく、斜陽技術から利益を絞り出せると、ぼろもうけをもくろんでいた。
くわえて、製品やプロセスのイノベーションの中心はやはり本社であると考えていた。また多国籍企業の大半が、グローバル展開に資する技術者や経営者人材の宝庫として、新興国市場に目を向けることはなかった。こうした帝国主義的な考え方のせいで、多国籍企業は新興国市場でそこそこの成功しか収めていない。
しかし現在、多くの企業が、巨大新興国市場でチャンスをつかむには発想の転換が不可欠であると気づき始めている。ただし、異文化への感受性を高めるだけでは、成功はおぼつかない。