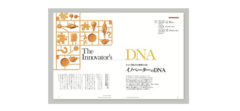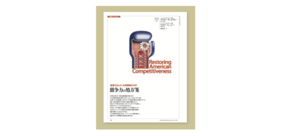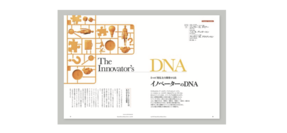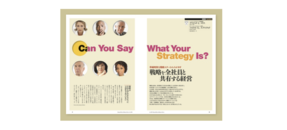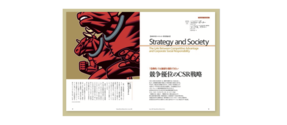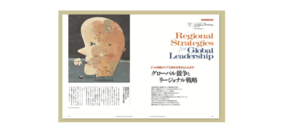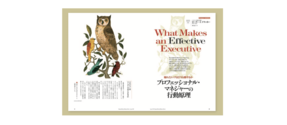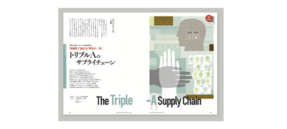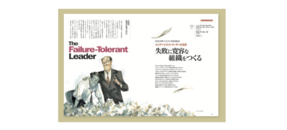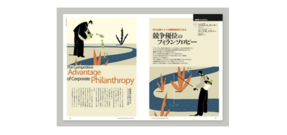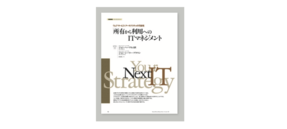-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
なぜ企業は早死にしてしまうのか
組織の世界において、営利企業は新参者である。企業が存在するようになって、たかだか500年ほどにすぎない。人類の文明史のなかで、ほんの一時のことである。企業はこの間、物質的な富の創造者として、あり余る成功を収めてきた。文明的な生活を可能たらしめる財やサービスを提供し、世界的に急拡大する人口を支えてきた。
しかし、その可能性を鑑みれば、ほとんどの営利企業がその真価を発揮できずにいる。企業はまだ進化の初期段階にあり、潜在能力のほんの一部しか開発・活用していない。
ここで、企業の「死亡率」の高さについて見てみよう。1970年時点の「フォーチュン500」の3分の1が、83年までに、買収されたり分割されたり、あるいは他社と合併している。
こうも多くの企業が「早すぎる死」を迎えるのは、どういうわけだろう。こう考えるのも、企業寿命はもっと長いという証拠があるからだ。
日本の住友グループの起源は、1590年に蘇我理右衛門(そがりえもん)が興した銅精錬業にさかのぼる。また、いまや紙・パルプおよび化学企業の大手であるストゥーラエンソは、700年以上前に、スウェーデン中部の銅山採掘会社として設立された。これらの例などは、企業の天寿は2、3世紀もしくはそれ以上である可能性を示している。
この統計値を見て、意気消沈するかもしれない。住友やストゥーラの超長寿と平均的企業の短命とのギャップは、企業の潜在能力が目減りしつつあることを表している。企業の早すぎる死は、個人、地域社会、経済すべてに影響を及ぼし、壊滅的打撃を与えることすらある。