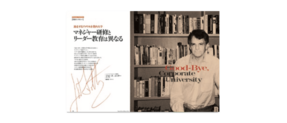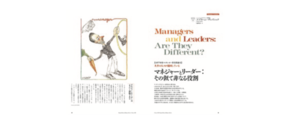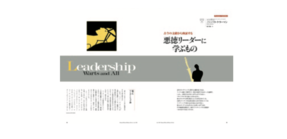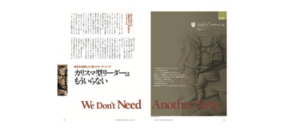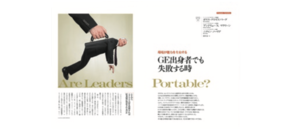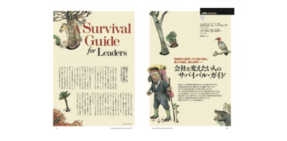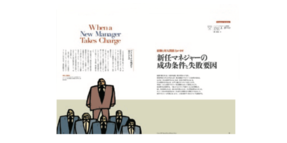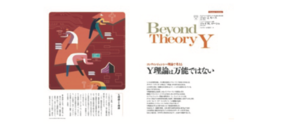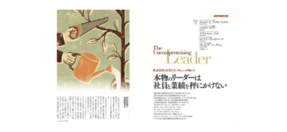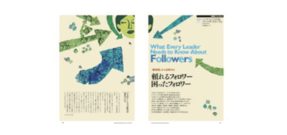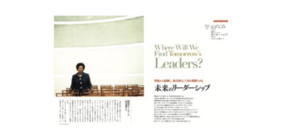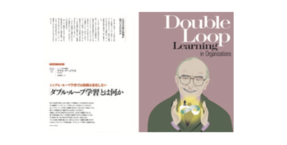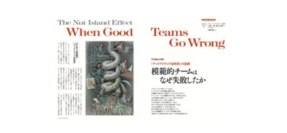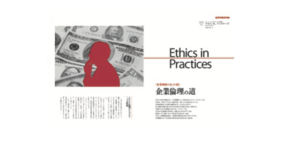-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
やる気は次第に失われ
高原状態に至る
成長が見られないからといって、即引退と考えるべきではない。アメリカの大企業は終身雇用制ではないが、そこで働くマネジャーのほとんどが1社のみに勤続して、ビジネスマンとしての生涯を終える。さらにその多くが、最後の10年ないし20年間を、さしたる成長がないままに過ごす。
このような高原状態が一般的なミドル・マネジャーとはいえ、依然生産的である人も少なからず存在している。その一方、とても生産的とはいえない人々も存在している。
長期雇用が広く一般化するにつれて、幹部社員の多くが、それ以上の昇進がもう望めない高原状態に達するのは不可避といえよう。なぜなら、社員が組織の階段を上れば上るほど、ピラミッドの幅は狭まり、昇進の機会は限られてくるからだ。
経営陣のなかには、情熱を失ったマネジャーを「いなくても差し支えのない人間」と決めつけて、何とか追い出せないものかと考える人が多い。これらの経営者が忘れていることは、長期勤続社員が実は組織の中核を成しており、日常業務を取り仕切っているかもしれないという点である。
このような人々の追い出し策を考える代わりに、トップ・マネジメントは別の解決策を考えるべきだ。会社生活の後半に差しかかった、これら高原状態にあるマネジャーのやる気をいかに甦らせ、刺激と動機づけを与え、それを持続させればよいだろうか。マネジャーの燃え尽き症候群を回避するために、いったい何ができるのだろうか。
主流の仕事か
傍流の仕事か
高原状態に達したマネジャーでも、その身を捧げる意欲を保ち続ける人が存在する半面、同じ作業をただ繰り返している人もいる。
その違いを考察するべく、東京に本社を構える某メーカーで技術系マネジャー30人を調査した[注1]。これらのマネジャーは勤続年数16~25年だったが、仕事の内容と会社への態度がまったく違う2つのグループに分かれた。
一方のグループは、自身の仕事と会社の将来に意欲的な姿勢を見せ、積極的に会社との関係を深めていたが、もう一方は受け身的で、自分の仕事や会社への関心は高くなかった。