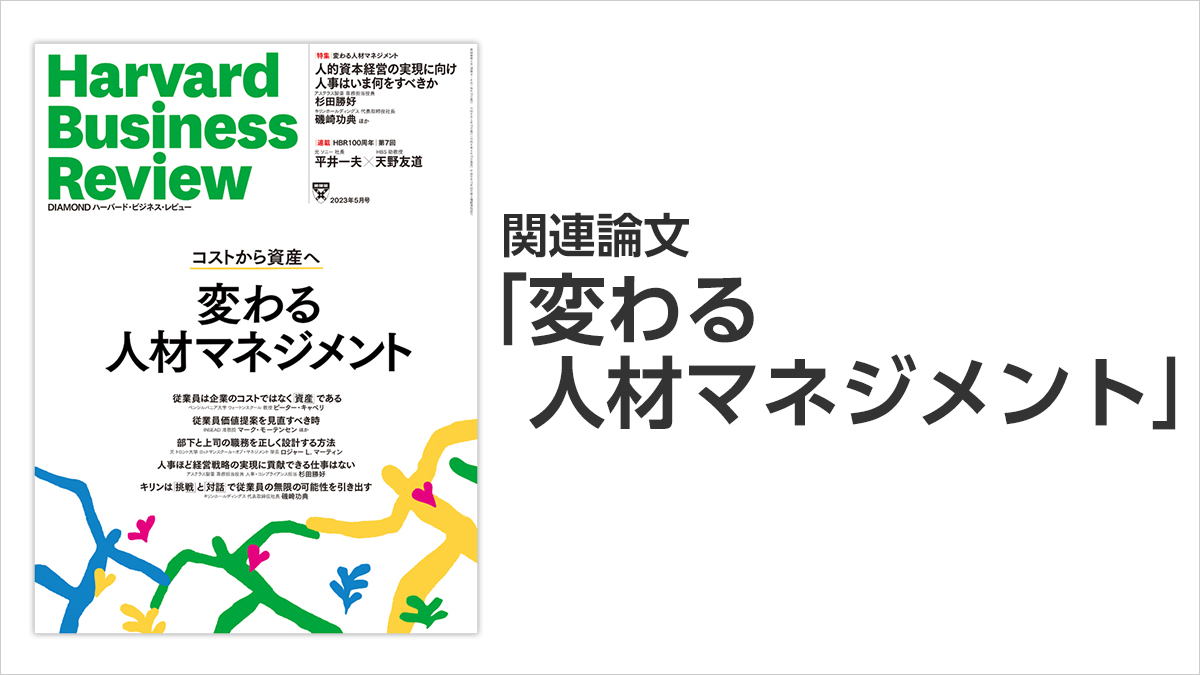
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
DHBR2023年5月号の特集は「変わる人材マネジメント」。多くの企業が人的資本経営の実現を目指しているが、そのためには金銭的条件を整えるだけでは十分でなく、個々人に適した仕事を設計するなど、従業員の潜在能力をフルに発揮できる環境づくりが求められる。
米国には好ましくない人事慣行が数多くある。たとえば、社員の能力開発に投資せず、業務を積極的に外に出すといったことだ。ペンシルバニア大学ウォートンスクール教授のピーター・キャペリは、こうした行為が企業の競争力を落とす原因になると指摘する。その背景には、米国財務会計における人的資本の扱い方をめぐる課題があるという。
「従業員は企業のコストではなく『資産』である」では、社員への投資が費用ないし負債として扱われることで、いかに経営判断がゆがめられているかを述べる。さらに、報告基準のわずかな変更によって、人的資本の活用が進み、企業業績にプラスの影響がもたらされる点を強調する。
いまや人材を引き寄せ、つなぎ留めることが経営上の大きな課題となっている。しかし、報酬やリモートワークなどの物理的待遇は他社に模倣されやすく、根本的な解決策とはならない。
INSEAD准教授のマーク・モーテンセンらは「従業員価値提案を見直すべき時」の中で、従業員が潜在能力をフルに発揮できる環境を目指して、従業員への価値提案──相互に結び付いている4つのファクターから成るシステム──を設計し、導入することが必要だと主張する。それこそが、組織が長期的に繁栄するための秘訣である。
部下にどのような職務を与えるかで、仕事の生産性は大きく変わる。やりがいがあっても達成不可能だったり、達成可能でもやりがいが乏しかったりすれば、前向きに取り組むことができず、部下は自分の職務を再定義して、上司の期待とは異なる成果を上げようとするだろう。これは部下にとっても上司にとっても好ましいものではない。
部下だけでなく上司も同様だ。部下から提案された職務にやりがいを感じられなければ、あら探しを始めかねない。
元トロント大学ロットマンスクール・オブ・マネジメント学長のロジャー L.マーティンによる「部下と上司の職務を正しく設計する方法」では、このような事態を避けるために、部下と上司それぞれが担うべき職務を正しく設計する方法を紹介する。
経営戦略と人材戦略の連動が重要とされ、日本では人的資本経営として注目を浴びている。ただし、従業員が会社に求めるものが大きく変化する中、会社の要求を一方的に押し付ければ、優秀な人材を採用できなかったり、流出したりするリスクはますます高まる。
組織のミッションを達成するだけでなく、従業員のニーズも満たすために、人事は何をすべきなのか。「人事ほど経営戦略の実現に貢献できる仕事はない」では、日本マイクロソフトやアストラゼネカなど数々の企業で人事の責任者を務め、現在はアステラス製薬の専務担当役員 人事・コンプライアンス担当を務める杉田勝好氏に話を聞いた。
企業は外部の優秀な人材を惹き付け、従業員の潜在能力を引き出すことで、変化の激しい時代を乗り越える必要性に迫られている。その大きなカギが、外部の人材や従業員から共感を得られるパーパスの存在だ。
キリンホールディングスの磯崎功典社長は、日本でいち早くCSV経営を導入したうえで「健康」をキーワードに事業を再編し、仕事を通じて社会に貢献したいと考える人々の共感を集めて、新たな挑戦に取り組んできた。
一連の改革により、従業員エンゲージメントも向上しているというが、「キリンは『挑戦』と『対話』で従業員の無限の可能性を引き出す」では、どのように人材の才能を活かしているのか、磯崎社長に話を聞いた。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









