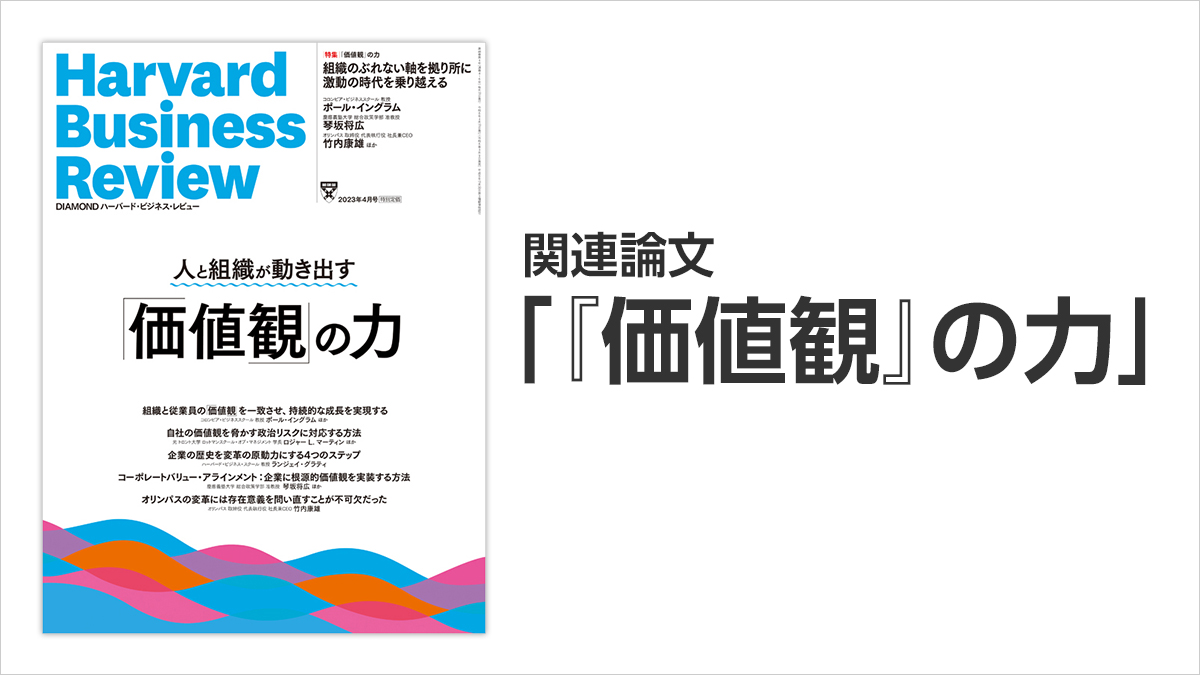
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
DHBR2023年4月号の特集は「『価値観』の力」。経営環境の変化に柔軟に適応していくには、組織の多様性を高めつつ、意思決定を迅速化することが求められる。その際、組織をまとめ上げる際の軸となるのが自社の「価値観」である。
組織と従業員個人の価値観が一致すると、離職率の低下や生産性の向上などあらゆる面で大きな恩恵が受けられる。変化の絶えない時代を乗り越え、持続的成長を実現するためには、組織と個人の価値観を整合させる「バリュー・アラインメント」が欠かせない。
コロンビア・ビジネススクール教授のポール・イングラムらによる「組織と従業員の『価値観』を一致させ、持続的な成長を実現する」では、それを実践するための5つのステップを紹介する。重要なのは、まず従業員の価値観を明らかにすることである。
企業がビジネス上の判断を行う際、政治的な問題を考慮せざるをえない時代になった。ウォルト・ディズニーやH&M、マクドナルドなどの企業が、政治絡みの問題に巻き込まれ、事業の継続や収益に重大な影響が及んでいる。ビジネスと政治は切り離せる、むしろ切り離すべきだという考えは、もはや現実的ではない。
元トロント大学ロットマンスクール・オブ・マネジメント学長のロジャー L.マーティンらによる「自社の価値観を脅かす政治リスクに対応する方法」では、スターバックスやデビアス、シーメンスなどの事例を交えながら、倫理、社会、政治的課題がたえず変容する環境下で、最善の戦略的選択を行うためにリーダーが実践すべき5つの方策を解説する。
業界や経済が目まぐるしく変化する中、たいていのビジネスリーダーは、過去はイノベーションを妨げるものだととらえ、未来に目を向けることが重要だと考える。
しかし、筆者が数十年にわたり世界中の企業を研究した結果、企業の歴史は戦略やモチベーションの源泉になりうることがわかった。創業当時の理念や精神をより深く理解し、その知識をもとに今日のミッションやバリューを明確にしている企業は、危機を乗り越え、大きな飛躍を遂げる。
ハーバード・ビジネス・スクール教授のランジェイ・グラティによる「企業の歴史を変革の原動力にする4つのステップ」では、カールスバーグ、レゴグループ、ジョンソン・エンド・ジョンソンなどの事例に触れながら、自社の歴史を活かすための4つのステップを解説する。
現代の予測不可能な経営環境において、変化に柔軟に適応し、持続的な競争優位を確立するには、組織の多様性を高めたり、意思決定を機動的に行ったりすることが不可欠だが、多様性が高まるほど意見の集約は困難になる。
その際、各自がコーポレートバリュー(企業の根源的価値観)を理解していれば、それが思考や判断の軸となり、機動的な意思決定を実現しやすい。しかし実際には、コーポレートバリューが適切な表現を用いて定義されていなかったり、組織に網羅的に実装されていなかったりするため、多くの企業が十分に活用できていない。
慶應義塾大学総合政策学部准教授の琴坂将広氏らによる「コーポレートバリュー・アラインメント:企業に根源的価値観を実装する方法」では、コーポレートバリューの構造的な理解を示したうえで、それらの課題を解決するためのフレームワークを提示する。
オリンパスは2011年に発覚した粉飾決算事件で株価が暴落し、存続すら危ぶまれる状況に陥ったが、近年の業績は好調に推移し、2022年度は過去最高益を記録、2023年度も最高益を更新する見込みだ。
同社の変革を成し遂げ、再建を果たした立役者の一人が、現社長兼CEOの竹内康雄氏である。竹内氏は事件を機に変革の必要性を感じたわけではなく、オリンパスの経営を幅広い視野でとらえ、グローバル企業としてあるべき姿を描く過程でいくつもの課題を発見し、それらをどのように解決すべきか考え続けてきた。
「オリンパスの変革には存在意義を問い直すことが不可欠だった」では、親会社と子会社が独立した経営を行うローカル企業の集合体から、国境を超えたシナジーを発揮する真のグローバル企業に生まれ変わるために、オリンパスの変革をどのように進めてきたのか、竹内氏に聞いた。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









